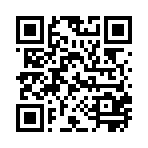2019年09月18日
受賞者インタビュー(1) キュイ 綾門優季さん(劇作家賞)
・まずは受賞されての率直な感想をお聞かせください。
今回のこの受賞インタビューを、たまたま僕のスケジュールの都合でコンクールの受賞発表から10日後※に受けているんですが、この10日間のうちに未曽有の出来事が起きまして、これを避けては今回の作品についてはもう、喋ることが出来ないだろうというのが率直な気持ちです。(※綾門さんには後日インタビューにご協力頂きました。)
その事件というのは、ご存知の方も多いと思いますが、京アニで起きた放火事件です。
まだ事件から一週間も経っていないくらいなので、連日の報道で死者も増えていきますし、まだ全然気持ちの整理がついていない状況です。深い悲しみの中にいます。
Twitterでもちらほら見かけたんですが、今回の『蹂躙を蹂躙』を観た方の中で、事件のニュースを観た瞬間に、作品のことを思い出した、という方がいらっしゃいました。実際、あまりにも連想しやすい作品だったと思っています。
他でもない作者の僕が、事件のことを知った瞬間に『蹂躙を蹂躙』のことを強く想起し、悲しみに暮れたくらいなので、それはたぶん、今回の座組のみなさんにも、劇場で作品を観た方にも、少なからず起きた現象なのではないかと推測しています。
今回、劇作家賞に選んでくださった審査員の方々にはすごく感謝の気持ちはありますし、劇場に足を運んで作品を観ていただいた、観客の方々にも感謝の気持ちはあるんですけど、気持ちは今、物凄く沈んでいます。
コンクール当日にこのインタビューを収録していたら、もしかしたら「やったー!」って言っていたかもしれないんですが、今ではどうにも無理な気持ちになってしまいました。喜びの気持ちが全くなくて、毎日、事件のことばかりを考えて、心の痛みが酷いです。
受賞インタビューなのに申し訳ないんですけど、それが今の率直な気持ちです。
・ありがとうございます。キュイという演劇プロデュースユニット、そして劇作家としての綾門さんの創作のテーマやコンセプトについて、あらためて教えてください。
キュイとしての活動としては9年目に差し掛かります。これまでにすべての作品でテロを扱ってきたわけではもちろんないんですが、それでも数作品、片手で余る数を上演してきたわけで、割と頻繁にテロをテーマに扱ってきていると言っていいと思います。
もちろん、直接的にテロを扱った作品を観ていて楽しいわけがないし、観客の方から「せっかく劇場に来たのになんで楽しい作品じゃないんだ!」的な文句をいただくことは実際、以前もあったんですよね。
特に今回、普段の公演に比べてキュイの作品を初めて観た方が多かったと思いますし、しかもコンクールのトップバッターだったので「……え?」という空気が流れました。出演者の方たちも、舞台上で少なからず感じたと言っていました。
あとはキュイっていう名前だけ知っていたり、綾門の名前だけは知っていたというような人たちが、実際に初めてキュイの作品を観てびっくりしちゃった、ということもよく起きます。思ってたのと違う、ってやつですね。こういうものだとは事前に想定しないから。
それについて一貫した主張として思うのは、今、日本の社会がいい方向に向かっているとはあまり捉えていないんですね。なんだったらだんだん邪悪な方向に向かっているんじゃないかという気がします。特に僕が大人になってからは、強くそう感じているんです。それで楽しい作品を書くほうが僕には難しいし、無理に楽しくしても、どうにも嘘っぽく感じてしまうところがあるんです。
僕は27歳なので、選挙権を持ってから7年が経ちましたが、僕の支持する候補者はずっと落選し続けている。貧しい若者や、今ある文化を守ろうという公約を掲げている方が、何故か毎回のように落選する。本当に不思議です。まっとうな意見に、民衆のほうが耳を貸さなくなってきているのではないか。今回の作品について、盛んに「閉じている」という講評がなされましたが、それは時代の反映ですよ。知っているひとの知っている意見だけで、多くのひとは、閉じている気がして。
テロにしても、令和に入ってこの僅か3カ月の間に、いくらなんでも頻繁に起き過ぎています。登戸の事件もそうだし、年に1回起こるだけで、その事実を知っただけで精神がめちゃくちゃになるような事件が、この短期間に立て続けに起きて、全体的に心が疲弊してしまっている、という絶対的な感覚があって。
こんな社会状況なのに「令和の最初はこういう感じだったけど、この後数十年は特に何もありませんでした~、めでたしめでたし、ちゃんちゃん」というような未来には、まずならないと思っているんです。そんなに楽観的にはなれない。
平成の終わりだけで考えても、座間の事件があり、相模原の事件がありました。
その時にどうしても疑問に思うのは、メディアやSNSで盛大に犯人を叩いても仕方がないということで。特に犯人がすでに死んでしまっているケースで犯人を罵倒しようが、犯人の家族歴や隣人との関係を詳細に報道しようが、あんまり意味がなくて。
問題なのは、そういうことを起こすひとを、今の社会が恒常的に生み出してしまっているという紛れもない事実だと思いますし、その原因がどこにあるのかを緻密に議論しなければならないんですが、「一人で死ね」の是非とか、どうにも問題を矮小化して伝えてしまっています。そこがいちばん重要なわけじゃない。犯人をモンスターと平気で呼ぶようなコメンテーターがいてギョッとしました。宇宙人がいきなり攻めてきたんじゃないんです。私たちと同じ人間で、そこには必ず思考がある。相模原の犯人のドキュメンタリー番組をみればわかることです。それを簡単に排除して、怖いよねえ、で済ませようとしているひとたちのほうが、僕には何倍も怖いです。何も済んでない。押し入れにあらゆるものを放り込んで、「部屋を片付けた」と言い張ってる感じ。全く片付いてないのに。
そこに問いを容赦なく突きつけるのが、使命のひとつだと思っているんです。これがたとえあなたたちの知らない演劇だとしても、そんなことは関係なく、そうなんです。何で演劇だったら、人を楽しませないといけないんですかね。映画でも、笑いのないもの、楽しくないもの、怖いものは溢れているのに。SNSでもチラシでも、正直にどういう物語を上演するか、伝えてきたはずです。やかましいぐらいに。しんどい内容ですよ、って。それでも文句を言うひとはいる。僕はあらゆるところで説明責任を果たすしかないので、それで伝わらなければ、もうどうしようもないです。
乱暴に言うと、観客は大きくふたつのタイプに分かれます。
現実が辛いから、せめて劇場だけでも楽しい作品に触れたいという方。
そしてもうひとつは、現実がたとえ辛くても悲しくても、なぜそのようなことが起きるのか、その原因を理解したり考えたりしたい、そのきっかけとして作品を享受したい方。
もちろんこのふたつはグラデーションで、混ざり合っているのですが。
仮にそうだとして、決して前者のお客さんを否定するわけではないんです。僕も京アニの事件が起きた時には複数の仕事を進めていたけれど、どうしてもショックで一旦手が止まってしまい、体調を一時的に著しく崩してしまいました。
好きなミュージシャンの曲を聴くとか好きな本を開くとかして、気持ちを落ち着けないと、どうしようもない状態になりました。いつでも元気をくれる、楽しいものは、確かにあった方がいい。そのひとにとって、心の支えになるものがあった方がいいということは重々承知の上で、それでも、やっぱり、辛い現実を常に問うていく作品があっても、それはそれでいいんじゃないかと思うんですよ。
きっと少数派であり続けるでしょうが、今後もそれについて考えていくことになると思うんです。強制的に。僕にとって社会について考えることと、テロについて考えることというのは、今、ほとんどイコールなんです。
受賞した時のスピーチでも言ったんですが、僕が今どうしてもテロから目を離せないということが、演劇と直接関係あるかどうか分からないが、ただもうこのようにするしかないんだと。それについて書かざるを得ないんだと、言いました。
演劇的にどうあるべきかとか、流行りの演劇はどうであるかとは最早関係がなく、僕が今これを問う必要があるのではないかと信じることを、徹底的に追及して、表現として捻り出すしかないんじゃないかと思っていますし、それは今後の方針として、恐らく変わることはありません。
【キュイ プロフィール】
専属の俳優を持たない、プロデュース・ユニットとして活動中。戯曲は「震災、テロ、無差別殺人など、突発的な天災・人災を主なモチーフとすること」が特徴。『止まらない子供たちが轢かれてゆく』『不眠普及』でせんだい短編戯曲賞大賞を受賞。
今回のこの受賞インタビューを、たまたま僕のスケジュールの都合でコンクールの受賞発表から10日後※に受けているんですが、この10日間のうちに未曽有の出来事が起きまして、これを避けては今回の作品についてはもう、喋ることが出来ないだろうというのが率直な気持ちです。(※綾門さんには後日インタビューにご協力頂きました。)
その事件というのは、ご存知の方も多いと思いますが、京アニで起きた放火事件です。
まだ事件から一週間も経っていないくらいなので、連日の報道で死者も増えていきますし、まだ全然気持ちの整理がついていない状況です。深い悲しみの中にいます。
Twitterでもちらほら見かけたんですが、今回の『蹂躙を蹂躙』を観た方の中で、事件のニュースを観た瞬間に、作品のことを思い出した、という方がいらっしゃいました。実際、あまりにも連想しやすい作品だったと思っています。
他でもない作者の僕が、事件のことを知った瞬間に『蹂躙を蹂躙』のことを強く想起し、悲しみに暮れたくらいなので、それはたぶん、今回の座組のみなさんにも、劇場で作品を観た方にも、少なからず起きた現象なのではないかと推測しています。
今回、劇作家賞に選んでくださった審査員の方々にはすごく感謝の気持ちはありますし、劇場に足を運んで作品を観ていただいた、観客の方々にも感謝の気持ちはあるんですけど、気持ちは今、物凄く沈んでいます。
コンクール当日にこのインタビューを収録していたら、もしかしたら「やったー!」って言っていたかもしれないんですが、今ではどうにも無理な気持ちになってしまいました。喜びの気持ちが全くなくて、毎日、事件のことばかりを考えて、心の痛みが酷いです。
受賞インタビューなのに申し訳ないんですけど、それが今の率直な気持ちです。
・ありがとうございます。キュイという演劇プロデュースユニット、そして劇作家としての綾門さんの創作のテーマやコンセプトについて、あらためて教えてください。
キュイとしての活動としては9年目に差し掛かります。これまでにすべての作品でテロを扱ってきたわけではもちろんないんですが、それでも数作品、片手で余る数を上演してきたわけで、割と頻繁にテロをテーマに扱ってきていると言っていいと思います。
もちろん、直接的にテロを扱った作品を観ていて楽しいわけがないし、観客の方から「せっかく劇場に来たのになんで楽しい作品じゃないんだ!」的な文句をいただくことは実際、以前もあったんですよね。
特に今回、普段の公演に比べてキュイの作品を初めて観た方が多かったと思いますし、しかもコンクールのトップバッターだったので「……え?」という空気が流れました。出演者の方たちも、舞台上で少なからず感じたと言っていました。
あとはキュイっていう名前だけ知っていたり、綾門の名前だけは知っていたというような人たちが、実際に初めてキュイの作品を観てびっくりしちゃった、ということもよく起きます。思ってたのと違う、ってやつですね。こういうものだとは事前に想定しないから。
それについて一貫した主張として思うのは、今、日本の社会がいい方向に向かっているとはあまり捉えていないんですね。なんだったらだんだん邪悪な方向に向かっているんじゃないかという気がします。特に僕が大人になってからは、強くそう感じているんです。それで楽しい作品を書くほうが僕には難しいし、無理に楽しくしても、どうにも嘘っぽく感じてしまうところがあるんです。
僕は27歳なので、選挙権を持ってから7年が経ちましたが、僕の支持する候補者はずっと落選し続けている。貧しい若者や、今ある文化を守ろうという公約を掲げている方が、何故か毎回のように落選する。本当に不思議です。まっとうな意見に、民衆のほうが耳を貸さなくなってきているのではないか。今回の作品について、盛んに「閉じている」という講評がなされましたが、それは時代の反映ですよ。知っているひとの知っている意見だけで、多くのひとは、閉じている気がして。
テロにしても、令和に入ってこの僅か3カ月の間に、いくらなんでも頻繁に起き過ぎています。登戸の事件もそうだし、年に1回起こるだけで、その事実を知っただけで精神がめちゃくちゃになるような事件が、この短期間に立て続けに起きて、全体的に心が疲弊してしまっている、という絶対的な感覚があって。
こんな社会状況なのに「令和の最初はこういう感じだったけど、この後数十年は特に何もありませんでした~、めでたしめでたし、ちゃんちゃん」というような未来には、まずならないと思っているんです。そんなに楽観的にはなれない。
平成の終わりだけで考えても、座間の事件があり、相模原の事件がありました。
その時にどうしても疑問に思うのは、メディアやSNSで盛大に犯人を叩いても仕方がないということで。特に犯人がすでに死んでしまっているケースで犯人を罵倒しようが、犯人の家族歴や隣人との関係を詳細に報道しようが、あんまり意味がなくて。
問題なのは、そういうことを起こすひとを、今の社会が恒常的に生み出してしまっているという紛れもない事実だと思いますし、その原因がどこにあるのかを緻密に議論しなければならないんですが、「一人で死ね」の是非とか、どうにも問題を矮小化して伝えてしまっています。そこがいちばん重要なわけじゃない。犯人をモンスターと平気で呼ぶようなコメンテーターがいてギョッとしました。宇宙人がいきなり攻めてきたんじゃないんです。私たちと同じ人間で、そこには必ず思考がある。相模原の犯人のドキュメンタリー番組をみればわかることです。それを簡単に排除して、怖いよねえ、で済ませようとしているひとたちのほうが、僕には何倍も怖いです。何も済んでない。押し入れにあらゆるものを放り込んで、「部屋を片付けた」と言い張ってる感じ。全く片付いてないのに。
そこに問いを容赦なく突きつけるのが、使命のひとつだと思っているんです。これがたとえあなたたちの知らない演劇だとしても、そんなことは関係なく、そうなんです。何で演劇だったら、人を楽しませないといけないんですかね。映画でも、笑いのないもの、楽しくないもの、怖いものは溢れているのに。SNSでもチラシでも、正直にどういう物語を上演するか、伝えてきたはずです。やかましいぐらいに。しんどい内容ですよ、って。それでも文句を言うひとはいる。僕はあらゆるところで説明責任を果たすしかないので、それで伝わらなければ、もうどうしようもないです。
乱暴に言うと、観客は大きくふたつのタイプに分かれます。
現実が辛いから、せめて劇場だけでも楽しい作品に触れたいという方。
そしてもうひとつは、現実がたとえ辛くても悲しくても、なぜそのようなことが起きるのか、その原因を理解したり考えたりしたい、そのきっかけとして作品を享受したい方。
もちろんこのふたつはグラデーションで、混ざり合っているのですが。
仮にそうだとして、決して前者のお客さんを否定するわけではないんです。僕も京アニの事件が起きた時には複数の仕事を進めていたけれど、どうしてもショックで一旦手が止まってしまい、体調を一時的に著しく崩してしまいました。
好きなミュージシャンの曲を聴くとか好きな本を開くとかして、気持ちを落ち着けないと、どうしようもない状態になりました。いつでも元気をくれる、楽しいものは、確かにあった方がいい。そのひとにとって、心の支えになるものがあった方がいいということは重々承知の上で、それでも、やっぱり、辛い現実を常に問うていく作品があっても、それはそれでいいんじゃないかと思うんですよ。
きっと少数派であり続けるでしょうが、今後もそれについて考えていくことになると思うんです。強制的に。僕にとって社会について考えることと、テロについて考えることというのは、今、ほとんどイコールなんです。
受賞した時のスピーチでも言ったんですが、僕が今どうしてもテロから目を離せないということが、演劇と直接関係あるかどうか分からないが、ただもうこのようにするしかないんだと。それについて書かざるを得ないんだと、言いました。
演劇的にどうあるべきかとか、流行りの演劇はどうであるかとは最早関係がなく、僕が今これを問う必要があるのではないかと信じることを、徹底的に追及して、表現として捻り出すしかないんじゃないかと思っていますし、それは今後の方針として、恐らく変わることはありません。
【キュイ プロフィール】
専属の俳優を持たない、プロデュース・ユニットとして活動中。戯曲は「震災、テロ、無差別殺人など、突発的な天災・人災を主なモチーフとすること」が特徴。『止まらない子供たちが轢かれてゆく』『不眠普及』でせんだい短編戯曲賞大賞を受賞。
2019年09月16日
受賞者インタビュー(2) ルサンチカ 河井朗さん(演出家賞)
・今回のコンクール全体についての印象はいかがでしょうか。
異なったジャンルの作品がちゃんと集まったのがすごくいいことだなと思いました。
専門審査員の作品との向き合い方もとてもフラットで、「作品と社会」「劇場と作品」「観客と審査員」という風にそれぞれの関係にしっかりと眼差しが向けられていて、しっかりとした判断基準があったのがとてもよかったです。
・講評会では専門審査員の方々からのさまざまな講評や意見、感想がありましたが、それを受けて今思われることはありますか。
言われたことはすべて納得できるものでしたし、だからといって作品の性質上その変化をもたらす必要もないなと思えることもありました。ただコンクールというシステム上、上演デザインの中で出来ないことや制約も多々あったので、そういう一面についてはどう考えていけばいいかいま悩んでいます。
ただ本作がしっかり賛否の意見があったのが良かったなと思っています。「これは演劇なのか?」ということと、「観客とどうやって対話するか」ということをずっと考えていました。作品の中で語られる言葉が「理想の死に方」についてのインタビューから採られたものだというのもそのためです。
その過程を演劇的なアプローチに入れ込んで作品にしてみたというだけなので、そういった意味で色々な意見があったのがすごく嬉しいです。
・ありがとうございます。ルサンチカさんの今後の活動予定や、展望について教えてください。
この「理想の死に方」というシリーズで京都府立文化芸術会館と提携して2019年から2021年までの3年間、制作していきます。2年目となる来年は「仕事」についてインタビューして作品を作ろうと思っています。
社会的に、人は働くことで自分の居場所を作ることができるということがあると思うんです。「働く」ということから自分たちは何者かを問えるような作品ができたらいいなと思っています。
そして三年目にはシリアのグータであった出来事を題材に作品を作ろうと思っています。
内戦中のシリア、グータから「#IAmStillAlive(私はまだ生きている)」というハッシュタグをつけて、毎日地下室や避難所からTwitterへ動画や写真を投稿していた一般市民の男性がいたんです。
去年その彼は戦闘に巻き込まれて亡くなってしまったんですが、亡くなってしまったことが分かってからTwitter上では「#NoLongerAlive(彼はもう生きていない)」というハッシュタグが追加されたんです。
その「今までここで生きていた彼が、今日はもういなくなった。」ということから、「私たちは今日をどうやって生きていくのか」ということについて考える作品を作りたいなと思っています。
最終的には「理想の死に方」と「仕事」と「私たちは今日をどうやって生きるのか」というこの3つの作品の上演とインタビューの展示を両方できたらいいなと思っています。
―人が日常生活の中であらたまって生きることや死ぬことについて考えるというのは、西洋だったら教会、日本だったらお寺といった宗教的な場所が担ってきた役割なのかなと思うのですが、ルサンチカさんの作品はそういった人の生死に対する根源的な問いについて真正面から取り組んでいる印象を受けました。
そうですね、ただ考える機会を作るだけの上演なんです、本当に。
・ありがとうございます。今後せんがわ劇場でチャレンジしてみたいことはありますか?
京都府立文化芸術会館もせんがわ劇場と同じく公共の劇場なんですが、そういった公共の劇場に公演がない時どうやったら人は足を踏み入れてくれるんだろうと。
公共の劇場というのは、劇場自身で観客を創客しなければいけないと思うんです。そう考えたときに、公演がなくても人が来れるような場所ってどこなんだろうって考えてみると図書館みたいな場所なのかなと思うんですね。
そういった場所がどうにかしてできないのだろうか。
人が劇場へ日常的に足を運べるようになるために、何か恒久的に続いているサービスやイベントと劇場を結びつけることが出来ないかということを考えていきたいと思っています。
・ありがとうございます。最後に何か一言ありますか?
今回の作中で使用したインタビューもすべてルサンチカのサイトに載っているので、もし気になる方はぜひ見てみてください。
https://www.ressenchka.com/
【ルサンチカ プロフィール】
河井朗が主宰、演出を行う演劇カンパニー。物事の色々をひとまず両手ですくい取ってみて、その時にこぼれ落ちた側に焦点を当てて作品をつくる。主に既成戯曲、小説、インタビューなどを用いて舞台作品を制作する。
異なったジャンルの作品がちゃんと集まったのがすごくいいことだなと思いました。
専門審査員の作品との向き合い方もとてもフラットで、「作品と社会」「劇場と作品」「観客と審査員」という風にそれぞれの関係にしっかりと眼差しが向けられていて、しっかりとした判断基準があったのがとてもよかったです。
・講評会では専門審査員の方々からのさまざまな講評や意見、感想がありましたが、それを受けて今思われることはありますか。
言われたことはすべて納得できるものでしたし、だからといって作品の性質上その変化をもたらす必要もないなと思えることもありました。ただコンクールというシステム上、上演デザインの中で出来ないことや制約も多々あったので、そういう一面についてはどう考えていけばいいかいま悩んでいます。
ただ本作がしっかり賛否の意見があったのが良かったなと思っています。「これは演劇なのか?」ということと、「観客とどうやって対話するか」ということをずっと考えていました。作品の中で語られる言葉が「理想の死に方」についてのインタビューから採られたものだというのもそのためです。
その過程を演劇的なアプローチに入れ込んで作品にしてみたというだけなので、そういった意味で色々な意見があったのがすごく嬉しいです。
・ありがとうございます。ルサンチカさんの今後の活動予定や、展望について教えてください。
この「理想の死に方」というシリーズで京都府立文化芸術会館と提携して2019年から2021年までの3年間、制作していきます。2年目となる来年は「仕事」についてインタビューして作品を作ろうと思っています。
社会的に、人は働くことで自分の居場所を作ることができるということがあると思うんです。「働く」ということから自分たちは何者かを問えるような作品ができたらいいなと思っています。
そして三年目にはシリアのグータであった出来事を題材に作品を作ろうと思っています。
内戦中のシリア、グータから「#IAmStillAlive(私はまだ生きている)」というハッシュタグをつけて、毎日地下室や避難所からTwitterへ動画や写真を投稿していた一般市民の男性がいたんです。
去年その彼は戦闘に巻き込まれて亡くなってしまったんですが、亡くなってしまったことが分かってからTwitter上では「#NoLongerAlive(彼はもう生きていない)」というハッシュタグが追加されたんです。
その「今までここで生きていた彼が、今日はもういなくなった。」ということから、「私たちは今日をどうやって生きていくのか」ということについて考える作品を作りたいなと思っています。
最終的には「理想の死に方」と「仕事」と「私たちは今日をどうやって生きるのか」というこの3つの作品の上演とインタビューの展示を両方できたらいいなと思っています。
―人が日常生活の中であらたまって生きることや死ぬことについて考えるというのは、西洋だったら教会、日本だったらお寺といった宗教的な場所が担ってきた役割なのかなと思うのですが、ルサンチカさんの作品はそういった人の生死に対する根源的な問いについて真正面から取り組んでいる印象を受けました。
そうですね、ただ考える機会を作るだけの上演なんです、本当に。
・ありがとうございます。今後せんがわ劇場でチャレンジしてみたいことはありますか?
京都府立文化芸術会館もせんがわ劇場と同じく公共の劇場なんですが、そういった公共の劇場に公演がない時どうやったら人は足を踏み入れてくれるんだろうと。
公共の劇場というのは、劇場自身で観客を創客しなければいけないと思うんです。そう考えたときに、公演がなくても人が来れるような場所ってどこなんだろうって考えてみると図書館みたいな場所なのかなと思うんですね。
そういった場所がどうにかしてできないのだろうか。
人が劇場へ日常的に足を運べるようになるために、何か恒久的に続いているサービスやイベントと劇場を結びつけることが出来ないかということを考えていきたいと思っています。
・ありがとうございます。最後に何か一言ありますか?
今回の作中で使用したインタビューもすべてルサンチカのサイトに載っているので、もし気になる方はぜひ見てみてください。
https://www.ressenchka.com/
【ルサンチカ プロフィール】
河井朗が主宰、演出を行う演劇カンパニー。物事の色々をひとまず両手ですくい取ってみて、その時にこぼれ落ちた側に焦点を当てて作品をつくる。主に既成戯曲、小説、インタビューなどを用いて舞台作品を制作する。
2019年09月15日
受賞者インタビュー(1) ルサンチカ 河井朗さん(演出家賞)
・今回演出家賞を受賞されましたが、まずは率直な受賞の感想をお聞かせください。
そうですね、嬉しくも悔しいという気持ちがあります、やるからにはグランプリが獲りたいなとは思っていたんですけど。
それでもこの作品が審査員の皆さんやいろんなお客様に認められたのは、すごく光栄に思います。
・今回上演された『PIPE DREAM』という作品はもともと京都府立芸術文化センターで2019年~2021年まで3年間にわたる支援プログラムの中で創作された作品だということですが、そもそもルサンチカさんの普段の活動のテーマや創作時のコンセプトを教えてください。
僕は劇団じゃなくてユニットという扱いなので、基本的には僕個人で制作をしています。
作品のテーマ性としては主に「人がこれからをどうやって生きていくか」ということを考えていて、僕が抱えている問題を、そのとき集まったクリエイションメンバーとともにどう作品にしていくかということを考えながら活動しています。
・今回上演した『PIPE DREAM』という作品について、特に強く抱いていたテーマやコンセプトについて教えてください。
「人の話をどうやって聞けるだろうか」ということをずっと考えていました。
それと植物状態になった私の祖母のことを考えていました。
相模原障害者施設殺傷事件の加害者の男が「意思の疎通をとれない人間は殺してもいい」ということを言っていて、
その言葉を聞いた時に、だとすると僕たちは赤ちゃんを殺さなければならないし、犬も殺さなければならないし、植物状態の人のことも殺さなくちゃいけないなということを考えてしまって。
そうすると私の祖母は死んでしまうな、とも思ってしまったんです。
それで「意思の疎通」というテーマが一つ大きくありました。
もう一つは、スウェーデンで流行っている「生存放棄症候群※」という難病のことでした。
その病気は植物状態になったわけではなく、ただただ眠りから覚めないという病気なんです。
さきほどの「意思の疎通をとれない人間は殺してもいい」という前提からすると、その人たちも殺されてしまうな、と思って。
でも僕は、その人たちは今を生きることを保留にしたんだなと思ったんです。
(※20年前からスウェーデンでのみ発生している難病。亡命を望む難民のこども達に多く見られ、強い精神的ストレスが原因と考えられている。)
今の時勢は生きることに関して様々な決断を自己責任というもので求められる時代だなと思うんですが、
それを一旦自己責任で解決できないものは保留にしてもいいのではないか、という思いがありました。
なので「意思の疎通」と、「どうやって今の生き方を保留にすることができるか」ということを考えるために今回の作品を作りました。
・今回の「PIPE DREAM」という作品では、舞台上で人が宙づりにされているというのが多くの観客にとって特に印象的だったのではないかと思います。また審査会でも杉山至さんが言及されていましたが「人の呼吸を思わせる照明の明滅」というのも今回観る者に強い印象を与えるものでした。今回演出をされた中で、そうした視覚的に印象的な手法を選んでいったのにはどのような狙いがあったのでしょうか。
たとえば人は植物状態になって寝たきりで長い間動かないと、関節が動かない拘縮状態になってしまうんですね。
そうして地に足をついて動くことができない、関節が固くなる、動けないという現象をどうやったら舞台上で意図的に作れるかなと考えたときに、一度空を飛ばす(宙に吊り上げる)べきかなと考えました。
人はやはり地に足を付かない限り、自立運動は出来ないのだと今回の作品で改めて自覚しました。
そういった意味で、ハーネスを着て空に飛ばすという方法を選びました。
照明に関しては、京都府立文化芸術会館の照明スタッフの方と話した時に、ずっと動き続けるチェイスの照明がとても自然な流れでいいのではないかというプランがあったので、以来ずっとそのデザインで上演しています。
意識的に照明だけを観てほしいというわけではもちろんなくて、舞台上で自然な流れでなにが起こるかわからないという状態を作り出せたらいいなと思っています。
ただ上演中に起きる照明の動きは、実はすべて偶然だったりもするんですけど(笑)。
・ありがとうございます。先程お話のなかにも出ましたが、元々この作品は京都で製作され、今年の3月には神奈川かもめ「短編演劇」フェスティバルで、そして今回のコンクールと上演を重ねられてきましたが、今回の上演を終えてみての手ごたえや印象はいかがでしょうか。
今回この作品は5回目の公演で、初演は僕一人だけで舞台に立って、そこからどんどんいろんな人とクリエイションを重ねてきました。
せんがわでの上演は「どうやって人は眠りにつくのか」「死んでいくのか」ということについて考える旅みたいなものだなと思えました。もちろんこれからもずっと続いては行くんですけど、今回で一区切りをつけられたかなと思いました。
【ルサンチカ プロフィール】
河井朗が主宰、演出を行う演劇カンパニー。物事の色々をひとまず両手ですくい取ってみて、その時にこぼれ落ちた側に焦点を当てて作品をつくる。主に既成戯曲、小説、インタビューなどを用いて舞台作品を制作する。
そうですね、嬉しくも悔しいという気持ちがあります、やるからにはグランプリが獲りたいなとは思っていたんですけど。
それでもこの作品が審査員の皆さんやいろんなお客様に認められたのは、すごく光栄に思います。
・今回上演された『PIPE DREAM』という作品はもともと京都府立芸術文化センターで2019年~2021年まで3年間にわたる支援プログラムの中で創作された作品だということですが、そもそもルサンチカさんの普段の活動のテーマや創作時のコンセプトを教えてください。
僕は劇団じゃなくてユニットという扱いなので、基本的には僕個人で制作をしています。
作品のテーマ性としては主に「人がこれからをどうやって生きていくか」ということを考えていて、僕が抱えている問題を、そのとき集まったクリエイションメンバーとともにどう作品にしていくかということを考えながら活動しています。
・今回上演した『PIPE DREAM』という作品について、特に強く抱いていたテーマやコンセプトについて教えてください。
「人の話をどうやって聞けるだろうか」ということをずっと考えていました。
それと植物状態になった私の祖母のことを考えていました。
相模原障害者施設殺傷事件の加害者の男が「意思の疎通をとれない人間は殺してもいい」ということを言っていて、
その言葉を聞いた時に、だとすると僕たちは赤ちゃんを殺さなければならないし、犬も殺さなければならないし、植物状態の人のことも殺さなくちゃいけないなということを考えてしまって。
そうすると私の祖母は死んでしまうな、とも思ってしまったんです。
それで「意思の疎通」というテーマが一つ大きくありました。
もう一つは、スウェーデンで流行っている「生存放棄症候群※」という難病のことでした。
その病気は植物状態になったわけではなく、ただただ眠りから覚めないという病気なんです。
さきほどの「意思の疎通をとれない人間は殺してもいい」という前提からすると、その人たちも殺されてしまうな、と思って。
でも僕は、その人たちは今を生きることを保留にしたんだなと思ったんです。
(※20年前からスウェーデンでのみ発生している難病。亡命を望む難民のこども達に多く見られ、強い精神的ストレスが原因と考えられている。)
今の時勢は生きることに関して様々な決断を自己責任というもので求められる時代だなと思うんですが、
それを一旦自己責任で解決できないものは保留にしてもいいのではないか、という思いがありました。
なので「意思の疎通」と、「どうやって今の生き方を保留にすることができるか」ということを考えるために今回の作品を作りました。
・今回の「PIPE DREAM」という作品では、舞台上で人が宙づりにされているというのが多くの観客にとって特に印象的だったのではないかと思います。また審査会でも杉山至さんが言及されていましたが「人の呼吸を思わせる照明の明滅」というのも今回観る者に強い印象を与えるものでした。今回演出をされた中で、そうした視覚的に印象的な手法を選んでいったのにはどのような狙いがあったのでしょうか。
たとえば人は植物状態になって寝たきりで長い間動かないと、関節が動かない拘縮状態になってしまうんですね。
そうして地に足をついて動くことができない、関節が固くなる、動けないという現象をどうやったら舞台上で意図的に作れるかなと考えたときに、一度空を飛ばす(宙に吊り上げる)べきかなと考えました。
人はやはり地に足を付かない限り、自立運動は出来ないのだと今回の作品で改めて自覚しました。
そういった意味で、ハーネスを着て空に飛ばすという方法を選びました。
照明に関しては、京都府立文化芸術会館の照明スタッフの方と話した時に、ずっと動き続けるチェイスの照明がとても自然な流れでいいのではないかというプランがあったので、以来ずっとそのデザインで上演しています。
意識的に照明だけを観てほしいというわけではもちろんなくて、舞台上で自然な流れでなにが起こるかわからないという状態を作り出せたらいいなと思っています。
ただ上演中に起きる照明の動きは、実はすべて偶然だったりもするんですけど(笑)。
・ありがとうございます。先程お話のなかにも出ましたが、元々この作品は京都で製作され、今年の3月には神奈川かもめ「短編演劇」フェスティバルで、そして今回のコンクールと上演を重ねられてきましたが、今回の上演を終えてみての手ごたえや印象はいかがでしょうか。
今回この作品は5回目の公演で、初演は僕一人だけで舞台に立って、そこからどんどんいろんな人とクリエイションを重ねてきました。
せんがわでの上演は「どうやって人は眠りにつくのか」「死んでいくのか」ということについて考える旅みたいなものだなと思えました。もちろんこれからもずっと続いては行くんですけど、今回で一区切りをつけられたかなと思いました。
【ルサンチカ プロフィール】
河井朗が主宰、演出を行う演劇カンパニー。物事の色々をひとまず両手ですくい取ってみて、その時にこぼれ落ちた側に焦点を当てて作品をつくる。主に既成戯曲、小説、インタビューなどを用いて舞台作品を制作する。
2019年03月28日
【サンデー・マティネ・コンサートPlus vol.16】
【サンデー・マティネ・コンサートPlus vol.16】
【出演】
カルテット・プラチナム
沼田園子(ヴァイオリン)
野口千代光(ヴァイオリン)
大野かおる(ヴィオラ)
菊地知也(チェロ)

10周年を迎えた平成30年度せんがわ劇場の最後のコンサートは、
弦楽器の名手4人による弦楽四重奏カルテット・プラチナムの演奏で締めくくりました。
アンケートでは「素晴らしい」が沢山。
本当に贅沢な1時間で、客席内はどこか音楽の世界に飛んでいったかのような空間になっていました!
カルテット・プラチナムの皆さま、素晴らしい演奏をありがとうございました。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
カルテット・プラチナム
沼田園子(ヴァイオリン)
野口千代光(ヴァイオリン)
大野かおる(ヴィオラ)
菊地知也(チェロ)

10周年を迎えた平成30年度せんがわ劇場の最後のコンサートは、
弦楽器の名手4人による弦楽四重奏カルテット・プラチナムの演奏で締めくくりました。
アンケートでは「素晴らしい」が沢山。
本当に贅沢な1時間で、客席内はどこか音楽の世界に飛んでいったかのような空間になっていました!
カルテット・プラチナムの皆さま、素晴らしい演奏をありがとうございました。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
2019年03月20日
【サンデー・マティネ・コンサートvol.211】<ピアノトリオコンサート>
<ピアノトリオコンサート>
出演:吉村美智子( ヴァイオリン)
内山剛博( チェロ)
齊野晴香( ピアノ)
今シーズン最後のサンマチは、ピアノトリオ。
弦楽器だけの組合せではなく、メロディも伴奏も、何ならリズムも担当できるピアノが入ることで、
ヴァイオリンもチェロも、よりソリスト色が強くなるというか、個性が発揮される感じなのでしょうか。
このピアノトリオを、桐朋学園大学の1年生と3年生という、フレッジュかつ実力派の皆さんにご出演いただき、お届けしました!
特に2曲目のドビュッシーは全楽章、20分近くの演奏で、しっかりご堪能していただけたのではないかと思います。
恒例の「せんがわトーク」では、それぞれのランチタイムをご紹介。
斎野さんはお弁当中心なので・・・と特にお店は上がりませんでしたが(これも素晴らしいですね!)、
吉村さんは、見晴らしがよいsengawa Poireをあげてくださいました。
特筆は内山さん。このコーナーの存在を知っていたので準備してきました!と、
串カツ居酒屋 民屋、武蔵野うどん和酒 たか乃(残念ながら3月で閉店)、
更にお好きなラーメン屋さんで、めでたや・しば田、と、4軒も紹介の大サービス?でした。
コンサートの最後では、8年にわたり、サンマチをはじめとした音楽事業を長年担当し、
今年度で劇場を離れるスタッフMが、初めてステージでご挨拶しました。
来年度から、せんがわ劇場は、調布市直営から、調布市文化・コミュニティ振興財団の運営となりますが、
サンデー・マティネ・コンサートは引き続き開催します。
これからも、皆さまのお越しをお待ちしております!
終演後の写真は左から、斎野晴香さん、吉村美智子さん、内山剛博さんです。
堂々とした演奏から一変、2枚目のピース写真をみると、やはり若者!とほほえましくなるスタッフHでした☺️


終演後コメントは、斎野晴香さん、吉村美智子さん、内山剛博さんの順番です。どうぞご覧ください!
公演詳細はこちらからどうぞ→ここをクリック
出演:吉村美智子( ヴァイオリン)
内山剛博( チェロ)
齊野晴香( ピアノ)
今シーズン最後のサンマチは、ピアノトリオ。
弦楽器だけの組合せではなく、メロディも伴奏も、何ならリズムも担当できるピアノが入ることで、
ヴァイオリンもチェロも、よりソリスト色が強くなるというか、個性が発揮される感じなのでしょうか。
このピアノトリオを、桐朋学園大学の1年生と3年生という、フレッジュかつ実力派の皆さんにご出演いただき、お届けしました!
特に2曲目のドビュッシーは全楽章、20分近くの演奏で、しっかりご堪能していただけたのではないかと思います。
恒例の「せんがわトーク」では、それぞれのランチタイムをご紹介。
斎野さんはお弁当中心なので・・・と特にお店は上がりませんでしたが(これも素晴らしいですね!)、
吉村さんは、見晴らしがよいsengawa Poireをあげてくださいました。
特筆は内山さん。このコーナーの存在を知っていたので準備してきました!と、
串カツ居酒屋 民屋、武蔵野うどん和酒 たか乃(残念ながら3月で閉店)、
更にお好きなラーメン屋さんで、めでたや・しば田、と、4軒も紹介の大サービス?でした。
コンサートの最後では、8年にわたり、サンマチをはじめとした音楽事業を長年担当し、
今年度で劇場を離れるスタッフMが、初めてステージでご挨拶しました。
来年度から、せんがわ劇場は、調布市直営から、調布市文化・コミュニティ振興財団の運営となりますが、
サンデー・マティネ・コンサートは引き続き開催します。
これからも、皆さまのお越しをお待ちしております!
終演後の写真は左から、斎野晴香さん、吉村美智子さん、内山剛博さんです。
堂々とした演奏から一変、2枚目のピース写真をみると、やはり若者!とほほえましくなるスタッフHでした☺️


終演後コメントは、斎野晴香さん、吉村美智子さん、内山剛博さんの順番です。どうぞご覧ください!
公演詳細はこちらからどうぞ→ここをクリック
2019年03月05日
サンデー・マティネ・コンサートvol.210 東京の民謡を知る
<東京の民謡を知る>
【出演】
村松 喜久則(唄・構成・ご案内)
京極 加津恵(唄・ご案内)
月岡 雪子(笛・三味線)
モード・アルシャンボー(鳴り物・踊り)

民謡。
日本全国に民謡がどのくらいあるかご存知ですか?
何と58,000曲!!(昭和62年調査)
しかも、何となく、地方の方がたくさんの民謡がある気がしていましたが、
実は東京は「民謡の宝庫」ともいわれるほど、多くの民謡が残されている地域なんだそうです!
今回は、たくさんあるにもかかわらず、
意外と知らない民謡の数々を、わかりやすく楽しい解説と共に、聴くことができました。
考えてみると、江戸は、当時世界でも有数の人口を抱える大都市で、
地方との行き来も既に盛んにおこなわれていましたから、
各地の民謡が江戸に伝わるのは、当然なのかもしれません。
(江戸を経由して、また他の地方に伝わって行ったりもしたようです)
こうして広まるうちに、少しずつお土地柄にあわせて歌詞が変わり、テンポやメロディが変わっていく。
江戸の民謡は、江戸っ子気質を反映してか「節の上がり下がりが激しく、旋律が直線的で、歯切れがよい」んですって。なるほど!
民謡は、誰が作ったのでもなく、日々の労働や暮らしの中から生まれ、
文字や楽譜ではなく口から耳へ伝えられてきたもの。
田畑を耕す歌、舟をこぐ歌、遊びに行こうとする若者の気持ちをうたった歌など、
ごく自然に口ずさみながら生活していたのかもしれませんね。
冷たい雨の中ご来場くださったお客さまも、大満足のコンサートでした!
終演後、皆さんからコメントをいただきました。
京極 加津恵さん、モード・アルシャンボーさん、月岡 雪子さん、村松 喜久則さんの順です。
ぜひご覧ください!
※モード・アルシャンボーさんはカナダ人で、外国人として初めて、日本(一社)民謡プロ協会に入会して活躍中の方です。
※村松さんのコメント中にサイレンが入っています。お聞き苦しい点、ご容赦ください。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
村松 喜久則(唄・構成・ご案内)
京極 加津恵(唄・ご案内)
月岡 雪子(笛・三味線)
モード・アルシャンボー(鳴り物・踊り)
民謡。
日本全国に民謡がどのくらいあるかご存知ですか?
何と58,000曲!!(昭和62年調査)
しかも、何となく、地方の方がたくさんの民謡がある気がしていましたが、
実は東京は「民謡の宝庫」ともいわれるほど、多くの民謡が残されている地域なんだそうです!
今回は、たくさんあるにもかかわらず、
意外と知らない民謡の数々を、わかりやすく楽しい解説と共に、聴くことができました。
考えてみると、江戸は、当時世界でも有数の人口を抱える大都市で、
地方との行き来も既に盛んにおこなわれていましたから、
各地の民謡が江戸に伝わるのは、当然なのかもしれません。
(江戸を経由して、また他の地方に伝わって行ったりもしたようです)
こうして広まるうちに、少しずつお土地柄にあわせて歌詞が変わり、テンポやメロディが変わっていく。
江戸の民謡は、江戸っ子気質を反映してか「節の上がり下がりが激しく、旋律が直線的で、歯切れがよい」んですって。なるほど!
民謡は、誰が作ったのでもなく、日々の労働や暮らしの中から生まれ、
文字や楽譜ではなく口から耳へ伝えられてきたもの。
田畑を耕す歌、舟をこぐ歌、遊びに行こうとする若者の気持ちをうたった歌など、
ごく自然に口ずさみながら生活していたのかもしれませんね。
冷たい雨の中ご来場くださったお客さまも、大満足のコンサートでした!
終演後、皆さんからコメントをいただきました。
京極 加津恵さん、モード・アルシャンボーさん、月岡 雪子さん、村松 喜久則さんの順です。
ぜひご覧ください!
※モード・アルシャンボーさんはカナダ人で、外国人として初めて、日本(一社)民謡プロ協会に入会して活躍中の方です。
※村松さんのコメント中にサイレンが入っています。お聞き苦しい点、ご容赦ください。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
2019年02月11日
サンデー・マチネ・コンサートvol209 世界の楽器シリーズ<フィンランドの楽器・カンテレ>
~世界の楽器シリーズ~
<フィンランドの楽器・カンテレ>
【 出演】
はざた雅子(カンテレ)

カンテレ。関西テレビの略ではありません。楽器の名前です。
しかも、イントネーションは「カ↓ンテレ」で、「カ」が高いのです。関西テレビのカンテレとは逆です。
ふざけたような書き出しになってしまいましたが、そのくらい、日本ではなじみのない楽器ではないでしょうか。
フィンランドの民族楽器です。
写真をご覧いただくとわかりますが、木製の胴体にスチール絃を張っています。
小さなハープを横に倒した感じ・・・?
でもギターのように共鳴させる胴体を持っているところが違いますね。




左側の、蝶番の付いている木の部分はミュートです。
残響音が非常に長い楽器なので、これで音を止めます。
その上についているレバーは、半音をだすためのもの。
演奏の際は、忙しくあれこれ操作していらっしゃいました。
もともとは40cmほどの、木をくりぬいたものに弦を5本張った、とてもシンプルな楽器だったのが、
時代を追って絃の数が増えていき、今の形に進化してきたそうです。
(写真を撮り忘れました・・・すみません)
後でお話を伺ったところ、フィンランドでも、伝統楽器として大切にはされているものの演奏家は多くなく、
近年は(5弦のシンプルなものを)小学校で体験する時間が設けられるようになっているそうで・・・
日本における和楽器の状況とも似ている、と感じました。
日本ではもちろん手に入れることはできず、フィンランドに注文して輸入。
30万円くらいの楽器が輸送料でさらに2~3倍、と、大きなカンテレはさすがに大変ですが、
5弦のものは、最近ネットの個人輸入で2~3万で手に入るようになり、趣味で始める方もいるとか!
会場の9割以上、司会の合田先生すら「はじめて見た」楽器とあって、
終演後には、お客さまがステージにどっと集まって楽器の見学、撮影大会になりました。
でもその中でお一人,
「せんがわ劇場でカンテレが聴けるなんてとてもうれしいです。楽しみにしていました!」とおっしゃるお客さまが。
コンサートの前後で「はじめて」「知らない」を連発してしまいましたけど、
こうしたファンの方もちゃんといらっしゃるし、とても喜んでくださって、よかったなあと思ったのでした。
終演後のインタビューです。
「今日いらしたお客さまは、カンテレって、静かでおとなしい感じの楽器と思われたかもしれませんが、
もっといろんな曲や演奏法もあって、盛り上がるものもあるんですよ。またぜひどこかで聴いてください」
ともおっしゃっていました。
ニュースにもなる寒さの中、たくさんのお客さまにご来場いただきました。本当にありがとうございました!
<フィンランドの楽器・カンテレ>
【 出演】
はざた雅子(カンテレ)

カンテレ。関西テレビの略ではありません。楽器の名前です。
しかも、イントネーションは「カ↓ンテレ」で、「カ」が高いのです。関西テレビのカンテレとは逆です。
ふざけたような書き出しになってしまいましたが、そのくらい、日本ではなじみのない楽器ではないでしょうか。
フィンランドの民族楽器です。
写真をご覧いただくとわかりますが、木製の胴体にスチール絃を張っています。
小さなハープを横に倒した感じ・・・?
でもギターのように共鳴させる胴体を持っているところが違いますね。




左側の、蝶番の付いている木の部分はミュートです。
残響音が非常に長い楽器なので、これで音を止めます。
その上についているレバーは、半音をだすためのもの。
演奏の際は、忙しくあれこれ操作していらっしゃいました。
もともとは40cmほどの、木をくりぬいたものに弦を5本張った、とてもシンプルな楽器だったのが、
時代を追って絃の数が増えていき、今の形に進化してきたそうです。
(写真を撮り忘れました・・・すみません)
後でお話を伺ったところ、フィンランドでも、伝統楽器として大切にはされているものの演奏家は多くなく、
近年は(5弦のシンプルなものを)小学校で体験する時間が設けられるようになっているそうで・・・
日本における和楽器の状況とも似ている、と感じました。
日本ではもちろん手に入れることはできず、フィンランドに注文して輸入。
30万円くらいの楽器が輸送料でさらに2~3倍、と、大きなカンテレはさすがに大変ですが、
5弦のものは、最近ネットの個人輸入で2~3万で手に入るようになり、趣味で始める方もいるとか!
会場の9割以上、司会の合田先生すら「はじめて見た」楽器とあって、
終演後には、お客さまがステージにどっと集まって楽器の見学、撮影大会になりました。
でもその中でお一人,
「せんがわ劇場でカンテレが聴けるなんてとてもうれしいです。楽しみにしていました!」とおっしゃるお客さまが。
コンサートの前後で「はじめて」「知らない」を連発してしまいましたけど、
こうしたファンの方もちゃんといらっしゃるし、とても喜んでくださって、よかったなあと思ったのでした。
終演後のインタビューです。
「今日いらしたお客さまは、カンテレって、静かでおとなしい感じの楽器と思われたかもしれませんが、
もっといろんな曲や演奏法もあって、盛り上がるものもあるんですよ。またぜひどこかで聴いてください」
ともおっしゃっていました。
ニュースにもなる寒さの中、たくさんのお客さまにご来場いただきました。本当にありがとうございました!
2019年01月13日
サンデー・マティネ・コンサートvol.208
<瀧廉太郎へのオマージュ>
【出演】
松井康司(お話・バリトン)
紀野洋孝(テノール)
藤原伊央里(ピアノ)
桐朋学園芸術短大声楽アンサンブル

新年最初のサンマチは、日本が誇る作曲家、瀧廉太郎を取り上げました。
寒い中、たくさんのお客さまにお越しいただき、ありがとうございました!
明治の時代、西洋の音楽を真摯に学び、それを自身の作曲で活かす試みをしつつ、
子どもたちが楽しく歌える歌を作り、あっという間にこの世を去ってしまった瀧廉太郎。
松井先生からはたくさんのエピソードが語られ、止まらないほどでした。
たとえば「花」が、実は四季折々の組曲になっていたこと、皆さんご存知でしたか?
組曲「四季」の春が「花」で、その後「納涼」「月」「雪」と続くのです。
「月」や「雪」は、教会の聖歌のような雰囲気で、
瀧廉太郎という人は、こんな曲も作っていたのか!と、その幅広さにびっくりしました。
組曲としてはめったに演奏される機会がなく、
今日初めてお聴きになった方も多かったのではないでしょうか。
それにしても、あれほど輝かしい才能を持ち、将来を嘱望されていた瀧廉太郎が、
23歳という若さで病に倒れ、死の間際に創った遺作「憾(うらみ)」は、
彼の無念や怒り、音楽への情熱、あらゆる想いがあふれるような曲です。
タイトルを見るだけでも心が痛みます……。

ピアノ曲、ソロ、合唱など、贅沢にいろんな編成でお楽しみいただきました。
終演後のインタビューは、松井康司先生(お話・バリトン)、紀野洋孝さん(テノール)、藤原伊央里さん(ピアノ)にお願いしました。
ぜひご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
松井康司(お話・バリトン)
紀野洋孝(テノール)
藤原伊央里(ピアノ)
桐朋学園芸術短大声楽アンサンブル

新年最初のサンマチは、日本が誇る作曲家、瀧廉太郎を取り上げました。
寒い中、たくさんのお客さまにお越しいただき、ありがとうございました!
明治の時代、西洋の音楽を真摯に学び、それを自身の作曲で活かす試みをしつつ、
子どもたちが楽しく歌える歌を作り、あっという間にこの世を去ってしまった瀧廉太郎。
松井先生からはたくさんのエピソードが語られ、止まらないほどでした。
たとえば「花」が、実は四季折々の組曲になっていたこと、皆さんご存知でしたか?
組曲「四季」の春が「花」で、その後「納涼」「月」「雪」と続くのです。
「月」や「雪」は、教会の聖歌のような雰囲気で、
瀧廉太郎という人は、こんな曲も作っていたのか!と、その幅広さにびっくりしました。
組曲としてはめったに演奏される機会がなく、
今日初めてお聴きになった方も多かったのではないでしょうか。
それにしても、あれほど輝かしい才能を持ち、将来を嘱望されていた瀧廉太郎が、
23歳という若さで病に倒れ、死の間際に創った遺作「憾(うらみ)」は、
彼の無念や怒り、音楽への情熱、あらゆる想いがあふれるような曲です。
タイトルを見るだけでも心が痛みます……。

ピアノ曲、ソロ、合唱など、贅沢にいろんな編成でお楽しみいただきました。
終演後のインタビューは、松井康司先生(お話・バリトン)、紀野洋孝さん(テノール)、藤原伊央里さん(ピアノ)にお願いしました。
ぜひご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
2018年12月27日
【サンデー・マティネ・コンサートvol.207】
<ヴィブラフォン&ギターデュオ クリスマスコンサート>
【出演】
Megterlink(服部 恵(ヴィブラフォン)
伊藤 芳輝(ギター)

今年のクリスマスコンサートは、ヴィブラフォンとギターのデュオ、Megterlink(メーテルリンク)のお二人でした。
超絶技巧!連発のすばらしい演奏とうらはら?に、伊藤さんのつぶやくようなおやじギャグ(すみません)連発のゆるめのトーク。
緊張と緩和というのでしょうか。
客席もすっかりお二人のペースに乗って、楽しいコンサートになりました。
小中学校で鉄琴に触れた方は多いと思いますが、本格的なヴィブラフォンの演奏を聴く機会は意外と少ないですね。
楽器紹介のトークでは、ペダルやファン……ファンが楽器についているのは知りませんでした!……を使用するとしないとで、どんな風に音が違うのかを聞かせててくださいました。
ペダルを踏むとエコーがかかったように音が広がり、ファンを回すと、ヴィブラートがかかるのですよ。
ちなみに、コンビ名のメーテルリンクは、幸せを運ぶ「青い鳥」の作者Maeterlinckからとっているのですが、
ちょっとスペルが違っていて、Megterlinkです。
これはお二人の名前、恵「メグみ」と芳輝「よしテル」が「リンクする」→メグテルリンク→メーテルリンク
という洒落にもなっているそうで……やっぱりオチがつく!
プログラムの方は、クリスマスソングメドレーのほか、ジャズアレンジの熊蜂の飛行「Bumble Bee Boogie」やピアソラのタンゴなど、
少し大人な雰囲気のクリスマスコンサートでした♪♪♪
終演後のインタビューです。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
今回で、2018年のサンマチは終了。
来年は、vol.208「瀧廉太郎へのオマージュ」から始まります。
どうぞお楽しみに!
【出演】
Megterlink(服部 恵(ヴィブラフォン)
伊藤 芳輝(ギター)

今年のクリスマスコンサートは、ヴィブラフォンとギターのデュオ、Megterlink(メーテルリンク)のお二人でした。
超絶技巧!連発のすばらしい演奏とうらはら?に、伊藤さんのつぶやくようなおやじギャグ(すみません)連発のゆるめのトーク。
緊張と緩和というのでしょうか。
客席もすっかりお二人のペースに乗って、楽しいコンサートになりました。
小中学校で鉄琴に触れた方は多いと思いますが、本格的なヴィブラフォンの演奏を聴く機会は意外と少ないですね。
楽器紹介のトークでは、ペダルやファン……ファンが楽器についているのは知りませんでした!……を使用するとしないとで、どんな風に音が違うのかを聞かせててくださいました。
ペダルを踏むとエコーがかかったように音が広がり、ファンを回すと、ヴィブラートがかかるのですよ。
ちなみに、コンビ名のメーテルリンクは、幸せを運ぶ「青い鳥」の作者Maeterlinckからとっているのですが、
ちょっとスペルが違っていて、Megterlinkです。
これはお二人の名前、恵「メグみ」と芳輝「よしテル」が「リンクする」→メグテルリンク→メーテルリンク
という洒落にもなっているそうで……やっぱりオチがつく!
プログラムの方は、クリスマスソングメドレーのほか、ジャズアレンジの熊蜂の飛行「Bumble Bee Boogie」やピアソラのタンゴなど、
少し大人な雰囲気のクリスマスコンサートでした♪♪♪
終演後のインタビューです。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
今回で、2018年のサンマチは終了。
来年は、vol.208「瀧廉太郎へのオマージュ」から始まります。
どうぞお楽しみに!
2018年12月03日
サンデー・マティネ・コンサートvol.206
<フルート& ハープコンサート>
【出演】
緒方 里珠(フルート)
小幡 華子(ハープ)

フルートとハープの組合せは、2015年のvo.138以来。ずいぶんと久しぶりになりました。すっかり冬になったような寒さでしたが、劇場内は優しい音色に包まれました。
楽器紹介のコーナー、まずは緒方さんのフルートのお話から。
材質が金か銀かによる音色の違いについて「目を閉じて聴くとわからない程度の違いかもしれませんが」とおっしゃりながら、吹き口に近い部分を金、下半分?を銀でつなげた、こだわりのフルート!
「銀の音色に、金ならではのキラキラした感じを加えたくて」自ら注文してオリジナルで作成してもらい、高校生の頃からずっと使っていらっしゃるのだそうです!
ハープは、ふだん身近に見ることの少ない楽器とあって、お客さまも興味津々。一見、優雅に絃をつま弾いているように見えますが、足元では7つものペダルを3段階で踏みながら音階を変え、手元では44本の弦を間違うことなく演奏するという、なかなかにハードモードな楽器です。1曲でペダルを100回踏みかえることもあるんだそうですよ!
プログラム最後の「荒城の月」は、フルート奏者ジャン=ピエール・ランパルが、日本の曲をフルートとハープのために編曲したシリーズの1曲。しっとりとコンサートのフィナーレを飾りました。
ところで、久々の仙川トークでは、緒方さんが「ローカルインディア」、小幡さんが「李記担担麺食堂」「なみはな」をあげてくださいました。いずれも美味しいですよ。皆さんも仙川にいらした際はどうぞ♪
終演後のインタビューをご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
緒方 里珠(フルート)
小幡 華子(ハープ)
フルートとハープの組合せは、2015年のvo.138以来。ずいぶんと久しぶりになりました。すっかり冬になったような寒さでしたが、劇場内は優しい音色に包まれました。
楽器紹介のコーナー、まずは緒方さんのフルートのお話から。
材質が金か銀かによる音色の違いについて「目を閉じて聴くとわからない程度の違いかもしれませんが」とおっしゃりながら、吹き口に近い部分を金、下半分?を銀でつなげた、こだわりのフルート!
「銀の音色に、金ならではのキラキラした感じを加えたくて」自ら注文してオリジナルで作成してもらい、高校生の頃からずっと使っていらっしゃるのだそうです!
ハープは、ふだん身近に見ることの少ない楽器とあって、お客さまも興味津々。一見、優雅に絃をつま弾いているように見えますが、足元では7つものペダルを3段階で踏みながら音階を変え、手元では44本の弦を間違うことなく演奏するという、なかなかにハードモードな楽器です。1曲でペダルを100回踏みかえることもあるんだそうですよ!
プログラム最後の「荒城の月」は、フルート奏者ジャン=ピエール・ランパルが、日本の曲をフルートとハープのために編曲したシリーズの1曲。しっとりとコンサートのフィナーレを飾りました。
ところで、久々の仙川トークでは、緒方さんが「ローカルインディア」、小幡さんが「李記担担麺食堂」「なみはな」をあげてくださいました。いずれも美味しいですよ。皆さんも仙川にいらした際はどうぞ♪
終演後のインタビューをご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック