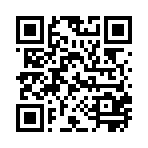2019年06月28日
サンデー・マティネ・コンサートvol.216
6月最後のコンサートは、サンデー・マティネ・コンサートとして桐朋学園大学学生による金管五重奏コンサートです。
昨年もスタートコンサートで華々しい演奏を聴かせて下さいました金管の学生たちでしたが、今回も素敵な演奏を聴かせて下さいました。演奏者の皆さんは、プログラムの色と同じ青や紫で衣装を統一して下さり、会場も一層華やかに。目で見ても楽しいのが演奏会の醍醐味ですよね。

プログラムは、アメリカの作曲家のしっかりとした金管アンサンブルを聴かせる作品もあり、皆さんが知っている童謡やサウンド・オブ・ミュージックのメドレーを金管アンサンブル用に編曲した作品もあり、様々な世代がいらっしゃるサンデー・マティネ・コンサートにぴったりの内容です。特に、金管で聴く童謡メドレーは、楽器の音色の特徴が存分に生かされ、6月の終わりにふさわしい心温まる演奏だったと思います。

さて、7月もサンデー・マティネ・コンサートは2回あります!オペラによる七夕コンサートに、ウクレレの高橋重人さんが久々の再登場!そのあとは、せんがわピアノオーディション!仙川に愛されるピアニストを発掘する大切な企画です!ピアニストの方々、ぜひご応募してくださいね!
来月も再来月もせんがわ劇場での様々な企画楽しみにして下さい!
【サンデー・マティネ・コンサートvol.216 金管五重奏コンサート】
【出演】
中島 巧乃介(トランペット)
矢野 緋奈子(トランペット)
藤野 千鶴(ホルン)
黒野 茉里恵(トロンボーン)
山崎 勇太(チューバ)
【プログラム】
グランドバレー・ファンファーレ(エワイゼン)
亜麻色の髪の乙女(ドビュッシー/クルシャ)
懐かしの童謡・唱歌メドレー(おぼろ月夜、鯉のぼり、海、浜辺の歌、赤とんぼ、スキー)
シースケッチ(マクドナルド)
サウンド・オブ・ミュージック・セレクション(ロジャース/ゲイル)
昨年もスタートコンサートで華々しい演奏を聴かせて下さいました金管の学生たちでしたが、今回も素敵な演奏を聴かせて下さいました。演奏者の皆さんは、プログラムの色と同じ青や紫で衣装を統一して下さり、会場も一層華やかに。目で見ても楽しいのが演奏会の醍醐味ですよね。
プログラムは、アメリカの作曲家のしっかりとした金管アンサンブルを聴かせる作品もあり、皆さんが知っている童謡やサウンド・オブ・ミュージックのメドレーを金管アンサンブル用に編曲した作品もあり、様々な世代がいらっしゃるサンデー・マティネ・コンサートにぴったりの内容です。特に、金管で聴く童謡メドレーは、楽器の音色の特徴が存分に生かされ、6月の終わりにふさわしい心温まる演奏だったと思います。
さて、7月もサンデー・マティネ・コンサートは2回あります!オペラによる七夕コンサートに、ウクレレの高橋重人さんが久々の再登場!そのあとは、せんがわピアノオーディション!仙川に愛されるピアニストを発掘する大切な企画です!ピアニストの方々、ぜひご応募してくださいね!
来月も再来月もせんがわ劇場での様々な企画楽しみにして下さい!
【サンデー・マティネ・コンサートvol.216 金管五重奏コンサート】
【出演】
中島 巧乃介(トランペット)
矢野 緋奈子(トランペット)
藤野 千鶴(ホルン)
黒野 茉里恵(トロンボーン)
山崎 勇太(チューバ)
【プログラム】
グランドバレー・ファンファーレ(エワイゼン)
亜麻色の髪の乙女(ドビュッシー/クルシャ)
懐かしの童謡・唱歌メドレー(おぼろ月夜、鯉のぼり、海、浜辺の歌、赤とんぼ、スキー)
シースケッチ(マクドナルド)
サウンド・オブ・ミュージック・セレクション(ロジャース/ゲイル)
2019年06月28日
サンデー・マティネ・コンサートvol.215 世界の楽器シリーズ
ファミリー音楽プログラムの翌日、6月9日には、サンデー・マティネ・コンサートが開催されました。今回のサンデー・マティネ・コンサートは、6年前に出演頂いたクロマチックハーモニカの山下伶さん。共演にはギタリストの山下俊輔さんがいらしてくださいました。

このコンサート、非常に問合せが多く、期待の高いコンサートで、当日も会場に入りきらない多くのお客様がいらして下さいました。
コンサートの方は、デビュー当初の作品から最近の録音まで、お二人の様々な思い出のある作品がちりばめられたプログラム。そして、お二人の圧倒的なパフォーマンス。会場が盛り上がらないわけがありません。演奏の合間には、お二人の出身校である桐朋学園芸術短期大学の教授であり、せんがわ劇場のアドバイザーである松井康司先生との学生生活の思い出話も挟んで頂き、せんがわ劇場ならではの「ライブ」となりました。

また、近いうちにお二人をお招き出来るよう、せんがわ劇場も頑張ります!

【サンデー・マティネ・コンサートvol.215 世界の楽器シリーズ】
【出演】
山下伶(クロマチック・ハーモニカ)
山下俊輔(ギター)
【プログラム】
1. Cavatina
2. かけら
3. リベルタンゴ
4. 月下の残像
6. Spain
5. ひまわり
このコンサート、非常に問合せが多く、期待の高いコンサートで、当日も会場に入りきらない多くのお客様がいらして下さいました。
コンサートの方は、デビュー当初の作品から最近の録音まで、お二人の様々な思い出のある作品がちりばめられたプログラム。そして、お二人の圧倒的なパフォーマンス。会場が盛り上がらないわけがありません。演奏の合間には、お二人の出身校である桐朋学園芸術短期大学の教授であり、せんがわ劇場のアドバイザーである松井康司先生との学生生活の思い出話も挟んで頂き、せんがわ劇場ならではの「ライブ」となりました。
また、近いうちにお二人をお招き出来るよう、せんがわ劇場も頑張ります!
【サンデー・マティネ・コンサートvol.215 世界の楽器シリーズ】
【出演】
山下伶(クロマチック・ハーモニカ)
山下俊輔(ギター)
【プログラム】
1. Cavatina
2. かけら
3. リベルタンゴ
4. 月下の残像
6. Spain
5. ひまわり
2019年05月20日
サンデー・マティネ・コンサート vol.214 〈未来のホープコンサートvol.24〉
【サンデー・マティネ・コンサートvol.214】
今回は、未来のホープコンサートvol.24として、守永由香さんをお招きしました。桐朋学園に在籍しながらも、既に輝かしい経歴をお持ちのピアニストです。
今回のサンマチでは、ピアニストのレパートリーの王道であるショパンのみを演奏するオール・ショパン・プログラム(さらに演奏された3曲ともワルシャワ出身のショパンがフランス滞在時に作曲されたそうです)を組んでくださいました。

サンマチのスタンプによる予約席が多かった今回の演奏会ですが、有難いことに満席御礼。入場出来なかったお客様大変申し訳ありません。
ショパンの作品は、ピアノの詩人なんて呼ばれることが多々ありますが、守永さんの演奏は、圧倒的な技巧はもちろん、バラードやポロネーズなどの難易度が非常に高い作品でも、常にその音楽が語りかけてくるような繊細さが感じられる見事な演奏でした。

まさしく、ショパンを弾くために生まれたピアニストと思いきや、実は一番好きな作曲家はシューマンだそうです笑 次回は、シューマンも聴いてみたいですね。
演奏の合間には、朗らかな人柄も見せてくれました。

未来のホープにふさわしい守永さんのさらなるご活躍をせんがわ劇場一同楽しみしております。
次回は、クロマチックハーモニカの山下伶さんがギタリストの山下俊輔さんと登場されます。ぜひご期待下さい!
SMC vol.214 5月19日
未来のホープコンサート
出演:守永由香(ピアノ)
演奏曲目:
~オール・ショパン・プログラム~
ノクターン ロ長調 Op. 9 - 3
バラード 第1番 ト短調 Op. 23
幻想ポロネーズ Op. 61
今回は、未来のホープコンサートvol.24として、守永由香さんをお招きしました。桐朋学園に在籍しながらも、既に輝かしい経歴をお持ちのピアニストです。
今回のサンマチでは、ピアニストのレパートリーの王道であるショパンのみを演奏するオール・ショパン・プログラム(さらに演奏された3曲ともワルシャワ出身のショパンがフランス滞在時に作曲されたそうです)を組んでくださいました。
サンマチのスタンプによる予約席が多かった今回の演奏会ですが、有難いことに満席御礼。入場出来なかったお客様大変申し訳ありません。
ショパンの作品は、ピアノの詩人なんて呼ばれることが多々ありますが、守永さんの演奏は、圧倒的な技巧はもちろん、バラードやポロネーズなどの難易度が非常に高い作品でも、常にその音楽が語りかけてくるような繊細さが感じられる見事な演奏でした。

まさしく、ショパンを弾くために生まれたピアニストと思いきや、実は一番好きな作曲家はシューマンだそうです笑 次回は、シューマンも聴いてみたいですね。
演奏の合間には、朗らかな人柄も見せてくれました。

未来のホープにふさわしい守永さんのさらなるご活躍をせんがわ劇場一同楽しみしております。
次回は、クロマチックハーモニカの山下伶さんがギタリストの山下俊輔さんと登場されます。ぜひご期待下さい!
SMC vol.214 5月19日
未来のホープコンサート
出演:守永由香(ピアノ)
演奏曲目:
~オール・ショパン・プログラム~
ノクターン ロ長調 Op. 9 - 3
バラード 第1番 ト短調 Op. 23
幻想ポロネーズ Op. 61
2019年05月06日
サンデー・マティネ・コンサートvol.213
【サンデー・マティネ・コンサートvol.213】
出演:芝 有維(しば ゆい) (篠笛)、有馬 美梨(ありま みのり)(箏)、金子 昇馬(かねこ しょうま) (箏)
令和元年、最初のサンデー・マティネ・コンサートは、日本音楽の世界として、篠笛と箏によるそれぞれの独奏とアンサンブルのコンサート。新しい元号の始まりにふさわしい和楽器の演奏をお楽しみ頂きました。
10連休とのことでご旅行される方も多く、お客様がいらっしゃるか不安でしたが、有難いことに今回もほぼ満席となりました!
出演者は、桐朋学園芸術短期大学に在籍している芝さん、有馬さん、金子さんの3名。日本において数少ない邦楽を専門的に学べる音楽大学がある仙川ならではの大切な企画です。

今回、演奏して頂いたのは、演奏者によって受け継がれて来た伝統ある古典の作品と新しく和楽器のために作曲された現代の作品。演奏の合間には、楽器の紹介や楽譜にも触れて頂き、西洋の楽器とは異なる特徴や多様な種類を分かり易く解説して頂きました。
そして、なんと言っても素敵なのは実際の演奏。若々しい力強さと表情豊かな音楽には、会場全体が引き込まれ、和楽器の魅力をたっぷり堪能出来たのではないでしょうか。

早くも次回は、もっと楽器の種類を増やしてやろうという声もちらほら。近いうちにまた皆様に日本の伝統芸術の素晴らしをお届け出来たらと思います。
さて、次回もまた、「未来のホープ」として、ピアノの守永由香さんがショパンを演奏して下さいます。若くして日本音楽コンクールで入選するなど将来を有望視されている若手の演奏!ぜひご期待下さい!
SMC vol.213 5月5日
日本音楽の世界
出演:芝 有維(しば ゆい) (篠笛)、有馬 美梨(ありま みのり)(箏)、金子 昇馬(かねこ しょうま) (箏)
演奏曲目:
箏譚詩集 Ⅰ 小さな序曲、Ⅴ やがて春が(三木稔作曲)
祭り囃子より『はねこ踊り』(作曲者不明)
古典曲『獅子狂い五段』(作曲者不明)
「三つの断章」(中能島欣一)
「二つの田園詩」(長沢勝俊)
出演:芝 有維(しば ゆい) (篠笛)、有馬 美梨(ありま みのり)(箏)、金子 昇馬(かねこ しょうま) (箏)
令和元年、最初のサンデー・マティネ・コンサートは、日本音楽の世界として、篠笛と箏によるそれぞれの独奏とアンサンブルのコンサート。新しい元号の始まりにふさわしい和楽器の演奏をお楽しみ頂きました。
10連休とのことでご旅行される方も多く、お客様がいらっしゃるか不安でしたが、有難いことに今回もほぼ満席となりました!
出演者は、桐朋学園芸術短期大学に在籍している芝さん、有馬さん、金子さんの3名。日本において数少ない邦楽を専門的に学べる音楽大学がある仙川ならではの大切な企画です。
今回、演奏して頂いたのは、演奏者によって受け継がれて来た伝統ある古典の作品と新しく和楽器のために作曲された現代の作品。演奏の合間には、楽器の紹介や楽譜にも触れて頂き、西洋の楽器とは異なる特徴や多様な種類を分かり易く解説して頂きました。
そして、なんと言っても素敵なのは実際の演奏。若々しい力強さと表情豊かな音楽には、会場全体が引き込まれ、和楽器の魅力をたっぷり堪能出来たのではないでしょうか。
早くも次回は、もっと楽器の種類を増やしてやろうという声もちらほら。近いうちにまた皆様に日本の伝統芸術の素晴らしをお届け出来たらと思います。
さて、次回もまた、「未来のホープ」として、ピアノの守永由香さんがショパンを演奏して下さいます。若くして日本音楽コンクールで入選するなど将来を有望視されている若手の演奏!ぜひご期待下さい!
SMC vol.213 5月5日
日本音楽の世界
出演:芝 有維(しば ゆい) (篠笛)、有馬 美梨(ありま みのり)(箏)、金子 昇馬(かねこ しょうま) (箏)
演奏曲目:
箏譚詩集 Ⅰ 小さな序曲、Ⅴ やがて春が(三木稔作曲)
祭り囃子より『はねこ踊り』(作曲者不明)
古典曲『獅子狂い五段』(作曲者不明)
「三つの断章」(中能島欣一)
「二つの田園詩」(長沢勝俊)
2019年04月16日
サンデー・マティネ・コンサートvol.212
【サンデー・マティネ・コンサートvol.212】
出演:ヴァンサン・リュカ(フルート)、東井美佳(ピアノ)
本年度のスタートコンサートは、パリ管弦楽団首席フルーティストのヴァンサン・リュカさんとピアノの東井美佳さんをお迎えした豪華な演奏会でした。リュカさんが演奏して下さるのは、せんがわ劇場ではなんと3度目。開場前から長蛇の列が出来る盛況ぶりでした。残念ながら入場出来なかったお客様には、リュカさんがロビーにいらしてフルートを吹いて下さるサプライズも!
今回のコンサートでは、ドビュッシーやフォーレのフルートならではの名作を中心にお送りしました。特に、最後のカルメン幻想曲での圧倒的な技巧には、ただただ感嘆するばかり!リュカさんの引き込まれるようなフルートの音色と東井さんとの見事なアンサンブルに多くのお客様より「素晴らしかった」との声を頂きました!

Facebookには公演後のインタービューもアップしましたので、ぜひご覧ください。
今年度も、せんがわ劇場は、皆さまに上質で親しみやすい音楽をお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします!
【プログラム】
ドビュッシー:シリンクス
牧神の午後への前奏曲
J.S.バッハ:フルートソナタ ホ長調 BWV1035
フォーレ:シシリエンヌ
グルック :精霊の踊り
オネゲル:雌山羊の踊り
ボルヌ:カルメン幻想曲

出演:ヴァンサン・リュカ(フルート)、東井美佳(ピアノ)
本年度のスタートコンサートは、パリ管弦楽団首席フルーティストのヴァンサン・リュカさんとピアノの東井美佳さんをお迎えした豪華な演奏会でした。リュカさんが演奏して下さるのは、せんがわ劇場ではなんと3度目。開場前から長蛇の列が出来る盛況ぶりでした。残念ながら入場出来なかったお客様には、リュカさんがロビーにいらしてフルートを吹いて下さるサプライズも!
今回のコンサートでは、ドビュッシーやフォーレのフルートならではの名作を中心にお送りしました。特に、最後のカルメン幻想曲での圧倒的な技巧には、ただただ感嘆するばかり!リュカさんの引き込まれるようなフルートの音色と東井さんとの見事なアンサンブルに多くのお客様より「素晴らしかった」との声を頂きました!
Facebookには公演後のインタービューもアップしましたので、ぜひご覧ください。
今年度も、せんがわ劇場は、皆さまに上質で親しみやすい音楽をお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします!
【プログラム】
ドビュッシー:シリンクス
牧神の午後への前奏曲
J.S.バッハ:フルートソナタ ホ長調 BWV1035
フォーレ:シシリエンヌ
グルック :精霊の踊り
オネゲル:雌山羊の踊り
ボルヌ:カルメン幻想曲
2019年03月28日
【サンデー・マティネ・コンサートPlus vol.16】
【サンデー・マティネ・コンサートPlus vol.16】
【出演】
カルテット・プラチナム
沼田園子(ヴァイオリン)
野口千代光(ヴァイオリン)
大野かおる(ヴィオラ)
菊地知也(チェロ)

10周年を迎えた平成30年度せんがわ劇場の最後のコンサートは、
弦楽器の名手4人による弦楽四重奏カルテット・プラチナムの演奏で締めくくりました。
アンケートでは「素晴らしい」が沢山。
本当に贅沢な1時間で、客席内はどこか音楽の世界に飛んでいったかのような空間になっていました!
カルテット・プラチナムの皆さま、素晴らしい演奏をありがとうございました。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
カルテット・プラチナム
沼田園子(ヴァイオリン)
野口千代光(ヴァイオリン)
大野かおる(ヴィオラ)
菊地知也(チェロ)

10周年を迎えた平成30年度せんがわ劇場の最後のコンサートは、
弦楽器の名手4人による弦楽四重奏カルテット・プラチナムの演奏で締めくくりました。
アンケートでは「素晴らしい」が沢山。
本当に贅沢な1時間で、客席内はどこか音楽の世界に飛んでいったかのような空間になっていました!
カルテット・プラチナムの皆さま、素晴らしい演奏をありがとうございました。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
2019年03月20日
【サンデー・マティネ・コンサートvol.211】<ピアノトリオコンサート>
<ピアノトリオコンサート>
出演:吉村美智子( ヴァイオリン)
内山剛博( チェロ)
齊野晴香( ピアノ)
今シーズン最後のサンマチは、ピアノトリオ。
弦楽器だけの組合せではなく、メロディも伴奏も、何ならリズムも担当できるピアノが入ることで、
ヴァイオリンもチェロも、よりソリスト色が強くなるというか、個性が発揮される感じなのでしょうか。
このピアノトリオを、桐朋学園大学の1年生と3年生という、フレッジュかつ実力派の皆さんにご出演いただき、お届けしました!
特に2曲目のドビュッシーは全楽章、20分近くの演奏で、しっかりご堪能していただけたのではないかと思います。
恒例の「せんがわトーク」では、それぞれのランチタイムをご紹介。
斎野さんはお弁当中心なので・・・と特にお店は上がりませんでしたが(これも素晴らしいですね!)、
吉村さんは、見晴らしがよいsengawa Poireをあげてくださいました。
特筆は内山さん。このコーナーの存在を知っていたので準備してきました!と、
串カツ居酒屋 民屋、武蔵野うどん和酒 たか乃(残念ながら3月で閉店)、
更にお好きなラーメン屋さんで、めでたや・しば田、と、4軒も紹介の大サービス?でした。
コンサートの最後では、8年にわたり、サンマチをはじめとした音楽事業を長年担当し、
今年度で劇場を離れるスタッフMが、初めてステージでご挨拶しました。
来年度から、せんがわ劇場は、調布市直営から、調布市文化・コミュニティ振興財団の運営となりますが、
サンデー・マティネ・コンサートは引き続き開催します。
これからも、皆さまのお越しをお待ちしております!
終演後の写真は左から、斎野晴香さん、吉村美智子さん、内山剛博さんです。
堂々とした演奏から一変、2枚目のピース写真をみると、やはり若者!とほほえましくなるスタッフHでした☺️


終演後コメントは、斎野晴香さん、吉村美智子さん、内山剛博さんの順番です。どうぞご覧ください!
公演詳細はこちらからどうぞ→ここをクリック
出演:吉村美智子( ヴァイオリン)
内山剛博( チェロ)
齊野晴香( ピアノ)
今シーズン最後のサンマチは、ピアノトリオ。
弦楽器だけの組合せではなく、メロディも伴奏も、何ならリズムも担当できるピアノが入ることで、
ヴァイオリンもチェロも、よりソリスト色が強くなるというか、個性が発揮される感じなのでしょうか。
このピアノトリオを、桐朋学園大学の1年生と3年生という、フレッジュかつ実力派の皆さんにご出演いただき、お届けしました!
特に2曲目のドビュッシーは全楽章、20分近くの演奏で、しっかりご堪能していただけたのではないかと思います。
恒例の「せんがわトーク」では、それぞれのランチタイムをご紹介。
斎野さんはお弁当中心なので・・・と特にお店は上がりませんでしたが(これも素晴らしいですね!)、
吉村さんは、見晴らしがよいsengawa Poireをあげてくださいました。
特筆は内山さん。このコーナーの存在を知っていたので準備してきました!と、
串カツ居酒屋 民屋、武蔵野うどん和酒 たか乃(残念ながら3月で閉店)、
更にお好きなラーメン屋さんで、めでたや・しば田、と、4軒も紹介の大サービス?でした。
コンサートの最後では、8年にわたり、サンマチをはじめとした音楽事業を長年担当し、
今年度で劇場を離れるスタッフMが、初めてステージでご挨拶しました。
来年度から、せんがわ劇場は、調布市直営から、調布市文化・コミュニティ振興財団の運営となりますが、
サンデー・マティネ・コンサートは引き続き開催します。
これからも、皆さまのお越しをお待ちしております!
終演後の写真は左から、斎野晴香さん、吉村美智子さん、内山剛博さんです。
堂々とした演奏から一変、2枚目のピース写真をみると、やはり若者!とほほえましくなるスタッフHでした☺️


終演後コメントは、斎野晴香さん、吉村美智子さん、内山剛博さんの順番です。どうぞご覧ください!
公演詳細はこちらからどうぞ→ここをクリック
2019年03月05日
サンデー・マティネ・コンサートvol.210 東京の民謡を知る
<東京の民謡を知る>
【出演】
村松 喜久則(唄・構成・ご案内)
京極 加津恵(唄・ご案内)
月岡 雪子(笛・三味線)
モード・アルシャンボー(鳴り物・踊り)

民謡。
日本全国に民謡がどのくらいあるかご存知ですか?
何と58,000曲!!(昭和62年調査)
しかも、何となく、地方の方がたくさんの民謡がある気がしていましたが、
実は東京は「民謡の宝庫」ともいわれるほど、多くの民謡が残されている地域なんだそうです!
今回は、たくさんあるにもかかわらず、
意外と知らない民謡の数々を、わかりやすく楽しい解説と共に、聴くことができました。
考えてみると、江戸は、当時世界でも有数の人口を抱える大都市で、
地方との行き来も既に盛んにおこなわれていましたから、
各地の民謡が江戸に伝わるのは、当然なのかもしれません。
(江戸を経由して、また他の地方に伝わって行ったりもしたようです)
こうして広まるうちに、少しずつお土地柄にあわせて歌詞が変わり、テンポやメロディが変わっていく。
江戸の民謡は、江戸っ子気質を反映してか「節の上がり下がりが激しく、旋律が直線的で、歯切れがよい」んですって。なるほど!
民謡は、誰が作ったのでもなく、日々の労働や暮らしの中から生まれ、
文字や楽譜ではなく口から耳へ伝えられてきたもの。
田畑を耕す歌、舟をこぐ歌、遊びに行こうとする若者の気持ちをうたった歌など、
ごく自然に口ずさみながら生活していたのかもしれませんね。
冷たい雨の中ご来場くださったお客さまも、大満足のコンサートでした!
終演後、皆さんからコメントをいただきました。
京極 加津恵さん、モード・アルシャンボーさん、月岡 雪子さん、村松 喜久則さんの順です。
ぜひご覧ください!
※モード・アルシャンボーさんはカナダ人で、外国人として初めて、日本(一社)民謡プロ協会に入会して活躍中の方です。
※村松さんのコメント中にサイレンが入っています。お聞き苦しい点、ご容赦ください。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
村松 喜久則(唄・構成・ご案内)
京極 加津恵(唄・ご案内)
月岡 雪子(笛・三味線)
モード・アルシャンボー(鳴り物・踊り)
民謡。
日本全国に民謡がどのくらいあるかご存知ですか?
何と58,000曲!!(昭和62年調査)
しかも、何となく、地方の方がたくさんの民謡がある気がしていましたが、
実は東京は「民謡の宝庫」ともいわれるほど、多くの民謡が残されている地域なんだそうです!
今回は、たくさんあるにもかかわらず、
意外と知らない民謡の数々を、わかりやすく楽しい解説と共に、聴くことができました。
考えてみると、江戸は、当時世界でも有数の人口を抱える大都市で、
地方との行き来も既に盛んにおこなわれていましたから、
各地の民謡が江戸に伝わるのは、当然なのかもしれません。
(江戸を経由して、また他の地方に伝わって行ったりもしたようです)
こうして広まるうちに、少しずつお土地柄にあわせて歌詞が変わり、テンポやメロディが変わっていく。
江戸の民謡は、江戸っ子気質を反映してか「節の上がり下がりが激しく、旋律が直線的で、歯切れがよい」んですって。なるほど!
民謡は、誰が作ったのでもなく、日々の労働や暮らしの中から生まれ、
文字や楽譜ではなく口から耳へ伝えられてきたもの。
田畑を耕す歌、舟をこぐ歌、遊びに行こうとする若者の気持ちをうたった歌など、
ごく自然に口ずさみながら生活していたのかもしれませんね。
冷たい雨の中ご来場くださったお客さまも、大満足のコンサートでした!
終演後、皆さんからコメントをいただきました。
京極 加津恵さん、モード・アルシャンボーさん、月岡 雪子さん、村松 喜久則さんの順です。
ぜひご覧ください!
※モード・アルシャンボーさんはカナダ人で、外国人として初めて、日本(一社)民謡プロ協会に入会して活躍中の方です。
※村松さんのコメント中にサイレンが入っています。お聞き苦しい点、ご容赦ください。
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
2019年02月11日
サンデー・マチネ・コンサートvol209 世界の楽器シリーズ<フィンランドの楽器・カンテレ>
~世界の楽器シリーズ~
<フィンランドの楽器・カンテレ>
【 出演】
はざた雅子(カンテレ)

カンテレ。関西テレビの略ではありません。楽器の名前です。
しかも、イントネーションは「カ↓ンテレ」で、「カ」が高いのです。関西テレビのカンテレとは逆です。
ふざけたような書き出しになってしまいましたが、そのくらい、日本ではなじみのない楽器ではないでしょうか。
フィンランドの民族楽器です。
写真をご覧いただくとわかりますが、木製の胴体にスチール絃を張っています。
小さなハープを横に倒した感じ・・・?
でもギターのように共鳴させる胴体を持っているところが違いますね。




左側の、蝶番の付いている木の部分はミュートです。
残響音が非常に長い楽器なので、これで音を止めます。
その上についているレバーは、半音をだすためのもの。
演奏の際は、忙しくあれこれ操作していらっしゃいました。
もともとは40cmほどの、木をくりぬいたものに弦を5本張った、とてもシンプルな楽器だったのが、
時代を追って絃の数が増えていき、今の形に進化してきたそうです。
(写真を撮り忘れました・・・すみません)
後でお話を伺ったところ、フィンランドでも、伝統楽器として大切にはされているものの演奏家は多くなく、
近年は(5弦のシンプルなものを)小学校で体験する時間が設けられるようになっているそうで・・・
日本における和楽器の状況とも似ている、と感じました。
日本ではもちろん手に入れることはできず、フィンランドに注文して輸入。
30万円くらいの楽器が輸送料でさらに2~3倍、と、大きなカンテレはさすがに大変ですが、
5弦のものは、最近ネットの個人輸入で2~3万で手に入るようになり、趣味で始める方もいるとか!
会場の9割以上、司会の合田先生すら「はじめて見た」楽器とあって、
終演後には、お客さまがステージにどっと集まって楽器の見学、撮影大会になりました。
でもその中でお一人,
「せんがわ劇場でカンテレが聴けるなんてとてもうれしいです。楽しみにしていました!」とおっしゃるお客さまが。
コンサートの前後で「はじめて」「知らない」を連発してしまいましたけど、
こうしたファンの方もちゃんといらっしゃるし、とても喜んでくださって、よかったなあと思ったのでした。
終演後のインタビューです。
「今日いらしたお客さまは、カンテレって、静かでおとなしい感じの楽器と思われたかもしれませんが、
もっといろんな曲や演奏法もあって、盛り上がるものもあるんですよ。またぜひどこかで聴いてください」
ともおっしゃっていました。
ニュースにもなる寒さの中、たくさんのお客さまにご来場いただきました。本当にありがとうございました!
<フィンランドの楽器・カンテレ>
【 出演】
はざた雅子(カンテレ)

カンテレ。関西テレビの略ではありません。楽器の名前です。
しかも、イントネーションは「カ↓ンテレ」で、「カ」が高いのです。関西テレビのカンテレとは逆です。
ふざけたような書き出しになってしまいましたが、そのくらい、日本ではなじみのない楽器ではないでしょうか。
フィンランドの民族楽器です。
写真をご覧いただくとわかりますが、木製の胴体にスチール絃を張っています。
小さなハープを横に倒した感じ・・・?
でもギターのように共鳴させる胴体を持っているところが違いますね。




左側の、蝶番の付いている木の部分はミュートです。
残響音が非常に長い楽器なので、これで音を止めます。
その上についているレバーは、半音をだすためのもの。
演奏の際は、忙しくあれこれ操作していらっしゃいました。
もともとは40cmほどの、木をくりぬいたものに弦を5本張った、とてもシンプルな楽器だったのが、
時代を追って絃の数が増えていき、今の形に進化してきたそうです。
(写真を撮り忘れました・・・すみません)
後でお話を伺ったところ、フィンランドでも、伝統楽器として大切にはされているものの演奏家は多くなく、
近年は(5弦のシンプルなものを)小学校で体験する時間が設けられるようになっているそうで・・・
日本における和楽器の状況とも似ている、と感じました。
日本ではもちろん手に入れることはできず、フィンランドに注文して輸入。
30万円くらいの楽器が輸送料でさらに2~3倍、と、大きなカンテレはさすがに大変ですが、
5弦のものは、最近ネットの個人輸入で2~3万で手に入るようになり、趣味で始める方もいるとか!
会場の9割以上、司会の合田先生すら「はじめて見た」楽器とあって、
終演後には、お客さまがステージにどっと集まって楽器の見学、撮影大会になりました。
でもその中でお一人,
「せんがわ劇場でカンテレが聴けるなんてとてもうれしいです。楽しみにしていました!」とおっしゃるお客さまが。
コンサートの前後で「はじめて」「知らない」を連発してしまいましたけど、
こうしたファンの方もちゃんといらっしゃるし、とても喜んでくださって、よかったなあと思ったのでした。
終演後のインタビューです。
「今日いらしたお客さまは、カンテレって、静かでおとなしい感じの楽器と思われたかもしれませんが、
もっといろんな曲や演奏法もあって、盛り上がるものもあるんですよ。またぜひどこかで聴いてください」
ともおっしゃっていました。
ニュースにもなる寒さの中、たくさんのお客さまにご来場いただきました。本当にありがとうございました!
2019年01月13日
サンデー・マティネ・コンサートvol.208
<瀧廉太郎へのオマージュ>
【出演】
松井康司(お話・バリトン)
紀野洋孝(テノール)
藤原伊央里(ピアノ)
桐朋学園芸術短大声楽アンサンブル

新年最初のサンマチは、日本が誇る作曲家、瀧廉太郎を取り上げました。
寒い中、たくさんのお客さまにお越しいただき、ありがとうございました!
明治の時代、西洋の音楽を真摯に学び、それを自身の作曲で活かす試みをしつつ、
子どもたちが楽しく歌える歌を作り、あっという間にこの世を去ってしまった瀧廉太郎。
松井先生からはたくさんのエピソードが語られ、止まらないほどでした。
たとえば「花」が、実は四季折々の組曲になっていたこと、皆さんご存知でしたか?
組曲「四季」の春が「花」で、その後「納涼」「月」「雪」と続くのです。
「月」や「雪」は、教会の聖歌のような雰囲気で、
瀧廉太郎という人は、こんな曲も作っていたのか!と、その幅広さにびっくりしました。
組曲としてはめったに演奏される機会がなく、
今日初めてお聴きになった方も多かったのではないでしょうか。
それにしても、あれほど輝かしい才能を持ち、将来を嘱望されていた瀧廉太郎が、
23歳という若さで病に倒れ、死の間際に創った遺作「憾(うらみ)」は、
彼の無念や怒り、音楽への情熱、あらゆる想いがあふれるような曲です。
タイトルを見るだけでも心が痛みます……。

ピアノ曲、ソロ、合唱など、贅沢にいろんな編成でお楽しみいただきました。
終演後のインタビューは、松井康司先生(お話・バリトン)、紀野洋孝さん(テノール)、藤原伊央里さん(ピアノ)にお願いしました。
ぜひご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
松井康司(お話・バリトン)
紀野洋孝(テノール)
藤原伊央里(ピアノ)
桐朋学園芸術短大声楽アンサンブル

新年最初のサンマチは、日本が誇る作曲家、瀧廉太郎を取り上げました。
寒い中、たくさんのお客さまにお越しいただき、ありがとうございました!
明治の時代、西洋の音楽を真摯に学び、それを自身の作曲で活かす試みをしつつ、
子どもたちが楽しく歌える歌を作り、あっという間にこの世を去ってしまった瀧廉太郎。
松井先生からはたくさんのエピソードが語られ、止まらないほどでした。
たとえば「花」が、実は四季折々の組曲になっていたこと、皆さんご存知でしたか?
組曲「四季」の春が「花」で、その後「納涼」「月」「雪」と続くのです。
「月」や「雪」は、教会の聖歌のような雰囲気で、
瀧廉太郎という人は、こんな曲も作っていたのか!と、その幅広さにびっくりしました。
組曲としてはめったに演奏される機会がなく、
今日初めてお聴きになった方も多かったのではないでしょうか。
それにしても、あれほど輝かしい才能を持ち、将来を嘱望されていた瀧廉太郎が、
23歳という若さで病に倒れ、死の間際に創った遺作「憾(うらみ)」は、
彼の無念や怒り、音楽への情熱、あらゆる想いがあふれるような曲です。
タイトルを見るだけでも心が痛みます……。

ピアノ曲、ソロ、合唱など、贅沢にいろんな編成でお楽しみいただきました。
終演後のインタビューは、松井康司先生(お話・バリトン)、紀野洋孝さん(テノール)、藤原伊央里さん(ピアノ)にお願いしました。
ぜひご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック