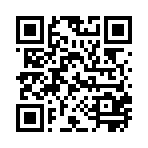2019年06月28日
ファミリー音楽プログラムvol.23 演奏会入門コンサート
更新がなかなか出来ず申し訳ありません。
6月のせんがわ劇場のコンサートはどれも大変充実したものとなりました。一つ一つ振り返りたいと思います。
6月8日(土)14時から行われたのは、「ファミリー音楽プログラムvol.23」として6月の恒例となっております「演奏会入門コンサート」です。
今回は、桐朋学園芸術短期大学の准教授であり、フルーティストの永井由比先生をお招きし、トロンボーンの村田 厚生さん、ピアノの小久保まゆきさんと一緒に演奏して頂きました。

演奏会入門コンサートは、5歳以上のお子様と保護者の皆様を対象にクラシックのコンサートに初めていくための準備となるように考えられたプログラムです。今回も、小さなお子様たちが笑顔で沢山いらして下さいました。
前半は、コンサートのマナーや、気になるけどなかなか聞けないことを永井先生にしてお話頂き、後半は、本格的なコンサートです。傘持ってきたらどうしたらいいのか、演奏会のブザーの意味などの説明や、小さなお子様が暗いところでも不安にならないか、実際に暗転も経験してもらうなど工夫を凝らした内容となっております。今回は、5~7歳くらいのお子様が多かったのですが、みなさんしっかりお話を聞いてくれました。
後半の演奏会は、クラシックってこんなに楽しいものなの?!って思わせてくれるようなユニークな曲が並びます。さらに、永井先生、村田先生が劇場を走り回って、目の前で演奏してくれるサービスっぷり。

一人一人にとって楽しいコンサートデビューの日になってくれていたらとせんがわ劇場一同願っております。
次回のファミリー音楽プログラムは、11月の予定です。ぜひご期待下さい!
【ファミリー音楽プログラムvol.23 演奏会入門コンサート】
【出演】
フルート 永井 由比
トロンボーン 村田 厚生
ピアノ 小久保 まゆき
【プログラム】
アイリッシュダンス
ブラームス:ハンガリー舞曲第5番
ベリオ:セクエンツァ
ローマン:笑うトロンボーン
ジュナン:ヴェニスの謝肉祭
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲
6月のせんがわ劇場のコンサートはどれも大変充実したものとなりました。一つ一つ振り返りたいと思います。
6月8日(土)14時から行われたのは、「ファミリー音楽プログラムvol.23」として6月の恒例となっております「演奏会入門コンサート」です。
今回は、桐朋学園芸術短期大学の准教授であり、フルーティストの永井由比先生をお招きし、トロンボーンの村田 厚生さん、ピアノの小久保まゆきさんと一緒に演奏して頂きました。
演奏会入門コンサートは、5歳以上のお子様と保護者の皆様を対象にクラシックのコンサートに初めていくための準備となるように考えられたプログラムです。今回も、小さなお子様たちが笑顔で沢山いらして下さいました。
前半は、コンサートのマナーや、気になるけどなかなか聞けないことを永井先生にしてお話頂き、後半は、本格的なコンサートです。傘持ってきたらどうしたらいいのか、演奏会のブザーの意味などの説明や、小さなお子様が暗いところでも不安にならないか、実際に暗転も経験してもらうなど工夫を凝らした内容となっております。今回は、5~7歳くらいのお子様が多かったのですが、みなさんしっかりお話を聞いてくれました。
後半の演奏会は、クラシックってこんなに楽しいものなの?!って思わせてくれるようなユニークな曲が並びます。さらに、永井先生、村田先生が劇場を走り回って、目の前で演奏してくれるサービスっぷり。
一人一人にとって楽しいコンサートデビューの日になってくれていたらとせんがわ劇場一同願っております。
次回のファミリー音楽プログラムは、11月の予定です。ぜひご期待下さい!
【ファミリー音楽プログラムvol.23 演奏会入門コンサート】
【出演】
フルート 永井 由比
トロンボーン 村田 厚生
ピアノ 小久保 まゆき
【プログラム】
アイリッシュダンス
ブラームス:ハンガリー舞曲第5番
ベリオ:セクエンツァ
ローマン:笑うトロンボーン
ジュナン:ヴェニスの謝肉祭
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲
2014年06月05日
ファミリー音楽プログラムvol.13 子どものための演奏会入門 ~はじめてのオペラ~
5月24日に行われたファミリー音楽プログラムvol.13≪子どものための演奏会入門~はじめてのオペラ~≫の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。
~~~~~~~~~~
せんがわ劇場は「次世代を担う子どもたち育成事業」に2011年より取り組んでいます。
ファミリー音楽プログラムはその一環で、前回の「おやこ楽器体験ツアー」に続く今回のテーマは、「オペラ」。
市内の5歳~小学生と保護者を対象に、敷居が高いと思われがちな「オペラ鑑賞」への入門講座です。
入場無料・予約制で、今回も多くの親子・ご家族連れがお越しくださり、はじめてのオペラ演奏会を堪能されていました。
「明るく楽しく、ためになる」せんがわ劇場の音楽事業。
今回の講師は、せんがわ劇場音楽コーディネーター・松井康司(まついやすし)先生です。
●街の中心にある劇場でオペラを毎日上演
第一部「オペラを知ろう!」は、オペラって何だろう? という視点で、オペラ劇場(オペラハウス)の説明から始まります。
「音楽の都・ウィーンやミラノ、パリではオペラハウスは街の中心にあって、オペラの公演が毎日あります」と松井先生。
「ヨーロッパではオペラが文化の最上位にあり、国をあげて大切にする伝統がある」とのこと。
そういえば、第二次大戦後、オーストリア・ウィーンの人々は「戦後復興の象徴」としてオペラ座の早期再建を願ったといわれます。
「オーケストラは舞台と客席の間で一段低くした“ピット”に入っています。もともとオーケストラは、主にオペラの伴奏をする演奏形態。ウィーン・フィルですら普段はあまり目立ちません(笑)。
オペラハウスの舞台は4面あるものもあって、素早く場面チェンジができるようになっています。舞台装置や美術、衣裳に贅の限りを尽くします。こうした劇場で、オーケストラが演奏する音楽に乗せて、歌い手がすべてのセリフを歌で表現し、ストーリーが展開する劇、それが『オペラ』なのです」。
まさに総合芸術。本場ヨーロッパで観るオペラはどんなにか華やかでしょう。その一端を、今回出演してくださった声楽家の皆さんが実演してくださいます。取り上げる演目は、モーツァルトの歌劇『魔笛』や『フィガロの結婚』、プッチーニの喜歌劇『ジャンニ・スキッキ』、などなど。名場面の実演を交えながら、オペラの「声」や「歌唱法」についての解説が入ります。
●オペラは歌はもちろん、演技力も大切
「女性の高い声がソプラノで、お姫様などを演じます。少し低い女声は、メゾ・ソプラノ、アルト。こちらはおばあさんや魔女を演じます。男性の高い声はテノールで、王子様役。低い声はバリトン、バスで、おじいさん役。声の高低で演じる役が分かるのです」(松井先生)。
ここでクイズが出されます。出演者がモーツァルト「夜の女王のアリア」、フンパーティンク「魔女の歌」、プッチーニ「私のお父さん」をそれぞれ歌い、声の高さから役を当てます。子どもたちがほとんど正解したのには、びっくり。すっかりオペラの世界の約束事に馴染んできたようです。
「オペラには4種類の歌唱法があります。お話しの中で人物が気持ちを歌い上げるアリア。ちょっとセリフっぽく歌うレチタティーヴォ。二人以上でハーモニーを聴かせる重唱、そして大勢で歌う合唱です」。
専門用語を実演で解説します。テノールで聴かせるアリア「王子タミーノの歌」(『魔笛』より)。レチタティーヴォは、コミカルな演技を交えた「ケンカの二重唱」(『フィガロの結婚』より)。ソプラノとメゾ・ソプラノが皮肉のこもったやりとりをする喜劇の場面で、なるほど、オペラは歌だけでなく、演技も大切なのだと分からせてくれます。
「レチタティーヴォでは、モーツァルトが書いた楽譜はほんの少し。伴奏のピアノも即興演奏をして劇を盛り立てます。ピアニストが演技に合わせて細かく音を入れているのが分かりますね」など、歌と演技と音楽が緊密に連携して劇としてのオペラを構成していると、松井先生の熱心な解説が続きます。

●「乾杯の歌」に始まり「乾杯の歌」で終わる
休憩をはさんで、第二部は「アンサンブルの楽しみ」です。本格的な重唱が楽しめます。
まず、モーツァルトの歌劇『魔笛』で有名な「パパパの二重唱」。パパゲーノとパパゲーナが「パ・パ・パ・・・・」と互いに呼びかけ合い、喜びを歌い上げます。
続くプッチーニの歌劇『ラ・ボエーム』より、第3幕の四重唱。愛し合いながら別れを覚悟する二人と、ののしり合いながら喧嘩別れする二人。二組の対照的なカップルの対照的な別れを「四重唱」で描いた名場面、プッチーニの傑作です。
そして、ビゼー作曲の歌劇『カルメン』より五重唱でフィナーレ。ヨハン・シュトラウスの「乾杯の歌」(喜歌劇『こうもり』)から始まった今回のレクチャー、最後はヴェルディ『椿姫』の「乾杯の歌」をアンコールでお贈りし、締めとなりました。
まさに“オペラに乾杯”する午後のひと時。それにしても年少時に「オペラ」に触れるとはなんと贅沢な体験でしょう。
子どもの頃の劇場での音楽体験は、原体験として感性に刻まれるでしょう。もしかしたら、オペラに病みつきになってしまう子どもたちも出るかもしれません。オペラの奥深い魅力を垣間見せてくれた本格的な演奏会とレクチャーでした。
(取材・文/ライター 才目)
~~~~~~~~~~
せんがわ劇場は「次世代を担う子どもたち育成事業」に2011年より取り組んでいます。
ファミリー音楽プログラムはその一環で、前回の「おやこ楽器体験ツアー」に続く今回のテーマは、「オペラ」。
市内の5歳~小学生と保護者を対象に、敷居が高いと思われがちな「オペラ鑑賞」への入門講座です。
入場無料・予約制で、今回も多くの親子・ご家族連れがお越しくださり、はじめてのオペラ演奏会を堪能されていました。
♭
「明るく楽しく、ためになる」せんがわ劇場の音楽事業。
今回の講師は、せんがわ劇場音楽コーディネーター・松井康司(まついやすし)先生です。
●街の中心にある劇場でオペラを毎日上演
第一部「オペラを知ろう!」は、オペラって何だろう? という視点で、オペラ劇場(オペラハウス)の説明から始まります。
「音楽の都・ウィーンやミラノ、パリではオペラハウスは街の中心にあって、オペラの公演が毎日あります」と松井先生。
「ヨーロッパではオペラが文化の最上位にあり、国をあげて大切にする伝統がある」とのこと。
そういえば、第二次大戦後、オーストリア・ウィーンの人々は「戦後復興の象徴」としてオペラ座の早期再建を願ったといわれます。
「オーケストラは舞台と客席の間で一段低くした“ピット”に入っています。もともとオーケストラは、主にオペラの伴奏をする演奏形態。ウィーン・フィルですら普段はあまり目立ちません(笑)。
オペラハウスの舞台は4面あるものもあって、素早く場面チェンジができるようになっています。舞台装置や美術、衣裳に贅の限りを尽くします。こうした劇場で、オーケストラが演奏する音楽に乗せて、歌い手がすべてのセリフを歌で表現し、ストーリーが展開する劇、それが『オペラ』なのです」。
まさに総合芸術。本場ヨーロッパで観るオペラはどんなにか華やかでしょう。その一端を、今回出演してくださった声楽家の皆さんが実演してくださいます。取り上げる演目は、モーツァルトの歌劇『魔笛』や『フィガロの結婚』、プッチーニの喜歌劇『ジャンニ・スキッキ』、などなど。名場面の実演を交えながら、オペラの「声」や「歌唱法」についての解説が入ります。
●オペラは歌はもちろん、演技力も大切
「女性の高い声がソプラノで、お姫様などを演じます。少し低い女声は、メゾ・ソプラノ、アルト。こちらはおばあさんや魔女を演じます。男性の高い声はテノールで、王子様役。低い声はバリトン、バスで、おじいさん役。声の高低で演じる役が分かるのです」(松井先生)。
ここでクイズが出されます。出演者がモーツァルト「夜の女王のアリア」、フンパーティンク「魔女の歌」、プッチーニ「私のお父さん」をそれぞれ歌い、声の高さから役を当てます。子どもたちがほとんど正解したのには、びっくり。すっかりオペラの世界の約束事に馴染んできたようです。
「オペラには4種類の歌唱法があります。お話しの中で人物が気持ちを歌い上げるアリア。ちょっとセリフっぽく歌うレチタティーヴォ。二人以上でハーモニーを聴かせる重唱、そして大勢で歌う合唱です」。
専門用語を実演で解説します。テノールで聴かせるアリア「王子タミーノの歌」(『魔笛』より)。レチタティーヴォは、コミカルな演技を交えた「ケンカの二重唱」(『フィガロの結婚』より)。ソプラノとメゾ・ソプラノが皮肉のこもったやりとりをする喜劇の場面で、なるほど、オペラは歌だけでなく、演技も大切なのだと分からせてくれます。
「レチタティーヴォでは、モーツァルトが書いた楽譜はほんの少し。伴奏のピアノも即興演奏をして劇を盛り立てます。ピアニストが演技に合わせて細かく音を入れているのが分かりますね」など、歌と演技と音楽が緊密に連携して劇としてのオペラを構成していると、松井先生の熱心な解説が続きます。

●「乾杯の歌」に始まり「乾杯の歌」で終わる
休憩をはさんで、第二部は「アンサンブルの楽しみ」です。本格的な重唱が楽しめます。
まず、モーツァルトの歌劇『魔笛』で有名な「パパパの二重唱」。パパゲーノとパパゲーナが「パ・パ・パ・・・・」と互いに呼びかけ合い、喜びを歌い上げます。
続くプッチーニの歌劇『ラ・ボエーム』より、第3幕の四重唱。愛し合いながら別れを覚悟する二人と、ののしり合いながら喧嘩別れする二人。二組の対照的なカップルの対照的な別れを「四重唱」で描いた名場面、プッチーニの傑作です。
そして、ビゼー作曲の歌劇『カルメン』より五重唱でフィナーレ。ヨハン・シュトラウスの「乾杯の歌」(喜歌劇『こうもり』)から始まった今回のレクチャー、最後はヴェルディ『椿姫』の「乾杯の歌」をアンコールでお贈りし、締めとなりました。
♪♪
まさに“オペラに乾杯”する午後のひと時。それにしても年少時に「オペラ」に触れるとはなんと贅沢な体験でしょう。
子どもの頃の劇場での音楽体験は、原体験として感性に刻まれるでしょう。もしかしたら、オペラに病みつきになってしまう子どもたちも出るかもしれません。オペラの奥深い魅力を垣間見せてくれた本格的な演奏会とレクチャーでした。
(取材・文/ライター 才目)