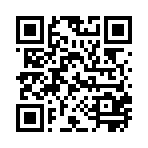2018年12月01日
受賞者インタビュー(4) パンチェッタ 一宮周平さん(グランプリ賞・オーディエンス賞・俳優賞)

左が一宮周平さん
トリプル受賞、演劇コンクールを終えていかがですか?
一宮 どうって言われても何も変わらないです(笑)全団体の演技を観た上であれば納得し、考えることもできますが、今回はコトリ会議さんとすこやかクラブさんの演技を観る事が出来ず、果たして受賞の可能性があるのかわからない状況での受賞だったので、びっくりしました。
もちろん受賞を狙っていましたが、作品作りに関しては何を意識したわけでもなく、単純に面白いものを作りたいという気持ちでした。専門家や評論家受けの良いものなどもわかりませんし、深くハマる人にはハマるけど万人に受け入れられる作品のつもりではありませんでした。僕は大衆が喜ぶキャッチーやポップなものが個人的にあまり好きではないので、今ここでしか観られないものを作ろうという思いで作っていました。会場が笑ってくれていたのは、舞台上からすごく感じていましたね。
パンチェッタさんは普段ミュージカルをやっていなかったと聞いたのですが今回はどうして取り入れようと・・・?
一宮 『Parsley』は以前、30分公演でやった作品で、その時はミュージカルの部分はありませんでした。一昨年の秋に10分間で4曲の生演奏ミュージカルをやったのですが、その時にミュージカルの面白みを感じました。それからかもしれないです。
でも、もともとミュージカルは好きではなかったです。わからないんです。劇団四季とかミュージカルを好きな人はすごく好きじゃないですか。すごくキラキラして目を輝かせて観ている人がいますけど、僕は「どうした?」って思ってしまうんです。その反応が正常だと思っていましたが、大勢の中で観た時に、そこにはキラキラした目で観ている人達がいて、ちょっと引いてしまいましたね。
僕は突然歌い出すシーンを見ると笑っちゃうんですけど、それを笑うと世間は「え?バカにしているの?」みたいな感じになるのがわからなくて。でも突然歌いだすっておもしろいと思うんです。なので、あえて「笑っちゃうよね?」というミュージカルを提示してみたんです。「笑っていいですよ」っていうミュージカルです。
ミュージカルを作るにあたって参考にしたものってありましたか?
一宮 全部オリジナルですね。作曲を以前もお願いしたことのある加藤亜祐美さんにお願いをしました。この方は歌詞から曲を作ってくれる方なので、先に話を完成させます。曲にしたい部分は言葉の数があうように意識して書いています。彼女はそこからインスピレーションで作曲してくれています。彼女の中にも参考にしているものがあると思うので、曲にもやはりその色がついています。
もともと、パセリの恩返しという作品は、ナレーションに合わせて演者が動くという形の作品だったのですが、ナレーションの言葉で説明的に提示していた部分を歌にして、説明をなくしていく作業をしました。特に何かが好きで参考にした、というのはないですね。話の中のどの部分を歌にするかという点は悩みました。
そこを決めるときはなにを基準に決めていましたか?
一宮 想いが溢れる所は曲になるほうがいいなあとは思いました。Parsleyの2曲目はただ、「お嫁さんにしてください」「誰」、というやり取りしかしていませんが、あえてそこは無駄に使うのもありかなとも思いました。僕は昔話がすごく好きで、今回はツルの恩返しをベースにしてみたんです。子供の頃なんとなく聞いて、なんとなく記憶して、なんの違和感もなく受け入れるという行為への風刺のようなものもありますね。冒頭の歌で、昔話は何故お爺さんから始まるのだろう、というのもある意味そうかもしれません。
ツルの恩返しだと突然娘さんが来て、お嫁さんにして下さいという意味のわからないやりとりが当たり前に行われているんです。何故そうなったのか説明して欲しい部分をあっさり飛ばしているんです。それがもし、ちゃんと対人間のやりとりがなされていたのならどうだったのだろうかと。今あることに難癖をつけたい訳ではありませんが、見る角度を変えるだけで、面白みは何からでも感じ取れると思うんです。視点を変えた方が絶対良いよという事ではなく、変えたら変えたでこういうものの見え方もあるんじゃないですか、というとこですね。
作品を通して伝えたい事はあまりないです。今回もパセリを食べようね、ということを伝えたいのではなく、もしパセリに寄り添ってみたらパセリはこういう事を思っているのかもしれないよという。この劇を観た人が次にパセリを食べるとき「あ、パセリか~」って頭に何かよぎったらいいなぁと思います。なので大衆に受け入れられやすい作品という意識はないですね。まぁ今回の作品は、今までの中ではわかりやすい作品ではあったと思います。
いつもはわかりにくい作品なんですか?
一宮 わかりづらい部分もあります。でも今回は会場のみなさんが感情を開放していてくれたように感じます。初演でParsleyをやった時は、作品として話がループし続けるので、「結局最後どうなったの?」と結構聞かれました。今回は、よく観て感じ取ってくれるお客様がすごく多かったと思いました。
パセリにした理由は?
一宮 作品をつくるときは必ずテーマとタイトルから入ります。
Parsleyの初演は、持ち時間が30分で、複数の団体が呼ばれて一緒に公演をするという企画に参加しました。そこの団体の名前が「パセリス」という団体で、じゃあそこをいじってやるかという思いから、タイトルを「Parsley」にしました。でも何か思う所はあったんだと思います。僕はもともとパセリを食べる人間なので、食べるために出されているのに食べない人いるよな、かわいそうだなぁと思っていて。それが僕の中で就職活動につながりました。50社受けましたとか、就職活動って数がステータスみたいにしている人もいるじゃないですか。選んでもらえるように表面を繕って、一生懸命やって、次へ、みたいな姿に見えたんです。
そもそもなんですけど、なぜ演劇を続けるんでしょうか?
一宮 演劇は好きではないんですよ。だからぜんぜん観に行かないです。インタビューの時にアウトリーチ活動が楽しみだ、という話をしたんですが、僕先生になりたかったんです。小・中・高等学校の体育の免許を持っているんですよ。でも、先生になりたかった理由も漠然としていました。小さい頃、友達に勉強を教えてその子が出来るようになると嬉しくて。親に対してもいい顔して、ある程度選択の余地もあってレールに乗っていました。それでいざ就職活動になった時に、これから40年か、人生一回だけなんだよな、これで終わるな、と考え始めてしまって。子供が主役もいいけど、もう少し自分を輝かせないと駄目だなと。目立つのも好きだったので、周りに勢いで「おれちょっと俳優なるわ」と言って、養成所を受けたら合格して。きっかけはそこですね。
そこからここの演劇につながるんですね
一宮 挫折や妥協、リタイアするのが嫌で、やると決めたからには食えるまでやろう、という目標がありました。納得してそれ以上にやりたい事が出来た時はやめようと思います。
役者に関して言えば、養成所の後に小劇場で役をもらい出演させていただきましたが、そこでお客さんを呼ばないといけないのがなんとなく受け入れづらくて。自分は面白いと感じない作品に出ることもやっぱりあって、そんな時に自分を観て欲しいとか、作品が面白いよ、とも言えなくて。それなら自分が納得できるものを書こうと思って、それがパンチェッタの始まりです。とりあえず自分が書けば、最低でも自分は納得して人は呼べる。その後作り手の喜びは生まれましたね。演出の時だと上演中は客席に座ってそこからお客さんの反応を観られるんです。笑って良いのか駄目なのかを悩んでいる人達の反応を見るのが特に好きです。
昔から演劇をやっていたわけではありませんが、原点は子供の頃からあったのかもしれないです。鬼ごっこの最中とか、その遊びに飽きてきたらジャングルジムの上だけはセーフとか条件をつけていくんです。条件が増える度にまたみんなが盛り上がっていく。それを提案した自分に喜びがあって、「俺、俺、考えたの俺」みたいな気持ちがすごくて。そう考えると新たな案を提示するという部分が、演出とか脚本につながっているような気がするので、こういうのが昔から好きだったのかなとは思いますね。
既存の脚本で演出したりはしないんですか?
一宮 外部から頼まれてそこの団体が書いた脚本を演出したりする事はあります。いつかは古典をやってみたいです。例えば、利賀村のコンクールの課題で読んだ三好十郎の「胎内」。昨年の課題作品にあがっていたのですが、結局「胎内」をやる団体が選ばれていなくて。脳内ですでに面白い形が見えていただけに、とても悔しかったです。
作品は本当に面白くて震えましたね。古い作品で敬遠される場合もあるけど、面白さは絶対あると思うので、それがわかるように提示できたらと思います。あとは別役実さんの作品もやりたいです。一度、外部の団体で、別役さんの作風を意識して60分くらいの長編を書いた事もありました。
喜劇をしていて、喜劇だから、と特別な事はないと思います。コメディの俳優さんは、コミカルな演技をして、笑わせようとしますが、一切その必要はないと思います。ただただそこで生きてくれていれば、自然と観ている人が笑いたくなる、という事だと思います。だから自分の作品では、おかしな人が出てきておかしな振る舞いをして笑われるというよりは、常識が一歩、何かがズレていて、そこを普通に生きているから観ている人達が面白いと感じる。やっぱりそういうのが好きです。
2018年11月26日
【サンデー・マティネ・コンサートvol.205】
<モーツァルト・レクチャー第2弾- 始まりと終わりのモーツァルト->
【出演】
安田 和信(お話)
小平 怜奈(ヴァイオリン)
神谷 悠生(ピアノ)

2年前、vol.166から、かなり時間は開いてしまいましたが、好評だったモーツァルト・レクチャーの第2弾をお届けしました。
今回は「ヴァイオリン・ソナタ」の最初と最後の1曲の聴き比べです。
最初の1曲K.6は、8歳の時の曲。
当時のヴァイオリン・ソナタはむしろピアノが主役で、ヴァイオリンが伴奏的に音を添える形が主流だったそうで、この曲もそのやり方に沿っています。ヴァイオリンなしで演奏しても、曲として成り立ってしまうみたい(驚)
一方、K.526は、ヴァイオリンとピアノが、時に絡み合い、時に支え合い、と、まさに両者で1つの曲を構築している感じ!
実は、本当の最後のヴァイオリンソナタはもう1曲後で、この曲は最後から2番目なのですが、最後の曲はK.6と同じ方法論で書かれているため、今回はあえてK.526を選ばれたそうです。
年齢による進化だけではないこの違い、解説がなければわからない、という方も多いのではないでしょうか。お客さまでも、うなずいていらっしゃる方が多かったです。
安田先生のわかりやすいお話で、レクチャーコンサートならではの楽しみ、味わっていただけた事と思います。モーツァルトはいろんな曲を書いていますから、「最初と最後」シリーズ、まだまだできそうですね。
さて、今回の演奏の小平さんは、6月のまちなかコンサートでご出演いただいたばかり。神谷さんは、第5回せんがわピアノオーディション最優秀賞で昨年ソロリサイタルを開いた方で、せんがわ劇場とゆかりのあるお二人でした。
終演後のインタビューをご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
安田 和信(お話)
小平 怜奈(ヴァイオリン)
神谷 悠生(ピアノ)

2年前、vol.166から、かなり時間は開いてしまいましたが、好評だったモーツァルト・レクチャーの第2弾をお届けしました。
今回は「ヴァイオリン・ソナタ」の最初と最後の1曲の聴き比べです。
最初の1曲K.6は、8歳の時の曲。
当時のヴァイオリン・ソナタはむしろピアノが主役で、ヴァイオリンが伴奏的に音を添える形が主流だったそうで、この曲もそのやり方に沿っています。ヴァイオリンなしで演奏しても、曲として成り立ってしまうみたい(驚)
一方、K.526は、ヴァイオリンとピアノが、時に絡み合い、時に支え合い、と、まさに両者で1つの曲を構築している感じ!
実は、本当の最後のヴァイオリンソナタはもう1曲後で、この曲は最後から2番目なのですが、最後の曲はK.6と同じ方法論で書かれているため、今回はあえてK.526を選ばれたそうです。
年齢による進化だけではないこの違い、解説がなければわからない、という方も多いのではないでしょうか。お客さまでも、うなずいていらっしゃる方が多かったです。
安田先生のわかりやすいお話で、レクチャーコンサートならではの楽しみ、味わっていただけた事と思います。モーツァルトはいろんな曲を書いていますから、「最初と最後」シリーズ、まだまだできそうですね。
さて、今回の演奏の小平さんは、6月のまちなかコンサートでご出演いただいたばかり。神谷さんは、第5回せんがわピアノオーディション最優秀賞で昨年ソロリサイタルを開いた方で、せんがわ劇場とゆかりのあるお二人でした。
終演後のインタビューをご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
2018年11月10日
受賞者インタビュー(3) コトリ会議 山本正典さん(劇作家賞)

あらためましてこのたびは劇作家賞の受賞、おめでとうございます。二週間ほどたちましたが実感のほどはいかがでしょうか。
山本 あまり実感はないですね。初めてこういった賞をもらったので。
今回ご自分の作品が劇作家賞を取った要素って、何だったと思いますか。
山本 今回自分たちの作品がほかの作品よりも、ドラマ的な要素が多かったからではないかなと思います。
脚本のメインになるかと思うんですが、稽古場インタビューの際に地球が滅ぶくらいでないと大切な人のありがたみがわからない。とおっしゃっていたんですが・・・
山本 未来的な話だったり、人類、地球が滅ぶ手前、例えば宇宙人に支配されるとかそういうスケールが大きなことが好きなんです。そういったところから結構影響を受けている部分はあるかもしれないです。今回の「チラ美のスカート」は地球が滅ぶというのがテーマでしたが、これからはもう少し小さなテーマを扱っていきたいと思っています。
もともと大きいことを書こうとは思っていないんですが、ここ2~3年続いていていますね。今は六畳ほどの会話劇をしようかと思っています。
旗揚げ公演は既成台本で行い、2回目以降からは山本さんが作・演出を担当しているとお聞きしましたが、コトリ会議としての活動をはじめる前は執筆活動をされていましたか?
山本 ずっと役者として活動していましたが、一度だけ、別のユニット名で脚本、演出をしました。自身の役者修行の為と思ってやった事だったのですが、その座組みが面白くて、もう一度やろう、というのが、コトリ会議でした。
講評会や感想で、台詞がいいという意見が多かったのですが、こういった台詞はどこから生まれているのでしょうか?
山本 歩いている時、電車に乗っている時、景色の流れている時、ポッと生まれます。
頭の中のような、白目の中のような、舌の付け根のような、どこからと言われたら、それが近いと思います。
テーマなどを決められた状態で、頼まれて台本をかくようなことはありますか?ある場合、どんなところに注意して書かれていますか?ない場合、今後こういった機会があった際、挑戦してみたいと思いますか?
山本 依頼されて書くこと、あります。
注意することは、余計な、思考の殴り書きのようなト書きは控えて、伝わりやすいト書きを書く、です。そして、一つくらい、どうやってこんな表現をすればいいんだ、と悩ませるような台詞、ト書きを書く、です。
表彰式前インタビューで、仙川のコーヒーとラーメンを堪能したということでしたが、今回初めていらっしゃった仙川のイメージはどうでしたか?
山本 脚本家のために作られた街だ、と思いました。
台本を書こうと決めて、1日に4件喫茶店をハシゴする僕にとって、なんだか、馴染む街でした。
どう言ったらいいのか、なんというか、カフェが堂々としていて、良かったです。
■今後の活動予定
・11月には兵庫県で「現代演劇レトロスペクティヴ」に参加。
1960年代以降に発表された、時代を画した現代演劇作品を、関西を中心に活躍する演劇人によって上演し、再検証する企画。『ともだちが来た』『髪をかきあげる』の2本。
・来年2月には福岡で行われる『キビるフェス2019』に参加。
2018年11月05日
受賞者インタビュー(2) ゆうめい 池田亮さん(特別賞)
周りの方の反応はどうでしたか?
池田 みんなおめでとうございますと言ってくれて、すごくうれしかったです。コンクールでは最初、自己紹介をやろうかなと考えていたんです。せんがわ劇場で「ゆうめい」を初めて観る人もいるから、自分たちが今までどういうものをやってきたのかを自己紹介という感じでやろうと思っていたので、そういう意味でも賞をいただけたのはうれしかったです。
出場が決まったときから、自己紹介をテーマにされていたんですね。
池田 最初は、コンクールという、言わばグランプリがあって上下がはっきりするものを経験しとかなきゃいけないっていう気持ちがありました。でも同時にコンクールは、別の団体を好きな人達も観に来てもらえるから、自分たちはこういうのをやっている団体ですって紹介したかった。そういう思いはありました。
今回特別賞でしたけど、それについてはどう思われました?
池田 まず特別賞ってなんだろうと疑問に思いましたけど、賞がもらえたのはうれしかったです。ただ、僕は他の作品もみて各々が特別だったと思っていましたから、その中で自分たちだけが特別賞っていうのがうれしくもあり、同時に僕たちがとってしまっていいのか、でも賞レースだから仕方ないと思ったり。
最近いろんな仕事、それこそバーチャルユーチューバーの仕事や、テレビアニメをやったりすると、演劇でできることなにかなと思っちゃったりすることが、けっこうあるんです。というのも本当にクオリティが高いと思ってて、ユーチューブだったりアニメだったり海外のドラマだったり。自宅にいて生の感覚を目の前で味わわなくてもいいかなと思うくらい、想像力を広げるコンテンツを作ってる人達が沢山いて、そこに自分が負けちゃいそうな危惧がある。だから「演劇ってこういうこともできるし、楽しんでもらえるかもしれません」というのを作って、他のジャンルにめっちゃはまっている人達にも、新しいものを観にきてほしい、楽しんでもらいたいという思いがありました。
もともとは彫刻をされていた、現在もアニメやバーチャルユーチューバーなど多岐にわたって活動を続けていらっしゃる。表現できる部分はそれぞれ違いますか?
池田 そうですね、違いますね。それがおもしろいんですけど、その違い以上に、演劇とユーチューブ、どっちを見るかというと、ユーチューブに傾いちゃう人が多いことを感じます。別に競う必要はないですが。でも演劇を観る人も作る側の想像以上にいろいろなものと既に触れている気がするので、そういうことも考えて作りたいです。
審査員の方々の「公共性」という話を聞くと、いろいろな世代の方々のことをもっと踏まえて、今流行っているものや新しく市民の方々に根付いているコンテンツにも、隅々までアプローチする必要があるんじゃないかと思うんです。だから演劇以外のジャンルを好きな方々にもすごく楽しんでいただける場にしたいです。
池田さんの中ではジャンルに優劣はなく、作品にあうものをその時々で選んでいるんですか?
池田 僕はけっこう雑食系というか、いろいろ楽しめちゃう方だと思うし、いろいろやりたいと思っています。広く深くみたいな。多分いろいろ欲張ってもいます。でもいろいろ楽しめない人もいるので、そういう面へのアプローチをゆうめいではしたいです。
それは観る側の人たちですか?
池田 第一に、観てくれた人達が、観劇後も社会とのつながりとか、いろんなことを想像できる範囲を広げられたりするものを作りたいです。
作品をつくる際、自分の主義主張からスタートするのではなくて、受け手である観客を重点にしているんですね。
池田 何をやるにしろ、そもそも自分が好きでやっていることだし、それに対して、観ている側が、同調や共感をしてくれたら。または、共感はしなくても、日常にいいアプローチができればなという意識で作っています。
稽古場インタビューで池田家以外の人達の在り方にも注目してくださいっておっしゃってましたが、作中でどういった面で意識されていたんでしょうか?
池田 親だから、血がつながっているからといって、お互い分かり合っているわけではないですし、親だけど他人だったりもすると思うんです。親子で出演はしていますけど、実は親子にそこまで重点は置いていなくて、それより、親子でやっているところに他人が入ってくることで、家族の在り方や、他人同士の在り方が変わるっていうのがいいんじゃないかなと思いました。
他人が入ってくることによって中が変わる。作品でははじめから全員が自己紹介でスタートしていたかと思うんですが、その変わるタイミングっていうのはどこらへんだったんでしょうか?
池田 最初、父親と僕だけの親子のやりとりが始まって、ただ他人の生活の話を聞いてるみたいな感じだけど、田中くんと小松くんが入ってくると「これ演劇なの?演劇じゃないの?」みたいな風になる。
田中くんと小松くんは、お客さんが感情移入する役割じゃないにしても、ガイドとなるというか…たとえば、ホラー映画って怖がる役の人がいるからより怖く感じるところがあるように、二人にいてもらうことでそういう見方もできるんじゃないかと。
前回の公演のときはspace not blankの中澤さんが今回の池田さんの役だったと伺いました。そのときと今回って何か違いがありましたか?
池田 作品自体がぜんぜん違いました。今まで自分がやってきたものはどれも違う意識があります。
前回、中澤くんが僕の役をやってくれた時は完全に演出だったから結構構成やストーリーを調整できました。
今回自分でやったのは、もちろん観る人にいろいろ想像してもらうためもありますけど、自分自身も祖父の絵についてすごい考えました。
今回のモチーフは絵です。絵をテーマにした時って、こっちが「この絵はこういうものです」と決めることが中々難しいと思ってて。だからヒントというか想像力が広げられるようなことをやるほうがいいなと。
それは絵に限った事ですか?
池田 絵プラス演劇だったり。むしろ視野を広げるために、今回の絵をモチーフにしたのはあるかもしれないです。
あの絵は特に思い入れがあったんですか?
池田 特にではないです。ほんとに100点くらいあって選べ切れないので。タイトルと年代がかいてあったので、その時何があったのか父に聞きながら、引っ張り出してきた2つです。
ストーリーの基盤はお父さんの体験談なんですね。
池田 あと祖父の体験もです。まず実話で全部ガーっと作って、その見せ方として、ちょっと身体を使ったり、ぐるぐる動かしたりしました。
・体験の当事者がいて、その方と作品を池田さんが介在して作っているんですね。自分の軸と体験者の実話のすりあわせはどのようにされているんでしょうか?
池田 すりあわせのためには、たくさん話して、たくさん取材します。でも一番大事にしてるのは取材によって出来た公演が終わった後の、体験者との関わり合いです。今回は父という本人がでてくれたけど、おじいちゃんという死んじゃった人が出ていないから、それを想像して伝える役割みたいなことをしたかった。演出上としては、死んじゃった人がいて、生きている人がいて、観客に伝える役割として自分たちが存在しているみたいな。演出面というか構成ではそこです。公演後はすぐ墓参りに行きつつ、ずっと公演の反省をしてました。あと絵についても稽古の時よりもっと考えてました。
(演出という俯瞰的にみることのできる立場ではなく役者というポジションになった)今回、自分がでることで苦しさみたいなのはありましたか?
池田 作品が、僕の日常の延長線上で出て来たものなので、あまり自分が役者だという心情になっちゃいけないと思っていました。ちゃんと考えて来たことを伝える姿勢でいるべきだって。
池田さんの話を見聞きしたことを作品に転じるという作り方は、周りの人達の話題が扱いたくなるようなものが多いからなんですか?
池田 創作を始めたきっかけが、インターネットに自分の辛い体験やそれを変換した小説を投稿しまくったことでした。それで酷評でも好評でもレスポンスが返ってくることがとにかく嬉しかった。自分が体験談を話すと、誰かも自分の体験を書いてくれたり。
正直、実名つかって演劇をやるのは、匿名から入った身だと怖くもあります。匿名のほうがたくさん想像できるし、見栄をはらないで出来る点はすごい好きです。毒されてもいるかもしれませんけど。
けっこう意識されます?
池田 観ている人がもし2ちゃんねらーだったら(今は5ちゃんねるですが)、っていうのはすごい意識して作っているかもしれないです。彼らに散々ダメ出しされてきましたから。うん、けっこうありますね、自分の中では。
どのジャンルでやるときもそうなんですか?
池田 どのジャンルでやるときもですが、アニメやユーチューブは顕著に出ます。匿名だからとんでもない悪口と思うようなのもくるけど、けっこう純だなと思うこともある。相手も自分も実名だとどうしてもセーブしちゃう。そのセーブを取っ払うとダメージもでかいし、衝突もすごいあるけど、僕はがそのダメージに若干慣れてきたのもあって何がこようがそれも意見として全部聞こう、みたいな姿勢になっています。
今後の活動内容について教えてください
池田 テレビの脚本だったり映画だったりアニメのDVDについてくる小説だったりがこの先結構いろいろあって、ゴールドシアターの公演もあります。
「ゆうめい」では、来年の三鷹市のある企画に選出されましたので、それが大きな公演になる予定です。2018年はあともう一本、僕が脚本を書いてるのがあります。今年は新作が5本できましたが、来年もいろいろなジャンルを学びながら、ずっと作ってばっかりな感じになると思っています。
2018年11月01日
【サンデー・マティネ・コンサートvol.204】
<モーツァルト「グラン・パルティータ」を聴く>
出演
《クラリネット》
亀井 良信、加藤 優穂
《バセットホルン》
石尾 きらら、菊池 優里
《オーボエ》
大隈 淳幾、山根 優季
《ファゴット》
渡邊 愛梨、河府 有紀
《ホルン》
田中 沙弥、藤野 千鶴、佐藤 千明、秋田 望珠
《コントラバス》
牛島みずき

200回を超えるサンマチの歴史の中でも、初めての試みでした。「グラン・パルティータ」全楽章を聴く!
総勢13名の演奏家による大曲。せんがわ劇場が、心地よい緊張感とモーツァルトの世界に包まれました。
今回は、桐朋学園大学の在学生・卒業生に亀井良信先生が加わった編成。亀井先生は「最近この世代と演奏する機会が少なかったから新鮮」と笑っていらっしゃいました。
終演後の笑顔です!
終演後のインタビューです。 今回は大勢なので、全員にお話を聞くのは残念ながら断念・・・。
代表して、河府有紀さん(ファゴット)、田中沙弥さん(ホルン)、菊池優里さん(バセットホルン)、
亀井良信さん(クラリネット)がお話し下さいました。
どうぞご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
.
出演
《クラリネット》
亀井 良信、加藤 優穂
《バセットホルン》
石尾 きらら、菊池 優里
《オーボエ》
大隈 淳幾、山根 優季
《ファゴット》
渡邊 愛梨、河府 有紀
《ホルン》
田中 沙弥、藤野 千鶴、佐藤 千明、秋田 望珠
《コントラバス》
牛島みずき

200回を超えるサンマチの歴史の中でも、初めての試みでした。「グラン・パルティータ」全楽章を聴く!
総勢13名の演奏家による大曲。せんがわ劇場が、心地よい緊張感とモーツァルトの世界に包まれました。
今回は、桐朋学園大学の在学生・卒業生に亀井良信先生が加わった編成。亀井先生は「最近この世代と演奏する機会が少なかったから新鮮」と笑っていらっしゃいました。
終演後の笑顔です!
終演後のインタビューです。 今回は大勢なので、全員にお話を聞くのは残念ながら断念・・・。
代表して、河府有紀さん(ファゴット)、田中沙弥さん(ホルン)、菊池優里さん(バセットホルン)、
亀井良信さん(クラリネット)がお話し下さいました。
どうぞご覧ください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
.
2018年10月10日
受賞者インタビュー(1) すこやかクラブ うえもとしほさん(演出家賞)
終わってからどうですか?
うえもと 受けてというか参加できてよかったなぁと思ってます。受賞したときは「えっ」ってなったんですけど、みんなからおめでとうって言われて実感しました。うれしいなぁって思いました。
「えっ」てなったのは意外だったということですか?
うえもと 受賞はしないだろうと思ってたんです。講評を聞いて、審査員の方々にも好評だったパンチェッタさんが賞を総なめするかもと考えていたので、驚きでした。
今回の演劇コンクールは2回目の参加でしたが、前回と今回ではすこやかクラブに何か変化はありました?
うえもと (以前参加した)第2回のときは始めたばかりの頃で、右も左もわからずでした。続けていく中で、いつも出てくれる人が増えたり、作品の作り方もなんとなく掴めてきたので、そこは違うかな。それに前回はFC東京というテーマがあったので、ぜんぜん違う感覚で臨みました。
作風自体は変わりましたか?
うえもと 作風自体はたぶんそんなに変わっていないです。台本があって、その台本に沿って作るというよりは、出演者とアイディアを出しながら一緒に考えながらという作り方。ただ、現在は、どのくらいを自分で考えて、どのくらいを人に考えてもらって、という配分が昔よりわかってきたので、そういう意味では成長したのかなと思います。
変革期はありましたか?
うえもと 以前は、何度も出てくれる人はいても、すこやかクラブの「メンバー」というのはなかったんです。でも、2016年からメンバー制をとるようになって、自分に近い場所でサポートしてくれる人が増えました。また、たちかわ創造舎を拠点にするようになって、安定感じゃないですけど、稽古場がいつでもある安心感ができたのは大きいですね。
シェアオフィスメンバーとして、創作の場があることは劇団の活動にも影響していますか?
うえもと 毎年夏に、「真夏のたちかわ怪奇クラブ」というものを開催しているんですね。地元の人に、せっかくここを拠点にするなら、この場所ですこやかクラブに何かしてほしいと言われたのをきっかけに始めて、今3年目なんですけど、去年も来て、今年も楽しみにして来たという方がいてくださるのが楽しいです。また、何が起こるのか、当日までどうなっちゃうのかわからない要素がかなりあるから、いい意味でガチガチにならずに、おおらかに作れるところがいいなと思います。
稽古場インタビューで人生の核となるものを探しているということでしたが、答えは出ましたか?
うえもと 私の核になることはなんだろうと考え続けていて、そこから「遠くへいきたい」というタイトルが浮かんだんですけど、稽古をやっていくうちに人生って絶望的なものなんだと私が思っていることがわかって、それがなんか嫌だったですね。
舞台をみて絶望的な感じは受け取りました。絶望的だけど、結局こうなるよなぁと。
うえもと そうなんです。前から、そういう感覚はあるけど、楽しく生きていきたいという思いも同時にあって、両方で生きてると思ってたんです。でもこの作品を作った時に、自分の暗い部分ばかり見ちゃって、それがすごいストレスでしたね。すごく肌が荒れました。
役者のみなさんはその絶望的な部分というのをどう受け止めて作品におこしていましたか?
うえもと 役者の人たちは特にメンタルに影響は受けていなくて、そういうもんなんだと演じてました。強いですよね。役者のみんなは作品に引きずられてなかったです。この作品、去年5月の本公演のあと、6月に立川で1回だけ上演したんですけど、その日が「巨大化したい」役の男子の結婚式の前日だったもので私がその役をやったんです。それはつらかったですね。体力的にも精神的にもつらくて、なんでこんなことしなきゃいけないんだろうと思いました。
体の動きと心情はどうリンクしていますか?動きでしか、言葉でしか表現できない部分というのはありますか?
うえもと 自分の感覚で、ここは台詞でやる、ここは体でやるというのは、最初に役者に提示して、細かいところ、どんな内容、動きにするかは一緒に稽古しながら決めます。役者から、どうしてもこの体の動きから感情の展開がうまくつながらないと言われると、話し合って変更することもあります。
その話し合いのときは、どんなすり合わせをしていますか?演出家であるうえもとさんと、役者の意見が一致しないようなときとか。
うえもと 自分でも何が言いたかったのかわからなくなって迷う時や、実際その動きをやってみて、確かにしっくりこないと思った時は、どうすればいいか、全員で意見を出しながら作ります。他のパフォーマーが出したアイディアが通ったりもしますし、私が主導するというより、みんなで作っている、みんなで解決していくというのが、すこやかクラブの健全な制作スタイルかなと思います。とはいえ、私が迷宮に入りこむと、地獄になりますけどね。何が正解なのか誰もわからないみたいな感じになって、ずーんってなったりします。
そうなってしまったときはどうするんですか?
うえもと 3月に出た王子の演劇祭時、迷宮に入って地獄の稽古場になったことがありました。その時は、出演者が「俺たちが何とかしないとこれはもうだめだ」となって、みんなで考えて。恐ろしい、恐ろしかったですね。その経験があってみんな心に傷は負いましたけど、いい経験になったというか、いい思い出にはなりました。
今回もともと1時間の作品を40分におさめたということでしたけど、その短縮をするにあたって、そぎ落とされてしまった部分であったり、これだけは絶対に落とせなかったという部分があれば教えてください。
うえもと やっぱりこれは60分の作品だったなと思いながら作っていて、けっこう苦労しました。すごく大切だと思っていたシーンを削って、それはそれで作品としては成立したとは思います。でも審査員の方々の感想を聞いて、やっぱり私がそぎ落としたあのシーンがとても大切だったんだと、後ですごく感じました。作る前は、短縮バージョンにするのはそんなに難しくないだろうと思っていたけど、あの作品はあの長さだからよかったんだという発見もあって、とても勉強になりました。
ちなみにそのシーンってどこですか?
うえもと 子供の頃の思い出を言うというシーンです。「遠くへいきたい」という作品は、たどり着けないけれどそれを求めてしまう希望と絶望が主軸になっているんです。審査員の方々が「わからないけど、どこか遠くに連れて行かれたという感覚になりたかった」みたいなことをおっしゃっていたと思うんですけど、確かに、この40分の作品はちょっときれいにまとめすぎていたのかな。あのシーンがあったら、よくわからないけどわかる、みたいな感覚にいけたのかもしれません。だから、削るとしても、あのシーンに代わる何かを入れられたらよかったと思いました。
「遠くへいきたい」の遠くは時間的な面、とくに過去への憧憬のようなものを感じたんですが、うえもとさんの言うところの遠くは?
うえもと 私の「遠く」はやっぱり、子供の頃ですね。過去が一番大きいです。・・・死ぬの怖いじゃないですか?時間が過ぎていってみんないつか死んじゃうんだって。そんなこと考えずに生きていけたらいいんですけど、考えちゃうでも、いつ死んでも、みたいなことを考えておくのは人生の指針になりますね、それから、人生に何かよりどころがあるとしたら、、私は自分の感覚をよりどころにして生きたいです。長く生きて来た人の言葉はたしかに説得力があるけど、その人はその人の人生しか生きていないんだし、素直な心で受け入れつつ、自分の感覚をよりどころにして生きていくのが大事なのかなと思いますね。
話がずいぶん広がりました。さて今後の活動予定は?
うえもと 11月24日、25日に、八王子禅東院というお寺で、馬喰町バンドと一緒に公演をやります。今から馬喰町バンドのリーダーの武さんに曲を作ってもらっていて、それを聞いてから作品をどうするか決めます。このお寺はこれまでにもいろんな音楽イベントを開催していて、すごくいい場所です。
今後の方向性はきまっていますか?
うえもと すこやかクラブとしては「真夏のたちかわ怪奇クラブ」が大切なイベントになりつつあるので、これを発展というか、今後も続けていきたいと思います。もちろん作品を作り続けていきますが、すごくたくさんの人じゃなくても、まだすこやかクラブのことを知らない人たちに知ってもらって、すこやかクラブの作品を好きになってほしい。すこやかクラブというのは、自分が幸せに生きていくためのひとつのかたちではありますね。うん、幸せに生きていきたい。
2018年09月24日
【サンデー・マティネ・コンサート】vol.203<アンデスの調べ>
<世界の楽器シリーズ ~アンデスの調べ~ >
【出演】
ウィニャイ Wiňay(アンデス民族音楽)
JAVIER CUELLAR(チャランゴ)
JUAN OJEDA(ギター)
LUIS OKAZAKI(チャスチャス)
NICOLAS CUELLAR(ケーナ、サンポーニャ)
哀愁溢れるメロディもあれば、会場中が手拍子で一体となる曲もあって、大好評でした!
写真はウィニャイの皆さん、左からハビエルさん、ルイスさん、ニコラスさん、ホワンさんです♪

終演後のインタビューです。
コンサートの余韻が残る中、お話を伺いました!
ウィニャイの皆さん明るく陽気で、撮影しているこちらも笑顔に。
でもカメラがガクガク揺れているのは笑っているのではなく単なる手ブレ。
申し訳ありません…
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
ウィニャイ Wiňay(アンデス民族音楽)
JAVIER CUELLAR(チャランゴ)
JUAN OJEDA(ギター)
LUIS OKAZAKI(チャスチャス)
NICOLAS CUELLAR(ケーナ、サンポーニャ)
哀愁溢れるメロディもあれば、会場中が手拍子で一体となる曲もあって、大好評でした!
写真はウィニャイの皆さん、左からハビエルさん、ルイスさん、ニコラスさん、ホワンさんです♪

終演後のインタビューです。
コンサートの余韻が残る中、お話を伺いました!
ウィニャイの皆さん明るく陽気で、撮影しているこちらも笑顔に。
でもカメラがガクガク揺れているのは笑っているのではなく単なる手ブレ。
申し訳ありません…
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
2018年08月10日
演劇コンクール 上演後の感想を聞きました
演劇コンクールが終わって約1ヶ月が経ちました。ただいま、表彰式での専門審査員の講評、受賞者インタビューをアップするべく準備中ですが、その前に、上演を終えた後の、全団体の感想などをお届けしたいと思います。
表彰式の直前、というタイミングで、団体控室にて行ったインタビューです。どうぞご覧ください。
【コトリ会議】

上演順がトップバッターでしたが、いかがでしたか?
原竹志(キャスト)
大変緊張しました。が、終演後の時間に余裕があり、他の団体の作品も観られましたので良かったです。
(制作の)若旦那さんは、他の団体の当日受付も手がけていましたね。
若旦那家康(制作)
6団体が色々な地域から来ているのが刺激になり、バラエティに富んでいて面白かったです。お手伝いを通じて出会いもあり、楽しかったです。
コトリ会議さんは、せんがわ劇場に足を踏み入れるのは初めてですよね。
山本正典(作・演出)
仙川の街も初めてで、街自体がすごいと思いました。トップバッターだったので、街の食べ歩きも楽しむ時間がありました。コーヒーとラーメンに行きまくりました。
苦労したところはどんなところですか?
山本正典(作・演出)
初めての劇場だったので、客席と舞台の関係や、距離感を測るのが大変でした。こんなに広い劇場での経験はあまりないのですが、声の響きが良く、ストレスなくやれたので、すごい劇場だと思いました。
小さい声で囁く場面が多く、他の同じくらいの規模の劇場だと、マイクを使ったり、声がこもって聞き取りにくかったりするのですが、ここはそんなにマイクも使わなくても声を張らなくても聞き取れて、音のめぐりが良かったです。
劇場や街を気に入っていただけて良かったです。どうもありがとうございました。
【ブルーエゴナク】

今回の参加団体で一番遠方の、北九州からの参加でしたね。最後の大事な稽古の詰めのところで大雨の影響を受け、稽古ができなくなってしまったというご相談もいただきましたが、実際どうでしたか?
穴迫信一(作・演出)
大雨の影響で2日くらい稽古がつぶれました。稽古が切羽詰っていたところだったので久々に追い込まれました。飛行機に乗る気にもなれませんでしたが、東京にきてからこちらで稽古場を借りられると分かってからは少し余裕が出ました。
今回の作品はまったくの新作ではなく、ベースの作品があったとはいえ、かなり手を入れたということですが、どうでしたか?
穴迫信一(作・演出)
実は一番大事なところをカットしたんです。
・・・?というと?
穴迫信一(作・演出)
何故かというと、初演からの時間の中で、たった5ヶ月ですけど、その部分が僕の中で切実なテーマじゃなくなっていたんです。だからその設定を残すことは自分にとって嘘になると感じて、あえて抜きました。ただ、それは作品を一番支える部分ではあったので、結果的に大手術となってしまいました。
ですから、初演と両方観た方と、今回初めての方では、印象が違うと思います。初めて観た方がどのように感じたのかは想像がつかないです。コンクールの結果がどうなるかも、まったくわからないです。
コンクールなので、何かしら結果はでますけれど、新しいお客様がブルーエゴナクさんを知ったことは確かですよね。
穴迫信一(作・演出)
はい。他の団体に協力してもらったり、また自分が手伝ったり、新しい出会いもあったので、参加してよかったです。
そう言っていただけて良かったです。ありがとうございました。
【ゆうめい】

ゆうめいさんは、「CoRich舞台芸術まつり!2018春」でも準グランプリを受賞なさったばかりで、今回のコンクールに向けて自信や勢いがあったのではないでしょうか?
池田亮(作・演出・出演)
自信はそこまでなかったです。劇場のスタッフの方々や、色々な方々からの助けがあって完成したので、自分がそこまで演出したという感じではまったくないです。皆さんのおかげだと思います。みんなが創った小さい作品を1つにまとめた感じです。
勢いというよりはちゃんとやらないといけないし、観に来てくれる人に楽しんで貰おうと思ってつくりました。
このコンクールは、6団体が2日間で短編作品を次々と上演するというタイトスケジュールですが、そのあたりはいかがでしたか?
河井朗(舞台監督)
テクリハで初めて会場を使ってみて、変更したところもありましたし、本番はお客様がいてまた違いましたね。ゲネでは沢山の人に観てもらえて、本番に近い感じでやれたんですけど。(通してできる機会は)3回しかないですから。
池田亮(作・演出・出演)
色々な団体が1ヶ所でやるのは面白かったし、他の団体の作品も楽しかったです。単純に観劇する立場としても、満足できたと思います。全部観劇したお客さまも楽しかったんじゃないかな。
色んなものが飾られている、美術館みたいに感じました。自分達が絵を展示していたことも関係しているかもしれませんが・・・舞台とか美術とかの垣根を越えたコンクールになったのではと思います。
面白い感想をいただきました。どうもありがとうございました。
【すこやかクラブ】

すこやかクラブさんは今回2回目の出場ですが、前回とは違うメンバーということですね。参加してみていかがでしたか?
うえもとしほ(作・演出)
スタッフの方々が手厚く対処してくれて嬉しかったです。
以前、ご自分達の公演でせんがわ劇場を利用していただいたこともあるので、ある程度劇場の使い勝手を把握した上で、作品創りに取り組めたのでは?
うえもとしほ(作・演出)
今回は昨年5月に上演した作品の再演だったので、せんがわ劇場をイメージしたというよりは、その作品を規定の時間内にどうまとめあげるかを意識して創りました。
時間というのが意識の中で大きかったですか?
うえもとしほ(作・演出)
大きかったです。もともと62分くらいの作品だったので、それを短くすると、やはり違う作品になってしまい、どうやって成立させるかを重点的に考えながらやりました。
出演者の皆さんは、40分バージョンをどう感じていましたか?スムーズに入っていけたのでしょうか?
向原徹(出演)
全然スムーズではなかったです。どのシーンも大事で、切るのはもったいないという意識がありました。もともと1時間かけて積み上げていくところを、35分でピークに持っていくのは、最初は違和感がありました。稽古と話し合いを重ねていくうちにクリアできた、というのが実感です。
単なる短縮ではなく、大切なところを残して凝縮していくということでしょうか。
うえもとしほ(作・演出)
その通りです!
40分バージョンの完成に行きつくことはできたという事ですね。悔いなく上演もできましたか?
うえもとしほ(作・演出)
悔いはないです!
うえもとさんとお話しているとこちらも元気が出ますね。どうもありがとうございました。
【パンチェッタ】

今回は限られた時間でリハーサル、本番というタイトスケジュールでしたが、いかがでしたか?大変だったところはどんなところでしたか?
一宮周平(作・演出・出演)
音響の竹下さんが一番大変だったと思います。マイクもありましたし、音響機材も多かったので。
普段から歌は多いのですか?
一宮周平(作・演出・出演)
ほとんど経験ないです。今回が2回目です。
出演者の皆さんは、今回こんなに歌が多いというのはいつ頃知ったのですか?
セキュリティ木村(出演)
稽古が始まってからです。
瞳(出演)
ちょっと歌があるっていう話だったのに。
一宮周平(作・演出・出演)
たった1回の公演のために曲を書き下ろしてもらって。
瞳(出演)
歌を作ってくれた人にも一度来ていただいて、あたたかく指導してもらいました。
パンチェッタさんとしては、今後もこの方向性はあるのですか?
一宮周平(作・演出・出演)
実はミュージカルは好きじゃないんです。笑うところは笑って欲しいので、笑っていいミュージカルを作りたくてあえてやっています。
かなり笑いも出ていましたね。そのあたりはやり切った感はありますか?
一宮周平(作・演出・出演)
やり切れたと思います。スタッフさんからも本番が一番良かったと言っていただけました。
セキュリティ木村(出演)
お祭りみたいな感じであっという間でした。
いろいろ意外なお答えもありました。どうもありがとうございました。
【N2】

一番大切な稽古の最後の詰めの時期に、地震や豪雨などが起こって、その影響もあったと思いますが、作品創りで一番大変だったところや苦労したところを教えてください。
杉本奈月(作・演出)
私自身が住んでいる大阪北部で地震があったのも含め、京都へ稽古に行くのに電車が走っていなかったり、気にしないようにしつつも、どこか不安に侵されていく感じは否めませんでした。彼女も私も、俳優と演出である以前に生活をともにする家族と身内がいる。現実として向きあわざるをえない非常と日常に今、何を上演とするべきかを考えました。
前田愛美(出演)
稽古に入れない時期もあって、稽古にならなかった日もあります。どうして役者をやっているのだろうと疑問に思う時もありました。
一人芝居というのは、今までにもやったことはあるのですか?
杉本奈月(作・演出)
戯曲は何本か書いてきましたが、演出としてかかわったのは1回だけです。俳優不在の上演をした際に、出演者ではないけれどスタッフとして私が舞台に立っていました。俳優と一人芝居をつくったのは今回が初めてです。
コンクールという、最後に評価が出される場所での一人芝居に、プレッシャーはありませんでしたか?
前田愛美(出演)
一人芝居自体にプレッシャーはありませんでした。
杉本奈月(作・演出)
いつもは劇作家として劇場と出演者へ宛て書く戯曲がメインとなりますが、一人でも作品を創作している俳優でプレイヤーでありながらクリエーターでもある彼女がいいと考え、今回は「語り」から立ちあげられる上演を試みました。12歳から演劇をつづけてきて、書ける人に書いてもらった台詞がなくとも創作と上演ができる場を求めている人たちもいる……という現実を知っているからです。
前田愛美(出演)
でも、できないところはできないな……と感じるところもありますね。
準備した事はすべて出し切れましたか?
前田愛美(出演)
できなかったこともありましたが、稽古でつくったものを出したいという思いはありました。
それは伝わっていたのではと思います。ありがとうございました。
せんがわ劇場演劇コンクール詳細は→ここをクリック!
表彰式の直前、というタイミングで、団体控室にて行ったインタビューです。どうぞご覧ください。
【コトリ会議】
上演順がトップバッターでしたが、いかがでしたか?
原竹志(キャスト)
大変緊張しました。が、終演後の時間に余裕があり、他の団体の作品も観られましたので良かったです。
(制作の)若旦那さんは、他の団体の当日受付も手がけていましたね。
若旦那家康(制作)
6団体が色々な地域から来ているのが刺激になり、バラエティに富んでいて面白かったです。お手伝いを通じて出会いもあり、楽しかったです。
コトリ会議さんは、せんがわ劇場に足を踏み入れるのは初めてですよね。
山本正典(作・演出)
仙川の街も初めてで、街自体がすごいと思いました。トップバッターだったので、街の食べ歩きも楽しむ時間がありました。コーヒーとラーメンに行きまくりました。
苦労したところはどんなところですか?
山本正典(作・演出)
初めての劇場だったので、客席と舞台の関係や、距離感を測るのが大変でした。こんなに広い劇場での経験はあまりないのですが、声の響きが良く、ストレスなくやれたので、すごい劇場だと思いました。
小さい声で囁く場面が多く、他の同じくらいの規模の劇場だと、マイクを使ったり、声がこもって聞き取りにくかったりするのですが、ここはそんなにマイクも使わなくても声を張らなくても聞き取れて、音のめぐりが良かったです。
劇場や街を気に入っていただけて良かったです。どうもありがとうございました。
【ブルーエゴナク】

今回の参加団体で一番遠方の、北九州からの参加でしたね。最後の大事な稽古の詰めのところで大雨の影響を受け、稽古ができなくなってしまったというご相談もいただきましたが、実際どうでしたか?
穴迫信一(作・演出)
大雨の影響で2日くらい稽古がつぶれました。稽古が切羽詰っていたところだったので久々に追い込まれました。飛行機に乗る気にもなれませんでしたが、東京にきてからこちらで稽古場を借りられると分かってからは少し余裕が出ました。
今回の作品はまったくの新作ではなく、ベースの作品があったとはいえ、かなり手を入れたということですが、どうでしたか?
穴迫信一(作・演出)
実は一番大事なところをカットしたんです。
・・・?というと?
穴迫信一(作・演出)
何故かというと、初演からの時間の中で、たった5ヶ月ですけど、その部分が僕の中で切実なテーマじゃなくなっていたんです。だからその設定を残すことは自分にとって嘘になると感じて、あえて抜きました。ただ、それは作品を一番支える部分ではあったので、結果的に大手術となってしまいました。
ですから、初演と両方観た方と、今回初めての方では、印象が違うと思います。初めて観た方がどのように感じたのかは想像がつかないです。コンクールの結果がどうなるかも、まったくわからないです。
コンクールなので、何かしら結果はでますけれど、新しいお客様がブルーエゴナクさんを知ったことは確かですよね。
穴迫信一(作・演出)
はい。他の団体に協力してもらったり、また自分が手伝ったり、新しい出会いもあったので、参加してよかったです。
そう言っていただけて良かったです。ありがとうございました。
【ゆうめい】
ゆうめいさんは、「CoRich舞台芸術まつり!2018春」でも準グランプリを受賞なさったばかりで、今回のコンクールに向けて自信や勢いがあったのではないでしょうか?
池田亮(作・演出・出演)
自信はそこまでなかったです。劇場のスタッフの方々や、色々な方々からの助けがあって完成したので、自分がそこまで演出したという感じではまったくないです。皆さんのおかげだと思います。みんなが創った小さい作品を1つにまとめた感じです。
勢いというよりはちゃんとやらないといけないし、観に来てくれる人に楽しんで貰おうと思ってつくりました。
このコンクールは、6団体が2日間で短編作品を次々と上演するというタイトスケジュールですが、そのあたりはいかがでしたか?
河井朗(舞台監督)
テクリハで初めて会場を使ってみて、変更したところもありましたし、本番はお客様がいてまた違いましたね。ゲネでは沢山の人に観てもらえて、本番に近い感じでやれたんですけど。(通してできる機会は)3回しかないですから。
池田亮(作・演出・出演)
色々な団体が1ヶ所でやるのは面白かったし、他の団体の作品も楽しかったです。単純に観劇する立場としても、満足できたと思います。全部観劇したお客さまも楽しかったんじゃないかな。
色んなものが飾られている、美術館みたいに感じました。自分達が絵を展示していたことも関係しているかもしれませんが・・・舞台とか美術とかの垣根を越えたコンクールになったのではと思います。
面白い感想をいただきました。どうもありがとうございました。
【すこやかクラブ】

すこやかクラブさんは今回2回目の出場ですが、前回とは違うメンバーということですね。参加してみていかがでしたか?
うえもとしほ(作・演出)
スタッフの方々が手厚く対処してくれて嬉しかったです。
以前、ご自分達の公演でせんがわ劇場を利用していただいたこともあるので、ある程度劇場の使い勝手を把握した上で、作品創りに取り組めたのでは?
うえもとしほ(作・演出)
今回は昨年5月に上演した作品の再演だったので、せんがわ劇場をイメージしたというよりは、その作品を規定の時間内にどうまとめあげるかを意識して創りました。
時間というのが意識の中で大きかったですか?
うえもとしほ(作・演出)
大きかったです。もともと62分くらいの作品だったので、それを短くすると、やはり違う作品になってしまい、どうやって成立させるかを重点的に考えながらやりました。
出演者の皆さんは、40分バージョンをどう感じていましたか?スムーズに入っていけたのでしょうか?
向原徹(出演)
全然スムーズではなかったです。どのシーンも大事で、切るのはもったいないという意識がありました。もともと1時間かけて積み上げていくところを、35分でピークに持っていくのは、最初は違和感がありました。稽古と話し合いを重ねていくうちにクリアできた、というのが実感です。
単なる短縮ではなく、大切なところを残して凝縮していくということでしょうか。
うえもとしほ(作・演出)
その通りです!
40分バージョンの完成に行きつくことはできたという事ですね。悔いなく上演もできましたか?
うえもとしほ(作・演出)
悔いはないです!
うえもとさんとお話しているとこちらも元気が出ますね。どうもありがとうございました。
【パンチェッタ】

今回は限られた時間でリハーサル、本番というタイトスケジュールでしたが、いかがでしたか?大変だったところはどんなところでしたか?
一宮周平(作・演出・出演)
音響の竹下さんが一番大変だったと思います。マイクもありましたし、音響機材も多かったので。
普段から歌は多いのですか?
一宮周平(作・演出・出演)
ほとんど経験ないです。今回が2回目です。
出演者の皆さんは、今回こんなに歌が多いというのはいつ頃知ったのですか?
セキュリティ木村(出演)
稽古が始まってからです。
瞳(出演)
ちょっと歌があるっていう話だったのに。
一宮周平(作・演出・出演)
たった1回の公演のために曲を書き下ろしてもらって。
瞳(出演)
歌を作ってくれた人にも一度来ていただいて、あたたかく指導してもらいました。
パンチェッタさんとしては、今後もこの方向性はあるのですか?
一宮周平(作・演出・出演)
実はミュージカルは好きじゃないんです。笑うところは笑って欲しいので、笑っていいミュージカルを作りたくてあえてやっています。
かなり笑いも出ていましたね。そのあたりはやり切った感はありますか?
一宮周平(作・演出・出演)
やり切れたと思います。スタッフさんからも本番が一番良かったと言っていただけました。
セキュリティ木村(出演)
お祭りみたいな感じであっという間でした。
いろいろ意外なお答えもありました。どうもありがとうございました。
【N2】

一番大切な稽古の最後の詰めの時期に、地震や豪雨などが起こって、その影響もあったと思いますが、作品創りで一番大変だったところや苦労したところを教えてください。
杉本奈月(作・演出)
私自身が住んでいる大阪北部で地震があったのも含め、京都へ稽古に行くのに電車が走っていなかったり、気にしないようにしつつも、どこか不安に侵されていく感じは否めませんでした。彼女も私も、俳優と演出である以前に生活をともにする家族と身内がいる。現実として向きあわざるをえない非常と日常に今、何を上演とするべきかを考えました。
前田愛美(出演)
稽古に入れない時期もあって、稽古にならなかった日もあります。どうして役者をやっているのだろうと疑問に思う時もありました。
一人芝居というのは、今までにもやったことはあるのですか?
杉本奈月(作・演出)
戯曲は何本か書いてきましたが、演出としてかかわったのは1回だけです。俳優不在の上演をした際に、出演者ではないけれどスタッフとして私が舞台に立っていました。俳優と一人芝居をつくったのは今回が初めてです。
コンクールという、最後に評価が出される場所での一人芝居に、プレッシャーはありませんでしたか?
前田愛美(出演)
一人芝居自体にプレッシャーはありませんでした。
杉本奈月(作・演出)
いつもは劇作家として劇場と出演者へ宛て書く戯曲がメインとなりますが、一人でも作品を創作している俳優でプレイヤーでありながらクリエーターでもある彼女がいいと考え、今回は「語り」から立ちあげられる上演を試みました。12歳から演劇をつづけてきて、書ける人に書いてもらった台詞がなくとも創作と上演ができる場を求めている人たちもいる……という現実を知っているからです。
前田愛美(出演)
でも、できないところはできないな……と感じるところもありますね。
準備した事はすべて出し切れましたか?
前田愛美(出演)
できなかったこともありましたが、稽古でつくったものを出したいという思いはありました。
それは伝わっていたのではと思います。ありがとうございました。
せんがわ劇場演劇コンクール詳細は→ここをクリック!
2018年08月06日
【サンデー・マティネ・コンサートvol.201】
<シャンソン・フランセーズ~ クラシック歌手による シャンソン・ショウ シャンソニエにようこそ ~>

【出演】
田辺いづみ(メゾ・ソプラノ)
和田ひでき(バリトン)
田中 知子(ピアノ)
厳しい暑さをさらりとかわすような、洒落たシャンソンをお楽しみいただきました!
いくつものシャンソニエ(シャンソン専門のライブハウス)が愛されてきたことでもわかるように、
日本に根付いているシャンソン。
意識して聴いたことのない方でも、CMなどでいつの間にか親しんでいたり、学校の音楽の時間に歌ったこともあるかもしれません。
舞台上には深紅の薔薇が一輪飾られ、雰囲気も満点の中、日本語とフランス語をとりまぜてお聴きいただきました。
アンコールの「オー・シャンゼリゼ」は客席も巻き込んでの合唱。
劇場を出るお客さまの足どりも、心なしか軽かったような……
終演後のひとことインタビューも、いつもとちょっと違う感じ?どうぞお楽しみください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
【出演】
田辺いづみ(メゾ・ソプラノ)
和田ひでき(バリトン)
田中 知子(ピアノ)
厳しい暑さをさらりとかわすような、洒落たシャンソンをお楽しみいただきました!
いくつものシャンソニエ(シャンソン専門のライブハウス)が愛されてきたことでもわかるように、
日本に根付いているシャンソン。
意識して聴いたことのない方でも、CMなどでいつの間にか親しんでいたり、学校の音楽の時間に歌ったこともあるかもしれません。
舞台上には深紅の薔薇が一輪飾られ、雰囲気も満点の中、日本語とフランス語をとりまぜてお聴きいただきました。
アンコールの「オー・シャンゼリゼ」は客席も巻き込んでの合唱。
劇場を出るお客さまの足どりも、心なしか軽かったような……
終演後のひとことインタビューも、いつもとちょっと違う感じ?どうぞお楽しみください!
公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
2018年08月06日
【サンデー・マティネ・コンサートvol.200】
<200回記念コンサート>
出演:200回記念合唱団、松井康司(指揮)、永井幸恵(ピアノ)
ブログに上げるのが遅くなってしまいましたが……
7月22日、ついにサンデー・マティネ・コンサートが200回を迎えました!
200回目は、100回と同様、コンサートを楽しみ、見守ってくださった市民の皆さまとお祝いしたいということで、
4月に公募した、市民合唱団の出演でした。
小学生のお子さんから、人生のベテランの方まで、約40名が初めて顔を合わせたのは5月20日。
それから5回の練習で、本番を迎えました。
初日から驚いたのは皆さんの実力の高さ!経験不問で募集したにもかかわらず、
指導の松井先生の指示をあっという間に理解し、パート別のメロディも難なくこなしてしまうのには本当にびっくりしました。
あまりにすんなりできてしまうので、何と、途中から曲数が増えたくらいです。
当日は、途中で200回を振り返るコーナーが設けられ、音楽コーディネーターの松井先生、合田先生と共に、
過去のコンサートの想い出を語りました。
懐かしい画像が出てくるとあれもこれもお話したくなり、
ちょっぴり時間オーバーになったのはご愛嬌……ということでご勘弁ください。
合唱の方はというと、最初は少し緊張気味?な雰囲気もうかがえましたが、
後半に進むにつれどんどん調子が上がり、本当に素晴らしい歌声でした!
最後の曲「ふるさと」は、客席の皆さまにもご参加いただいて、ホール中を包み込む全員合唱となりました。
「ジャンルにとらわれず上質な音楽」を「年齢に関わらず幅広いお客さま」にお贈りすることを目指したサンデー・マティネ・コンサートが、
こうして200回を迎えられたのは、すべての演奏家、スタッフ、そして何より、お客さまのおかげです。
改めて、深く感謝申し上げます。
せんがわ劇場が大切にお届けしているコンサートを、どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。



公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック
出演:200回記念合唱団、松井康司(指揮)、永井幸恵(ピアノ)
ブログに上げるのが遅くなってしまいましたが……
7月22日、ついにサンデー・マティネ・コンサートが200回を迎えました!
200回目は、100回と同様、コンサートを楽しみ、見守ってくださった市民の皆さまとお祝いしたいということで、
4月に公募した、市民合唱団の出演でした。
小学生のお子さんから、人生のベテランの方まで、約40名が初めて顔を合わせたのは5月20日。
それから5回の練習で、本番を迎えました。
初日から驚いたのは皆さんの実力の高さ!経験不問で募集したにもかかわらず、
指導の松井先生の指示をあっという間に理解し、パート別のメロディも難なくこなしてしまうのには本当にびっくりしました。
あまりにすんなりできてしまうので、何と、途中から曲数が増えたくらいです。
当日は、途中で200回を振り返るコーナーが設けられ、音楽コーディネーターの松井先生、合田先生と共に、
過去のコンサートの想い出を語りました。
懐かしい画像が出てくるとあれもこれもお話したくなり、
ちょっぴり時間オーバーになったのはご愛嬌……ということでご勘弁ください。
合唱の方はというと、最初は少し緊張気味?な雰囲気もうかがえましたが、
後半に進むにつれどんどん調子が上がり、本当に素晴らしい歌声でした!
最後の曲「ふるさと」は、客席の皆さまにもご参加いただいて、ホール中を包み込む全員合唱となりました。
「ジャンルにとらわれず上質な音楽」を「年齢に関わらず幅広いお客さま」にお贈りすることを目指したサンデー・マティネ・コンサートが、
こうして200回を迎えられたのは、すべての演奏家、スタッフ、そして何より、お客さまのおかげです。
改めて、深く感謝申し上げます。
せんがわ劇場が大切にお届けしているコンサートを、どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。



公演詳細ページはこちらからどうぞ→ここをクリック