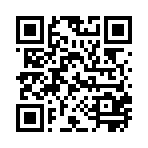2016年09月01日
第7回せんがわ劇場演劇コンクール 専門審査員講評(2) 「演劇活性化団体uni」

写真撮影:Koji Ota
※掲載の文章は、第7回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際、専門審査員から各劇団にむけて語られた講評を採録したものです。
劇団によって審査員の順番が違っていますが、当日の状況を再現しています。どうぞご了承ください。
■徳永京子
農耕演劇って書いてあるんですけど、農業の成り立ちを描きたかったわけではないですよね。おそらく、ある集団の発生、継続、分裂、新しい始まりなどを、ああいう形を借りて作りたかったのではないかと思います。
けれど私がちょっとわからなかったのは、「自分たちが育てたもの以外は食べてはいけない、摂取してはいけない」という厳密なルールが作品の中にあるんですが、脚本の5ページ目に、移動してきた場所にあった実を仲間同士で手渡しているシーンがありました。私はあれを、自分たちが育てた実ではないものを「食べた」と理解しました。また、櫓があるところに彼らが来るというのも、最初の設定がよくわかりませんでした。
物語の中に厳密なルールを敷いていますが、厳密なところと緩いところが混ざっていて、ちょっと損だと思いました。
一番気になったのはラストのセリフです。残る人と出ていく人がいるのはいいんですけれども、残る人が死んだ仲間をさして「みんなもそうしたと思う」と言いますよね。「みんなもそうしたと思う」という気持ちで新しいことを選んでいいのか。
同じ結果を選ぶにしても、もっと積極的に考えて、それを経て出した新しい答えが「残る」という選択だったらいいんですけれど、「みんなもそうしたと思う」という考え方での「残る」という選択は、大げさな言い方をすれば、政治のことが今これだけ意識的になっている時に、ちょっと寂しいことだと思います。
■菊池准
僕も同じような印象です。
彼らの主張や行動の核になる部分―親や他の誰かからもたらされた「教え」、あるいは「伝統」に縛られながら、それを軸にして生きて行くという初期設定が非常に不明確だったと思います。ただ「教え」ということになってしまっていて、それにみんなが縛られているという戯曲上の幹になる部分が、非常に曖昧な設定になっているんじゃないか、というのが気になります。だからいろいろなところに矛盾が生まれてくる。
例えば、こうした(「教えに従う」という)物語を今やる場合、世界的に起こっていることを考えても、個人の意思が実は個人の意志ではなく、いわゆる教訓とか徹底されたステレオタイプな何かによって支配されてしまっているということ自体がすごく危険な印象を与えてしまって、皆さんのやろうとしているメッセージと全く真逆なメッセージが伝わってしまう危険性がある。
その辺の突き詰めをはっきりしていないと、観客をどこに導こうとしているのか、自分たちがどこへ行こうとしているのかが見えてこない。
ただ演劇的に言うと、自然体な演技で会話もすごくナチュラルでとても良かったです。
けれど状況に対して何も変わっていかない。状況の捉え方やみんなの創り方の根幹ができていないから、状況が変わっていかないし、常に同じリズムでしかないのではないでしょうか。そこは直したほうがいいと思います。
■伊藤キム
例えが正しいかどうかわかりませんが、子供向けの啓発ドラマを見ているような感じがしました。
全てがわかりやすく進んでいて、とても予定調和なんですね。ぜんぜん裏切りがなくて新鮮味がなかったです。どういう事をされようとしているのか、メッセージみたいなものがあると思うんですが、演劇でどういうメッセージを発信していくんだろうということを、観ながらいろいろ考えさせられました。
■天野眞由美
私はとても好きでした。この芝居はとても穏やかで、内容もやってる方もみんな穏やかな感じで、私は好きでした。
出だしの会話はテンポよく、タッタッタッといったんですが、途中からダレてきましたね。それは先ほどおっしゃっていたような、設定の甘さというか 認識の甘さが影響したのかも知れません。
ただ、種を蒔く、水をかける、そういう動作はとてもきれいでした。穏やかさがこのチームの素敵なところだと思うんですが、もう一つ勢いというか強さというか、それがあったら良いなというふうに思いました。
※以上の文章は、第7回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際、専門審査員から各劇団にむけて語られた講評を採録したものです。
劇団によって審査員の順番が違っていますが、当日の状況を再現しています。どうぞご了承ください。
「演劇活性化団体uni」の公演詳細ページはこちら
第7回せんがわ劇場演劇コンクール全体ページはこちら
農耕演劇って書いてあるんですけど、農業の成り立ちを描きたかったわけではないですよね。おそらく、ある集団の発生、継続、分裂、新しい始まりなどを、ああいう形を借りて作りたかったのではないかと思います。
けれど私がちょっとわからなかったのは、「自分たちが育てたもの以外は食べてはいけない、摂取してはいけない」という厳密なルールが作品の中にあるんですが、脚本の5ページ目に、移動してきた場所にあった実を仲間同士で手渡しているシーンがありました。私はあれを、自分たちが育てた実ではないものを「食べた」と理解しました。また、櫓があるところに彼らが来るというのも、最初の設定がよくわかりませんでした。
物語の中に厳密なルールを敷いていますが、厳密なところと緩いところが混ざっていて、ちょっと損だと思いました。
一番気になったのはラストのセリフです。残る人と出ていく人がいるのはいいんですけれども、残る人が死んだ仲間をさして「みんなもそうしたと思う」と言いますよね。「みんなもそうしたと思う」という気持ちで新しいことを選んでいいのか。
同じ結果を選ぶにしても、もっと積極的に考えて、それを経て出した新しい答えが「残る」という選択だったらいいんですけれど、「みんなもそうしたと思う」という考え方での「残る」という選択は、大げさな言い方をすれば、政治のことが今これだけ意識的になっている時に、ちょっと寂しいことだと思います。
■菊池准
僕も同じような印象です。
彼らの主張や行動の核になる部分―親や他の誰かからもたらされた「教え」、あるいは「伝統」に縛られながら、それを軸にして生きて行くという初期設定が非常に不明確だったと思います。ただ「教え」ということになってしまっていて、それにみんなが縛られているという戯曲上の幹になる部分が、非常に曖昧な設定になっているんじゃないか、というのが気になります。だからいろいろなところに矛盾が生まれてくる。
例えば、こうした(「教えに従う」という)物語を今やる場合、世界的に起こっていることを考えても、個人の意思が実は個人の意志ではなく、いわゆる教訓とか徹底されたステレオタイプな何かによって支配されてしまっているということ自体がすごく危険な印象を与えてしまって、皆さんのやろうとしているメッセージと全く真逆なメッセージが伝わってしまう危険性がある。
その辺の突き詰めをはっきりしていないと、観客をどこに導こうとしているのか、自分たちがどこへ行こうとしているのかが見えてこない。
ただ演劇的に言うと、自然体な演技で会話もすごくナチュラルでとても良かったです。
けれど状況に対して何も変わっていかない。状況の捉え方やみんなの創り方の根幹ができていないから、状況が変わっていかないし、常に同じリズムでしかないのではないでしょうか。そこは直したほうがいいと思います。
■伊藤キム
例えが正しいかどうかわかりませんが、子供向けの啓発ドラマを見ているような感じがしました。
全てがわかりやすく進んでいて、とても予定調和なんですね。ぜんぜん裏切りがなくて新鮮味がなかったです。どういう事をされようとしているのか、メッセージみたいなものがあると思うんですが、演劇でどういうメッセージを発信していくんだろうということを、観ながらいろいろ考えさせられました。
■天野眞由美
私はとても好きでした。この芝居はとても穏やかで、内容もやってる方もみんな穏やかな感じで、私は好きでした。
出だしの会話はテンポよく、タッタッタッといったんですが、途中からダレてきましたね。それは先ほどおっしゃっていたような、設定の甘さというか 認識の甘さが影響したのかも知れません。
ただ、種を蒔く、水をかける、そういう動作はとてもきれいでした。穏やかさがこのチームの素敵なところだと思うんですが、もう一つ勢いというか強さというか、それがあったら良いなというふうに思いました。
※以上の文章は、第7回せんがわ劇場演劇コンクール表彰式の際、専門審査員から各劇団にむけて語られた講評を採録したものです。
劇団によって審査員の順番が違っていますが、当日の状況を再現しています。どうぞご了承ください。
「演劇活性化団体uni」の公演詳細ページはこちら
第7回せんがわ劇場演劇コンクール全体ページはこちら
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇チーフディレクター佐川大輔】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター櫻井拓見】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター柏木俊彦】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター桒原秀一】
第10回せんがわ劇場演劇コンクール・オーディエンス賞受賞公演【世界劇団】「天は蒼く燃えているか」≪稽古場レポート≫
受賞者インタビュー(3) 公社流体力学 太田日曜さん(グランプリ・俳優賞)
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター櫻井拓見】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター柏木俊彦】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター桒原秀一】
第10回せんがわ劇場演劇コンクール・オーディエンス賞受賞公演【世界劇団】「天は蒼く燃えているか」≪稽古場レポート≫
受賞者インタビュー(3) 公社流体力学 太田日曜さん(グランプリ・俳優賞)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。