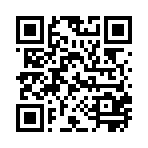2015年10月20日
受賞者インタビュー(6) ドキドキぼーいず・本間広大さん(グランプリ・演出賞)
―それではよろしくお願いいたします。
本間 よろしくお願いいたします。
―グランプリと演出賞受賞、おめでとうございます。
本間 ありがとうございます。
―受賞の感想を、といきたいところですが、まずは劇団の紹介からお願いたします。
本間 京都で活動しています。2009年に旗揚げして、大学卒業を目の前にして劇団員とどうするか、続けるかで一度休団して、2013年に再旗揚げという形で今もう一度やり直して、再旗揚げから3年目に突入した段階ですね。
で、若者を取り扱いたいという強い意志を持って活動してます。

本間 よろしくお願いいたします。
―グランプリと演出賞受賞、おめでとうございます。
本間 ありがとうございます。
―受賞の感想を、といきたいところですが、まずは劇団の紹介からお願いたします。
本間 京都で活動しています。2009年に旗揚げして、大学卒業を目の前にして劇団員とどうするか、続けるかで一度休団して、2013年に再旗揚げという形で今もう一度やり直して、再旗揚げから3年目に突入した段階ですね。
で、若者を取り扱いたいという強い意志を持って活動してます。

―今回はオーディエンス賞も京都の団体だったんですが、京都の演劇事情も教えてください。
本間 京都ってもともと都なんでプライドが高い人たちが多くて、でも京都としても国際的な何かをやっていきたいとか、地域とかとコミットしていきたいとか、すごい意識があって、京都の人たちが活動しているっていうより、外から入ってくる人たちが多いんですね。今そこに感化された京都の演劇をやっている人たちが、地方に飛んで行ったり、福岡に飛んで行ったり富山に行ったり、いろんなところへ行く劇団が多いですね。
―では改めまして、今回のグランプリと演出賞、おめでとうございます。そちらの感想をお願いいたします。
本間 どうかなあ。見ていただけた方にはわかると思うんですけど、人間の暴力性だったり、狂気性とか、見たくないものを描くことを僕は結構目指していて。
これだけメディアや芸術や簡単に誰もが発信できる時代の中で、ただ娯楽として芸術は機能しないと僕は本気で思っていて、見てないことから逃げてはいけない気がしているんですね。それが他の表現者たちを見ていて、それはもう見えていることだからとか。
嫌なことを直視しないでこれから先どこに行くのかなあと僕は不安なので、結構自分がいやな気持ちになりながら、こういう作品を作っています。いやな気持ちって変ですが。
―それを突きつけられたとき、見た方たちがどう思うか、ということでしょうか。
本間 やっぱり観客が同時に居合わせて生でそれぞれが考えを持つっていうのは演劇にしかない多様性だなって僕は思ってて、だから全員がいやぁ良かったということじゃなくって、これはあかんかったわ、っていう意見が生まれる場になれるのが劇場であって演劇だと思うんで。結構批判されるような作品を作り続けたいと思います。
やはりツイッターとかフェイスブックやラインとかそうですけど、人間関係が簡単につながるのはやっぱり良いことでもあるし。でも僕はまだそれが無い、便利じゃなかった時代を幼少期に過ごしていて、まだ僕は便利さをわかっているからそれをうまく使い分けているんですけど。
今の子供たちがそれをわかるかといえばわからないし、だから僕たちがどういう風に人間関係の作り方を、ちゃんと教えていけるかがすごい大事だなと思います。
―今回の作品の中で目指したことも、やはりそこなんだと思うんですけど。今回の作品についてもう少し。
本間 結構僕は、若いな、青いなって言われることは、ポジティブに捉えているんですけど、今僕が等身大で作れる時期だなあと思っています。
この作品を初演したときに若者たちとすごい話したというか、「ありえそうだね、殺人は」とか、「自分もとか」。
掘り返してみると自分の中にすごくあることを、ニュースで、「わ―、これはないわ」とか「私は殺さないな」ていうのは、本当にその一言で決まっているの?っていうのは疑わなくちゃいけないな、というところから発信して。掘り下げてみるといっぱい僕らの中に狂気があるのに、人間は頭が良いから抑えている。
―今もそうですけど、やはり簡単にそうした事件がたくさん起きていると思うんですけど、そうしたこととリンクさせながらということですか?
本間 僕は結構日常に、いかにお客さんに持って帰らせるかが演劇の大事なところだなと思っていて、自分たちの生活とどう、照らし合わせるかというか。例えばテレビを見ている時って、テレビを見ている自覚が無いんですよね。僕は現実と虚構の間をずっと行こうと思っていて、観客が観客だと思って見てて欲しいと思ってますし。
これは今回100%できなかったと思っているんですが、例えばボクシングとかでいつ人が死ぬかもしれないなんてことを、僕らは娯楽として見ているわけじゃないですか。その感覚にこの演劇がなれば良いなと思っていたとか、何かに盛り上げられている空気っていうのが結構怖いっていうか。
僕は空気を読まないときが必要だよ、ってすごく思っていて。今の戦争の雰囲気もそうですし、空気なのか自分の考えなのかを考えるきっかけにはなればなあと思って、身近な事件から取り上げてみました。
脚本の中で僕ら表現者は簡単に人を殺しちゃうので。それってどういうことなのかなって。物語だと簡単だからなあって。でもこれだけ面白い人生をみんなが歩んでいる中で、新たな横の物語を新しく提唱するんじゃなくって、再検証した方がいいなって。
この作品を公共劇場のコンクールに持ってくることは勇気が要りました。良いのかなって。市民の方の見たいものではない。ただ、それは難しいところで、公共劇場の役割と芸術の役割をどう考えるかで。いやぁ、でもいっかって。(笑)やってみた方が良いし、ふたを開けてみないと観客の皆さんがどういう風に思っているのかって意外と受けたりするっていうか、やっぱり人間って頭が良いんだなとすごい思うんですね。
―東京の公演は初めてですか?
本間 そうなんです。初めてです。
―せんがわ劇場のイメージってどうですか?
本間 贔屓目ではなく素晴らしい、ちょうど良いホールだなと思っていて、小劇場ってお客さんのキャパシティーも限られてるし、その中で公共劇場として活動する、しかも新しい劇場で、ちょうど東京の中心じゃない場所にある町で年間スケジュールですごい意欲的にやっていることは、実は京都では見当たらなかったり、意外と地方でも見当たらないなあと。おそらく東京との距離をすごい考えている劇場だなと思って。これは僕が考えている京都や演劇に対する距離感にコミットすると思いました。
―京都でもこうした劇場と劇団の関係を作っていこうみたいな活動っていうのはあるんですか?
本間 僕が今アトリエ劇研っていうところで創造サポートカンパニーに選ばれて、ディレクターとよくミーティングをするんです、選ばれた方たちは。「どう演劇を見るか」ということで。これって実はあんまり無かった流れなんです。その前にも、例えば今回来た劇団しようよさんと同世代で京都でやっていることをどう見るか、ということを最近話し始めているんですが、ちょうど今劇場と折り合いが付き始めたところなんですよね。
―今後の抱負とか今度東京で公演が決まりましたけど、意気込みとかお聞かせください。
本間 もっと勉強してもっとクオリティーの高い作品を作りたいことと、東京だから、京都から来たからとかではない目線で見れるものを作りたいなと思ってます。精一杯がんばります。
―どうもありがとうございました。

■本間広大
1990年生まれ、新潟出身。高校生の頃より演劇をはじめ、自ら演出し、出演した「お葬式(作、亀井佳宏)」では第41回新潟県高校演劇大会
最優秀賞を受賞。卒業後は京都造形芸術大学
舞台芸術学科に進学し、演劇について学ぶ。入学からほどなくして自身の劇団『ドキドキぼーいず』を旗揚げ、精力的に活動を行う。劇団で脚本・演出を担う中、他団体の作品にも俳優として多く活躍する。主に、
福岡演劇フェスティバルFFAC企画 柿食う客「ゴーゴリ病棟」 、演劇計画Ⅱ-戯曲創作- 柳沼昭徳 作・演出「新・内山」など。
■ドキドキぼーいず
京都を拠点に中心する若手演劇チーム。
2013年、代表である本間広大の学生卒業を機に再旗揚げ。
演劇の虚構性を利用した作品づくりが特徴的で、近年は、「現代を生きる若者の身体性」にスポットをあてている。
メンバーは9名で構成されており、俳優・演出家の他、音響・照明・映像・美術のスタッフが専属的に在籍しており、俳優と演出家で構成される日本の劇団には珍しい形態をとっている。
2015年よりアトリエ劇研創造サポートカンパニーに選出される。
写真撮影:青二才晃(せんがわ劇場市民サポーター)
本間 京都ってもともと都なんでプライドが高い人たちが多くて、でも京都としても国際的な何かをやっていきたいとか、地域とかとコミットしていきたいとか、すごい意識があって、京都の人たちが活動しているっていうより、外から入ってくる人たちが多いんですね。今そこに感化された京都の演劇をやっている人たちが、地方に飛んで行ったり、福岡に飛んで行ったり富山に行ったり、いろんなところへ行く劇団が多いですね。
―では改めまして、今回のグランプリと演出賞、おめでとうございます。そちらの感想をお願いいたします。
本間 どうかなあ。見ていただけた方にはわかると思うんですけど、人間の暴力性だったり、狂気性とか、見たくないものを描くことを僕は結構目指していて。
これだけメディアや芸術や簡単に誰もが発信できる時代の中で、ただ娯楽として芸術は機能しないと僕は本気で思っていて、見てないことから逃げてはいけない気がしているんですね。それが他の表現者たちを見ていて、それはもう見えていることだからとか。
嫌なことを直視しないでこれから先どこに行くのかなあと僕は不安なので、結構自分がいやな気持ちになりながら、こういう作品を作っています。いやな気持ちって変ですが。
―それを突きつけられたとき、見た方たちがどう思うか、ということでしょうか。
本間 やっぱり観客が同時に居合わせて生でそれぞれが考えを持つっていうのは演劇にしかない多様性だなって僕は思ってて、だから全員がいやぁ良かったということじゃなくって、これはあかんかったわ、っていう意見が生まれる場になれるのが劇場であって演劇だと思うんで。結構批判されるような作品を作り続けたいと思います。
やはりツイッターとかフェイスブックやラインとかそうですけど、人間関係が簡単につながるのはやっぱり良いことでもあるし。でも僕はまだそれが無い、便利じゃなかった時代を幼少期に過ごしていて、まだ僕は便利さをわかっているからそれをうまく使い分けているんですけど。
今の子供たちがそれをわかるかといえばわからないし、だから僕たちがどういう風に人間関係の作り方を、ちゃんと教えていけるかがすごい大事だなと思います。
―今回の作品の中で目指したことも、やはりそこなんだと思うんですけど。今回の作品についてもう少し。

本間 結構僕は、若いな、青いなって言われることは、ポジティブに捉えているんですけど、今僕が等身大で作れる時期だなあと思っています。
この作品を初演したときに若者たちとすごい話したというか、「ありえそうだね、殺人は」とか、「自分もとか」。
掘り返してみると自分の中にすごくあることを、ニュースで、「わ―、これはないわ」とか「私は殺さないな」ていうのは、本当にその一言で決まっているの?っていうのは疑わなくちゃいけないな、というところから発信して。掘り下げてみるといっぱい僕らの中に狂気があるのに、人間は頭が良いから抑えている。
―今もそうですけど、やはり簡単にそうした事件がたくさん起きていると思うんですけど、そうしたこととリンクさせながらということですか?
本間 僕は結構日常に、いかにお客さんに持って帰らせるかが演劇の大事なところだなと思っていて、自分たちの生活とどう、照らし合わせるかというか。例えばテレビを見ている時って、テレビを見ている自覚が無いんですよね。僕は現実と虚構の間をずっと行こうと思っていて、観客が観客だと思って見てて欲しいと思ってますし。
これは今回100%できなかったと思っているんですが、例えばボクシングとかでいつ人が死ぬかもしれないなんてことを、僕らは娯楽として見ているわけじゃないですか。その感覚にこの演劇がなれば良いなと思っていたとか、何かに盛り上げられている空気っていうのが結構怖いっていうか。
僕は空気を読まないときが必要だよ、ってすごく思っていて。今の戦争の雰囲気もそうですし、空気なのか自分の考えなのかを考えるきっかけにはなればなあと思って、身近な事件から取り上げてみました。
脚本の中で僕ら表現者は簡単に人を殺しちゃうので。それってどういうことなのかなって。物語だと簡単だからなあって。でもこれだけ面白い人生をみんなが歩んでいる中で、新たな横の物語を新しく提唱するんじゃなくって、再検証した方がいいなって。
この作品を公共劇場のコンクールに持ってくることは勇気が要りました。良いのかなって。市民の方の見たいものではない。ただ、それは難しいところで、公共劇場の役割と芸術の役割をどう考えるかで。いやぁ、でもいっかって。(笑)やってみた方が良いし、ふたを開けてみないと観客の皆さんがどういう風に思っているのかって意外と受けたりするっていうか、やっぱり人間って頭が良いんだなとすごい思うんですね。
―東京の公演は初めてですか?
本間 そうなんです。初めてです。
―せんがわ劇場のイメージってどうですか?
本間 贔屓目ではなく素晴らしい、ちょうど良いホールだなと思っていて、小劇場ってお客さんのキャパシティーも限られてるし、その中で公共劇場として活動する、しかも新しい劇場で、ちょうど東京の中心じゃない場所にある町で年間スケジュールですごい意欲的にやっていることは、実は京都では見当たらなかったり、意外と地方でも見当たらないなあと。おそらく東京との距離をすごい考えている劇場だなと思って。これは僕が考えている京都や演劇に対する距離感にコミットすると思いました。
―京都でもこうした劇場と劇団の関係を作っていこうみたいな活動っていうのはあるんですか?
本間 僕が今アトリエ劇研っていうところで創造サポートカンパニーに選ばれて、ディレクターとよくミーティングをするんです、選ばれた方たちは。「どう演劇を見るか」ということで。これって実はあんまり無かった流れなんです。その前にも、例えば今回来た劇団しようよさんと同世代で京都でやっていることをどう見るか、ということを最近話し始めているんですが、ちょうど今劇場と折り合いが付き始めたところなんですよね。
―今後の抱負とか今度東京で公演が決まりましたけど、意気込みとかお聞かせください。
本間 もっと勉強してもっとクオリティーの高い作品を作りたいことと、東京だから、京都から来たからとかではない目線で見れるものを作りたいなと思ってます。精一杯がんばります。
―どうもありがとうございました。

■本間広大
1990年生まれ、新潟出身。高校生の頃より演劇をはじめ、自ら演出し、出演した「お葬式(作、亀井佳宏)」では第41回新潟県高校演劇大会
最優秀賞を受賞。卒業後は京都造形芸術大学
舞台芸術学科に進学し、演劇について学ぶ。入学からほどなくして自身の劇団『ドキドキぼーいず』を旗揚げ、精力的に活動を行う。劇団で脚本・演出を担う中、他団体の作品にも俳優として多く活躍する。主に、
福岡演劇フェスティバルFFAC企画 柿食う客「ゴーゴリ病棟」 、演劇計画Ⅱ-戯曲創作- 柳沼昭徳 作・演出「新・内山」など。
■ドキドキぼーいず
京都を拠点に中心する若手演劇チーム。
2013年、代表である本間広大の学生卒業を機に再旗揚げ。
演劇の虚構性を利用した作品づくりが特徴的で、近年は、「現代を生きる若者の身体性」にスポットをあてている。
メンバーは9名で構成されており、俳優・演出家の他、音響・照明・映像・美術のスタッフが専属的に在籍しており、俳優と演出家で構成される日本の劇団には珍しい形態をとっている。
2015年よりアトリエ劇研創造サポートカンパニーに選出される。
写真撮影:青二才晃(せんがわ劇場市民サポーター)
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇チーフディレクター佐川大輔】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター櫻井拓見】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター柏木俊彦】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター桒原秀一】
第10回せんがわ劇場演劇コンクール・オーディエンス賞受賞公演【世界劇団】「天は蒼く燃えているか」≪稽古場レポート≫
受賞者インタビュー(3) 公社流体力学 太田日曜さん(グランプリ・俳優賞)
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター櫻井拓見】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター柏木俊彦】
演劇コンクールスピンオフ企画「映像と生で楽しむリーディング」に向けて 【せんがわ劇場演劇ディレクター桒原秀一】
第10回せんがわ劇場演劇コンクール・オーディエンス賞受賞公演【世界劇団】「天は蒼く燃えているか」≪稽古場レポート≫
受賞者インタビュー(3) 公社流体力学 太田日曜さん(グランプリ・俳優賞)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。