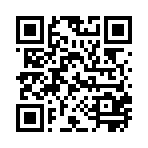2014年10月31日
せんがわ劇場サンデー・マティネ・コンサート Vol. 131 「チェンバロ」
9月21日に行われたサンデー・マティネ・コンサートVol.131の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。
-------
2014年9月後半のサンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)は、チェンバロのミニコンサートを開催いたしました。
演奏してくださるのは、優れたチェンバロ奏者としてはもちろん、バロック音楽のワークショップや指揮活動などでも注目されている大塚直哉(おおつかなおや)さん。
早朝のNHK FM放送「古楽の楽しみ」のパーソナリティもつとめられている音楽家です。
チェンバロの生演奏が間近に聴ける絶好のチャンスとあって、おかげさまで今回もほぼ満席の盛況ぶり。
サンマチ常連の皆さまに加えて、子育て世代の若いお母様方と「お出かけ着」に身を包んだ子供たちの姿も多く見られました。
秋晴れの爽やかな日曜の朝。繊細華麗な音色、心なごむ素晴らしい演奏…。
宮廷人になったかのようなゴージャスなひと時を過ごしました。

●チェンバロのソロ演奏を間近に聴く喜び
劇場ホールに入ると、舞台上にはグランドピアノに似た「グランド型」の優美なチェンバロが静かにスタンバイしています。
大きな拍手で大塚さんが迎えられ、さっそく演奏が始まります。
まず、17世紀フランスの作曲家ルイ・クープランの『組曲ヘ長調』から「前奏曲」と「バスクのブランル」です。“ブランル”はダンス曲(舞曲)の一種。明るくリズミカルな曲想で、誰もが「歓迎されている」気分になる華やかな演奏です。
「ドイツ語やイタリア語でチェンバロ。英語ではハープシコード、フランス語ではクラヴサンと呼ばれます」と大塚さんの解説が入ります。
このチェンバロは「17~18世紀頃、『フランダースの犬』で知られるフランドル地方で作られたオリジナル楽器を現代に復元したもの」。今日のプログラムも作曲された当時の古楽器でお聴きいただこうという趣向です。
次に、爽やかな日曜の朝にふさわしく、鳥のさえずりをチェンバロで模した「描写音楽」の演奏が続きます。
ダカン作曲「かっこう」、フランソワ・クープラン作曲「恋のうぐいす」、そしてラモー作曲の「めんどり」。
生き生きと自然の情景を描く可憐な音楽の世界が披露されます。
「17~18世紀、フランスで多くのチェンバロ曲が書かれますが、中でもチェンバロらしい曲といえばダンス曲です」と大塚さん。今年(2014年)没後250年を迎えたラモーが、自身のオペラの中に用いた軽快な舞曲「メヌエット」を弾いて前半が終わりました。
フランソワ・クープランやラモーというと、華やかなりし頃のフランス王宮が思い浮かびます。
こうしたチェンバロ音楽が太陽王ルイ14世の治世下、ヴェルサイユ宮殿などで演奏されていたかと思うと、気分はまた格別です。
●バッハが愛した気品あふれるフランスのダンス曲
後半、「音楽の父」ヨハン・ゼバスティアン・バッハの曲の演奏に移ります。
まず、バッハのフランス音楽への憧憬がたっぷり注がれた『フランス風序曲』から、「序曲」「クーラント」「ガヴォット」「ブレ」の4曲の演奏です。
大塚さんの解説が入ります。
「ピアノは弦をハンマーでたたきますが、チェンバロはギターやハープと同様、小さな爪で弦をはじいて音を出します。
実はこのチェンバロは、鍵盤が上下2段式になっており、上と下で音色が違います。
1オクターヴ高いキラキラした音も出せます。
さまざまな楽器の音を出したり、オーケストラの真似までできるよう工夫されているのです。
バッハがこの2段式鍵盤のチェンバロ1台でフランスのオペラを演奏できるよう作曲したのが、この『フランス風序曲』です」。
音楽ラジオ番組の案内役らしい穏やかで滑らかな語り口です。
コンサート最後も優雅で気品にあふれたフランス風のダンス曲で締めくくります。
バッハ作曲『フランス組曲 第5番』から「アルマンド」「サラバンド」、そして『無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番』から「シャコンヌ イ短調」(演奏者自身による編曲版)。
そして、アンコールはお馴染み、バッハの「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第1番 プレリュード」。
混じりけのない神聖なまでの調べが抜けるような秋の空に響き、劇場はお客様の盛大な拍手に包まれました。
●劇場は「ハレの場」、日常を刺激する文化の拠点
近ごろ、心癒やす「古楽器」の演奏企画を楽しみにされている方が多いように見受けられます。
せんがわ劇場は舞台と客席の距離が近く、反射音の残響も短めで、古楽器の演奏を楽しむには適した劇場かもしれません。
ところで、コンサートの反応(満足度)は、お客様の「アンケート回収率」にも表れます。
今回のチェンバロ・ミニコンサートでは、約8割という高い回収率でした。
子供たちがお行儀よく「ありがとうございました」と声を添えてスタッフにアンケート用紙を差し出す姿が、ほほえましく心に残ります。
柳田民俗学を持ち出すまでもなく、劇場は地域の「ハレ」の場であり、日常(「ケ」)を刺激する文化の拠点です。
「お出かけ着の子供たち」にとって、劇場で過ごした今日は「ハレ」の日として記憶されるでしょう。
卓越した演奏に感謝し、満足気なお客様、子供たちの笑顔を見送り、いろんな手応えを感じる朝のひと時でした。
(取材・文/ライター 才目)
-------
2014年9月後半のサンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)は、チェンバロのミニコンサートを開催いたしました。
演奏してくださるのは、優れたチェンバロ奏者としてはもちろん、バロック音楽のワークショップや指揮活動などでも注目されている大塚直哉(おおつかなおや)さん。
早朝のNHK FM放送「古楽の楽しみ」のパーソナリティもつとめられている音楽家です。
チェンバロの生演奏が間近に聴ける絶好のチャンスとあって、おかげさまで今回もほぼ満席の盛況ぶり。
サンマチ常連の皆さまに加えて、子育て世代の若いお母様方と「お出かけ着」に身を包んだ子供たちの姿も多く見られました。
秋晴れの爽やかな日曜の朝。繊細華麗な音色、心なごむ素晴らしい演奏…。
宮廷人になったかのようなゴージャスなひと時を過ごしました。

●チェンバロのソロ演奏を間近に聴く喜び
劇場ホールに入ると、舞台上にはグランドピアノに似た「グランド型」の優美なチェンバロが静かにスタンバイしています。
大きな拍手で大塚さんが迎えられ、さっそく演奏が始まります。
まず、17世紀フランスの作曲家ルイ・クープランの『組曲ヘ長調』から「前奏曲」と「バスクのブランル」です。“ブランル”はダンス曲(舞曲)の一種。明るくリズミカルな曲想で、誰もが「歓迎されている」気分になる華やかな演奏です。
「ドイツ語やイタリア語でチェンバロ。英語ではハープシコード、フランス語ではクラヴサンと呼ばれます」と大塚さんの解説が入ります。
このチェンバロは「17~18世紀頃、『フランダースの犬』で知られるフランドル地方で作られたオリジナル楽器を現代に復元したもの」。今日のプログラムも作曲された当時の古楽器でお聴きいただこうという趣向です。
次に、爽やかな日曜の朝にふさわしく、鳥のさえずりをチェンバロで模した「描写音楽」の演奏が続きます。
ダカン作曲「かっこう」、フランソワ・クープラン作曲「恋のうぐいす」、そしてラモー作曲の「めんどり」。
生き生きと自然の情景を描く可憐な音楽の世界が披露されます。
「17~18世紀、フランスで多くのチェンバロ曲が書かれますが、中でもチェンバロらしい曲といえばダンス曲です」と大塚さん。今年(2014年)没後250年を迎えたラモーが、自身のオペラの中に用いた軽快な舞曲「メヌエット」を弾いて前半が終わりました。
フランソワ・クープランやラモーというと、華やかなりし頃のフランス王宮が思い浮かびます。
こうしたチェンバロ音楽が太陽王ルイ14世の治世下、ヴェルサイユ宮殿などで演奏されていたかと思うと、気分はまた格別です。
●バッハが愛した気品あふれるフランスのダンス曲
後半、「音楽の父」ヨハン・ゼバスティアン・バッハの曲の演奏に移ります。
まず、バッハのフランス音楽への憧憬がたっぷり注がれた『フランス風序曲』から、「序曲」「クーラント」「ガヴォット」「ブレ」の4曲の演奏です。
大塚さんの解説が入ります。
「ピアノは弦をハンマーでたたきますが、チェンバロはギターやハープと同様、小さな爪で弦をはじいて音を出します。
実はこのチェンバロは、鍵盤が上下2段式になっており、上と下で音色が違います。
1オクターヴ高いキラキラした音も出せます。
さまざまな楽器の音を出したり、オーケストラの真似までできるよう工夫されているのです。
バッハがこの2段式鍵盤のチェンバロ1台でフランスのオペラを演奏できるよう作曲したのが、この『フランス風序曲』です」。
音楽ラジオ番組の案内役らしい穏やかで滑らかな語り口です。
コンサート最後も優雅で気品にあふれたフランス風のダンス曲で締めくくります。
バッハ作曲『フランス組曲 第5番』から「アルマンド」「サラバンド」、そして『無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番』から「シャコンヌ イ短調」(演奏者自身による編曲版)。
そして、アンコールはお馴染み、バッハの「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第1番 プレリュード」。
混じりけのない神聖なまでの調べが抜けるような秋の空に響き、劇場はお客様の盛大な拍手に包まれました。
●劇場は「ハレの場」、日常を刺激する文化の拠点
近ごろ、心癒やす「古楽器」の演奏企画を楽しみにされている方が多いように見受けられます。
せんがわ劇場は舞台と客席の距離が近く、反射音の残響も短めで、古楽器の演奏を楽しむには適した劇場かもしれません。
ところで、コンサートの反応(満足度)は、お客様の「アンケート回収率」にも表れます。
今回のチェンバロ・ミニコンサートでは、約8割という高い回収率でした。
子供たちがお行儀よく「ありがとうございました」と声を添えてスタッフにアンケート用紙を差し出す姿が、ほほえましく心に残ります。
柳田民俗学を持ち出すまでもなく、劇場は地域の「ハレ」の場であり、日常(「ケ」)を刺激する文化の拠点です。
「お出かけ着の子供たち」にとって、劇場で過ごした今日は「ハレ」の日として記憶されるでしょう。
卓越した演奏に感謝し、満足気なお客様、子供たちの笑顔を見送り、いろんな手応えを感じる朝のひと時でした。
(取材・文/ライター 才目)
【第8回せんがわピアノオーディション受賞コンサート 松本悠里さんインタビュー】
【第8回せんがわピアノオーディション受賞コンサート 五条玲緒インタビュー】
サンデー・マティネ・コンサートvol.216
サンデー・マティネ・コンサートvol.215 世界の楽器シリーズ
ファミリー音楽プログラムvol.23 演奏会入門コンサート
サンデー・マティネ・コンサート vol.214 〈未来のホープコンサートvol.24〉
【第8回せんがわピアノオーディション受賞コンサート 五条玲緒インタビュー】
サンデー・マティネ・コンサートvol.216
サンデー・マティネ・コンサートvol.215 世界の楽器シリーズ
ファミリー音楽プログラムvol.23 演奏会入門コンサート
サンデー・マティネ・コンサート vol.214 〈未来のホープコンサートvol.24〉
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。