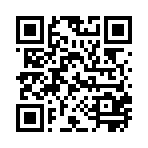2014年10月09日
せんがわ劇場サンデー・マティネ・コンサートVol. 130 in JAZZ ART せんがわ ~ 「超歌唱家・巻上公一」
9月7日に行われたサンデー・マティネ・コンサートVol.130の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。
せんがわ劇場が2008年に開館して以来、「サンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)」と「JAZZ ART せんがわ」は途切れることなく回を重ねています。
2014年9月7日の「サンマチ Vol. 130」は、7年目を迎えた「JAZZ ART せんがわ2014」内での開催されました。
演奏家は、「JAZZ ART せんがわ」の総合プロデューサーを務める巻上公一(まきがみこういち)氏。いよいよ満を持しての登場です。
巻上氏は、バンド「ヒカシュー」のリーダーであるだけでなく、国内外の前衛芸術シーンで多彩な活動を続けており、とりわけ「超歌唱家」として声と歌唱の可能性を大きく拡げたことで知られます。
サンマチでは、トゥバ共和国への旅、音楽や演劇、即興芸術にまつわる貴重なエピソードを交えつつ、多彩なソロパフォーマンスを披露。「宇宙語」の即興では場内の子供たちが歓声を上げて大笑いしたのが印象的でした。
喉歌など独特の唱法、珍しい楽器を操りながらの変幻自在の“巻上ヴォイス・ワールド”。
観客は驚き、魅せられ、まるで見知らぬ世界を旅するような気分に浸りました。

----*----*----*----*----*----
●「JAZZ ART せんがわ」が始まったきっかけ
今回のサンマチは、「JAZZ ART せんがわ」の舞台・客席セッティングをそのまま利用します。
いつもお越しくださるサンマチ・ファンの皆さんに加えて、「JAZZ ART」ファンのお客様が大勢おいでくださり、おかげさまで満員御礼となった場内。
お子様連れの若いファミリーも目立ち、華やいだ雰囲気です。
せんがわ劇場・萩原の司会とともに、大きな拍手で迎えられた巻上公一氏。
「JAZZ ART せんがわ」がどのようにして始まったのか、そのきっかけからトークが始まります。
「海外には前衛的な音楽フェスティバルがたくさんあります。
そこでよく日本のミュージシャンを見かけるのに、なぜ日本国内には彼らが参加できるフェスが少ないのだろう。
日本で彼らが結集できる音楽フェスをつくろうじゃないか。
ということで、せんがわ劇場のスタートともに「JAZZ ART せんがわ」が始まったのです」。
巻上氏の呼びかけのもと、日本だけでなく、ニューヨーク、ヨーロッパ、アジアからさまざまな音楽家が参加するようになり、いまやユニークな音楽フェスとして知られるようになった「JAZZ ART せんがわ」。
都心に近く、市民にも身近な劇場で国内外の前衛アーティストが一堂に会するというのは、非常に稀なことといえるでしょう。7年間の「継続」、歴史の重みもそこに感じられます。
近年、日本でもフリージャズやノイズ系音楽への認知が広がり、自由即興演奏に市民が参加して町を盛り上げるイベントなどが開催されるようになりました。
「JAZZ ART せんがわ」は、そうした変化をリードしてきたのです。
●トゥバ共和国「口琴」「ホーメイ」との出会い
さて、巻上氏のソロパフォーマンスが始まります。
巻上氏はバンド演奏ではヴォーカルの他、電子楽器のテルミンやコルネットを担当しますが、舞台上にそうした楽器はありません。
「今日持ってきた楽器は、演奏できない楽器です。演奏できない楽器で演奏します」と、早くも巻上ワールド開陳。「まずは、口琴(こうきん)という楽器です。歯にはさんではじき、頭蓋骨を共鳴させますが、低い音なので皆さんには聴こえません。耳を澄ますと聴こえるかもしれません」。
まるで東洋の哲学者のように語りかける巻上氏。じっーと耳を澄ませて聴き入る観客。微かにブーンという低い音が響きます。すでに新しい音楽との出会いが始まっています。
続いて、モンゴル語で「ホーミー」、巻上氏が毎年通っているロシア連邦トゥバ共和国では「ホーメイ」と呼ばれる「喉歌」です。
遊牧民(ノマド)の人々が、大草原をバックに詠唱しているのをご覧になった方も多いでしょう。
喉(声帯)を緩めながら「オー、ウェー、イエー...」という低い声とともに、声に含まれる倍音の高音部を強調して口笛に似た音を出す独特の唱法です。
野太い声で巻上氏の見事なホーメイが劇場にこだまします。
「低いだみ声の中から、かすかに口笛のような音が聴こえてきませんか?」。子供たちは「聴こえる」と応えますが、どうも大人の耳には判然としません。耳がまだ慣れていないのかもしれません。
1979年にバンド「ヒカシュー」でメジャーデビューした巻上氏が、一対一で聴く「小さな音楽」に興味をもったのが、1994年から95年頃。トゥバ共和国の口琴やホーメイに出会ったのがきっかけといいます。
トゥバ共和国はシベリアの南、モンゴルの西北部に位置する小さな国です。物理学者のファインマン教授が興味をもったことでも知られます。
インターネットで航空券の予約もできない時代、巻上氏が苦労を重ねてトゥバ共和国を訪れた話、そこで出会った口琴の神秘的な演奏が続きます。
●「宇宙語即興パフォーマンス」に即反応する子供たち
巻上氏といえば、「声」とならんで、「即興」のイメージがあります。話は「声と即興」に移ります。
「1995年にニューヨークに行ってソロヴォイス作品『KUCHINOHA(クチノハ)』というアルバムを収録したんです。これも私の大きな転機となりました」。
ニューヨークは巻上氏が18歳の頃(約40年前)、ミュージカル劇団・東京キッドブラザースの一員として訪れたことがあり、ラ・ママ劇場での公演が失敗してトラウマとなった街だそうです。
続くロンドン公演で劇団は一時解散状態となったのですが、巻上氏はロンドンの前衛劇団にスカウトされ、2本の作品に出演。そこで「声の即興」に目覚めたといいます。
「ロンドンの前衛劇団でやったのが、宇宙人の役だったんです。合図でシーンが変わり、即興の宇宙語で会話する。でたらめな言葉で会話することを英語でジブリッシュといいますが、ジブリッシュでの掛け合い。どこかの国の言葉に聴こないよう、いろんな声を開発しなくてはいけなかったんです。こんな感じです…」と、始まったのが「宇宙語即興パフォーマンス」です。
「アハハハ…」子供たちが反射的に笑い出しました。巻上氏が声色を変えるたびにあちこちで大きな歓声と笑い声が上がります。
魂に直接訴えかける「声」の威力。子供たちの反応でますます激しく変化するヴォイス・パフォーマンス。
「声」による解放、即興の醍醐味を目の当たりにする瞬間でした。
ソロヴォイス作品の発表以降、世界の音楽フェスティバルから招かれるようになった巻上氏。「ヒカシュー」を続けながら、音楽だけでなく、演劇・舞踏を含む前衛芸術の領域へ活動の幅は大きく広がっていきました。
●異次元の巻上ワールドに観客の意識もさまよう
後半は、「口琴を付けたウクレレ」「吹けない尺八」での演奏ですが、これらを弾きこなしながら歌を歌う独自の巻上ワールド。もう観客は異次元の世界にすっかり引き込まれ、なぜか気持もよくなってきます。
「吹けない尺八」をフーッと力一杯吹く巻上氏の呼吸に子供たちは完全に同期して、また歓声が上がります。
やがて尺八の本来の音が出ると感動もひとしおです。
「ヴォイス・パフォーマンスでもそうですが、こうした演奏を続けていると、僕もお客様も一種のトランス(忘我)状態に入って気持よくなってくるんです」。
最後の演奏は、トゥバ共和国の民族楽器「ドシュプルール」、日本の三味線にあたる三弦楽器を弾きながら、ホーメイと即興が合体した音楽。
即興演奏のカリスマ、デレク・ベイリー氏に招かれ、英国の即興演奏フェスティバルで演奏を披露したといいます。
今度のホーメイではどっしりとした低音に重畳して澄んだ口笛のような倍音がはっきり聴こえます。
まさに「圧巻」という言葉がふさわしい歌唱でサンマチを締めくくった巻上氏。
「JAZZ ART せんがわ」総合プロデューサーの名に恥じない超絶パフォーマンスに、サンマチ・ファンも心から称賛の拍手を送りました。
(取材・文/ライター 才目)
せんがわ劇場が2008年に開館して以来、「サンデー・マティネ・コンサート(サンマチ)」と「JAZZ ART せんがわ」は途切れることなく回を重ねています。
2014年9月7日の「サンマチ Vol. 130」は、7年目を迎えた「JAZZ ART せんがわ2014」内での開催されました。
演奏家は、「JAZZ ART せんがわ」の総合プロデューサーを務める巻上公一(まきがみこういち)氏。いよいよ満を持しての登場です。
巻上氏は、バンド「ヒカシュー」のリーダーであるだけでなく、国内外の前衛芸術シーンで多彩な活動を続けており、とりわけ「超歌唱家」として声と歌唱の可能性を大きく拡げたことで知られます。
サンマチでは、トゥバ共和国への旅、音楽や演劇、即興芸術にまつわる貴重なエピソードを交えつつ、多彩なソロパフォーマンスを披露。「宇宙語」の即興では場内の子供たちが歓声を上げて大笑いしたのが印象的でした。
喉歌など独特の唱法、珍しい楽器を操りながらの変幻自在の“巻上ヴォイス・ワールド”。
観客は驚き、魅せられ、まるで見知らぬ世界を旅するような気分に浸りました。

----*----*----*----*----*----
●「JAZZ ART せんがわ」が始まったきっかけ
今回のサンマチは、「JAZZ ART せんがわ」の舞台・客席セッティングをそのまま利用します。
いつもお越しくださるサンマチ・ファンの皆さんに加えて、「JAZZ ART」ファンのお客様が大勢おいでくださり、おかげさまで満員御礼となった場内。
お子様連れの若いファミリーも目立ち、華やいだ雰囲気です。
せんがわ劇場・萩原の司会とともに、大きな拍手で迎えられた巻上公一氏。
「JAZZ ART せんがわ」がどのようにして始まったのか、そのきっかけからトークが始まります。
「海外には前衛的な音楽フェスティバルがたくさんあります。
そこでよく日本のミュージシャンを見かけるのに、なぜ日本国内には彼らが参加できるフェスが少ないのだろう。
日本で彼らが結集できる音楽フェスをつくろうじゃないか。
ということで、せんがわ劇場のスタートともに「JAZZ ART せんがわ」が始まったのです」。
巻上氏の呼びかけのもと、日本だけでなく、ニューヨーク、ヨーロッパ、アジアからさまざまな音楽家が参加するようになり、いまやユニークな音楽フェスとして知られるようになった「JAZZ ART せんがわ」。
都心に近く、市民にも身近な劇場で国内外の前衛アーティストが一堂に会するというのは、非常に稀なことといえるでしょう。7年間の「継続」、歴史の重みもそこに感じられます。
近年、日本でもフリージャズやノイズ系音楽への認知が広がり、自由即興演奏に市民が参加して町を盛り上げるイベントなどが開催されるようになりました。
「JAZZ ART せんがわ」は、そうした変化をリードしてきたのです。
●トゥバ共和国「口琴」「ホーメイ」との出会い
さて、巻上氏のソロパフォーマンスが始まります。
巻上氏はバンド演奏ではヴォーカルの他、電子楽器のテルミンやコルネットを担当しますが、舞台上にそうした楽器はありません。
「今日持ってきた楽器は、演奏できない楽器です。演奏できない楽器で演奏します」と、早くも巻上ワールド開陳。「まずは、口琴(こうきん)という楽器です。歯にはさんではじき、頭蓋骨を共鳴させますが、低い音なので皆さんには聴こえません。耳を澄ますと聴こえるかもしれません」。
まるで東洋の哲学者のように語りかける巻上氏。じっーと耳を澄ませて聴き入る観客。微かにブーンという低い音が響きます。すでに新しい音楽との出会いが始まっています。
続いて、モンゴル語で「ホーミー」、巻上氏が毎年通っているロシア連邦トゥバ共和国では「ホーメイ」と呼ばれる「喉歌」です。
遊牧民(ノマド)の人々が、大草原をバックに詠唱しているのをご覧になった方も多いでしょう。
喉(声帯)を緩めながら「オー、ウェー、イエー...」という低い声とともに、声に含まれる倍音の高音部を強調して口笛に似た音を出す独特の唱法です。
野太い声で巻上氏の見事なホーメイが劇場にこだまします。
「低いだみ声の中から、かすかに口笛のような音が聴こえてきませんか?」。子供たちは「聴こえる」と応えますが、どうも大人の耳には判然としません。耳がまだ慣れていないのかもしれません。
1979年にバンド「ヒカシュー」でメジャーデビューした巻上氏が、一対一で聴く「小さな音楽」に興味をもったのが、1994年から95年頃。トゥバ共和国の口琴やホーメイに出会ったのがきっかけといいます。
トゥバ共和国はシベリアの南、モンゴルの西北部に位置する小さな国です。物理学者のファインマン教授が興味をもったことでも知られます。
インターネットで航空券の予約もできない時代、巻上氏が苦労を重ねてトゥバ共和国を訪れた話、そこで出会った口琴の神秘的な演奏が続きます。
●「宇宙語即興パフォーマンス」に即反応する子供たち
巻上氏といえば、「声」とならんで、「即興」のイメージがあります。話は「声と即興」に移ります。
「1995年にニューヨークに行ってソロヴォイス作品『KUCHINOHA(クチノハ)』というアルバムを収録したんです。これも私の大きな転機となりました」。
ニューヨークは巻上氏が18歳の頃(約40年前)、ミュージカル劇団・東京キッドブラザースの一員として訪れたことがあり、ラ・ママ劇場での公演が失敗してトラウマとなった街だそうです。
続くロンドン公演で劇団は一時解散状態となったのですが、巻上氏はロンドンの前衛劇団にスカウトされ、2本の作品に出演。そこで「声の即興」に目覚めたといいます。
「ロンドンの前衛劇団でやったのが、宇宙人の役だったんです。合図でシーンが変わり、即興の宇宙語で会話する。でたらめな言葉で会話することを英語でジブリッシュといいますが、ジブリッシュでの掛け合い。どこかの国の言葉に聴こないよう、いろんな声を開発しなくてはいけなかったんです。こんな感じです…」と、始まったのが「宇宙語即興パフォーマンス」です。
「アハハハ…」子供たちが反射的に笑い出しました。巻上氏が声色を変えるたびにあちこちで大きな歓声と笑い声が上がります。
魂に直接訴えかける「声」の威力。子供たちの反応でますます激しく変化するヴォイス・パフォーマンス。
「声」による解放、即興の醍醐味を目の当たりにする瞬間でした。
ソロヴォイス作品の発表以降、世界の音楽フェスティバルから招かれるようになった巻上氏。「ヒカシュー」を続けながら、音楽だけでなく、演劇・舞踏を含む前衛芸術の領域へ活動の幅は大きく広がっていきました。
●異次元の巻上ワールドに観客の意識もさまよう
後半は、「口琴を付けたウクレレ」「吹けない尺八」での演奏ですが、これらを弾きこなしながら歌を歌う独自の巻上ワールド。もう観客は異次元の世界にすっかり引き込まれ、なぜか気持もよくなってきます。
「吹けない尺八」をフーッと力一杯吹く巻上氏の呼吸に子供たちは完全に同期して、また歓声が上がります。
やがて尺八の本来の音が出ると感動もひとしおです。
「ヴォイス・パフォーマンスでもそうですが、こうした演奏を続けていると、僕もお客様も一種のトランス(忘我)状態に入って気持よくなってくるんです」。
最後の演奏は、トゥバ共和国の民族楽器「ドシュプルール」、日本の三味線にあたる三弦楽器を弾きながら、ホーメイと即興が合体した音楽。
即興演奏のカリスマ、デレク・ベイリー氏に招かれ、英国の即興演奏フェスティバルで演奏を披露したといいます。
今度のホーメイではどっしりとした低音に重畳して澄んだ口笛のような倍音がはっきり聴こえます。
まさに「圧巻」という言葉がふさわしい歌唱でサンマチを締めくくった巻上氏。
「JAZZ ART せんがわ」総合プロデューサーの名に恥じない超絶パフォーマンスに、サンマチ・ファンも心から称賛の拍手を送りました。
(取材・文/ライター 才目)
【第8回せんがわピアノオーディション受賞コンサート 松本悠里さんインタビュー】
【第8回せんがわピアノオーディション受賞コンサート 五条玲緒インタビュー】
サンデー・マティネ・コンサートvol.216
サンデー・マティネ・コンサートvol.215 世界の楽器シリーズ
ファミリー音楽プログラムvol.23 演奏会入門コンサート
サンデー・マティネ・コンサート vol.214 〈未来のホープコンサートvol.24〉
【第8回せんがわピアノオーディション受賞コンサート 五条玲緒インタビュー】
サンデー・マティネ・コンサートvol.216
サンデー・マティネ・コンサートvol.215 世界の楽器シリーズ
ファミリー音楽プログラムvol.23 演奏会入門コンサート
サンデー・マティネ・コンサート vol.214 〈未来のホープコンサートvol.24〉
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。