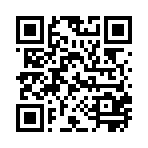2015年01月25日
伝統芸能ワークショップ発表会 せんがわ劇場「おらほ亭せんがわ落語会」~第一部 市民落語会~
1月12日に行われた、「おらほ亭せんがわ落語会」の様子をライターであり、市民サポーターでもある才目さんによるレポートでお届けします。
-------
せんがわ劇場は「次世代を担う子どもたちを育成する事業」に取り組んでいます。
「伝統芸能ワークショップ」もその取り組みのひとつで、
日本独特の話芸である「落語」に焦点を当て、講座を開催・運営してまいりました。
協力してくださるのは、市内で10年を超える活動歴をもつ落語愛好会「調布噺の会」の皆さんです。
本年度「落語ワークショップ」への参加者は、市内の小学生から大人まで計6名。
プロの落語家を講師に招いて稽古した成果を、年明け成人の日(1月12日)
「おらほ亭せんがわ落語会」の「第一部 市民落語会」として発表する運びとなりました。
「年の初めは落語で笑って過ごしたい」と多くのお客様がお越し下さいました。
受講生の皆さんが初々しく一生懸命高座をつとめる姿に、お客様は大いに笑い、盛大な拍手と声援を送ります。その温かい笑いが受講生にますます力を与えます。
心もほっこり、新春の初笑い。笑門来福。めでたく実りの多い市民落語会となりました。
今年度、講師にお招きしたプロの噺家さんは、四代目 柳家三語楼(やなぎやさんごろう)師匠。
2014年3月に真打ち昇進し、「三語楼」の名跡を継いだ若手注目株です。
三語楼師匠の司会進行のもと、本年度のワークショップの概要が紹介され、落語会となります。
「本日はようこそ市民落語会においでくださいました。
今回、稽古期間は約2ヶ月と短かったのですが、受講生の皆さんはよく頑張って稽古してくれました。
演目は各自の希望で選んだものです。
お客様の笑い声がなにより大きな力になります。どうぞ大いに笑ってください」。
「落語ワークショップ」参加者は<おらほ亭一門会>と呼ばれ、「おらほ亭」の屋号を名乗ります。
以下、出番順にお題と出演者を紹介していきましょう。
●『転失気(てんしき)』おらほ亭おばこ
トップバッター・おばこさんは、主婦でありながらフリーアナウンサーのお仕事もなさっているとのことで、口跡も滑らか、綺麗なお声の持ち主です。
演し物は、医者が言ったオナラを意味する「転失気」の意味がわからず、寺の和尚が知ったかぶりをするというお噺。
着物の着こなしも美しく、落語のセミプロといっても通じるほどの落ち着きと腕前でした。
●『平林(ひらばやし)』おらほ亭風りん(小学5年生)
丁稚の定吉が平林さん宅に手紙を届けるようお使いを頼まれる。
行き先を忘れないよう「ヒラバヤシ、ヒラバヤシ」と唱えながら歩くが、やがて忘れてしまい、
道行く人たちが口々に違う読み方を教えるというお噺。
風りん君が、大きな声で「タイラバヤシか、ヒラリンか、イチハチジュウのモークモク…」と呼び歩く姿がなんとも微笑ましく、しかも完璧に近く演じきるので、高座姿も堂々と見えてきます。
●『真田小僧(さなだこぞう)』おらほ亭りんりん(小学6年生)
りんりん君は昨年もおらほ亭に登場してお客をわかせた実力派です。
お題の『真田小僧』は、子どもがおとっつぁんに小遣いをせがみ、悪知恵を働かせて5銭、10銭とせびり取っていく噺。前座噺ではなく、東西の名人も取り組む「悪童噺」です。
子どもが子どもを演じる面白さ。しかも、古今亭志ん朝ばりの切れのいい口調で生意気な感じを出し、お色気シーンでは大人をハラハラさせる芸のうまさを見せます。
見事にお客を引き込み、噺半ばではあるものの、独自のオチで決めました。
日頃から落語に親しみ、研究熱心なことが分かる出来映え。昨年からの成長ぶりにも目をみはります。
将来楽しみな逸材といえるでしょう。
…仲入り(休憩)をはさんで…
●『まわり猫』おらほ亭小とら(小学4年生)
お題の『まわり猫』は飼い猫に強い名前をつけてやろうとして、まわりまわって結局「猫」になるという噺。
落語というより、童話かメルヘンでも聞いているような、ファンタジーの世界が広がっていきます。
小とら君は途中つっかえながらも、お客様の応援をうけ、最後までしっかりつとめました。
小学4年の落語初心者でも「ここまでできる」。当ワークショップの「質」と達成度を示す一席といえるでしょう。
●『猫の皿』平屋まつえい(大学生)
大学で落研に所属し、すでに屋号を持ち活動中です。
お題は、古美術を扱う商人が立ち寄った茶屋で高価な骨董品の皿を猫のエサ皿にしているのを見て、
その猫を買うといって亭主をだまし、皿を買い叩こうとする噺。
本人のやる気も十分な上、プロの指導を受け、見事に演じ切りました。
●『動物園』おらほ亭らいや(小学4年生)
トリは小学4年の女の子です。落語初挑戦のらいやさんはお笑いやモノマネが大好き。
『動物園』は新作落語で、あの桂枝雀も得意としたお題です。
高報酬にひかれ、動物園でライオンの真似をするアルバイトにありついた怠け者の男。
ぬいぐるみをかぶり檻の中をのしのし歩く仕草や、
いきなり「猛獣ショー」に駆り出されてあたふたする様子など、
語りだけでなく、身振り・手振り、体の動きも入れながら可愛く楽しく演じてくれました。
最後に、出番が終わって緊張も解けた受講生が高座に勢揃い。三語楼師匠が舞台の感想や出来映えをインタビューします。
それぞれ感想を述べ自己採点していくのですが、それにもまた個性が出て、客席に笑いが絶えません。
つねに笑顔で励まし指導してくださった三語楼師匠や「調布噺の会」の皆さんに感謝しつつ、
大きな拍手に包まれながら、舞台と客席が一体となった温かい落語会の幕が引かれました。

====================================================================================================
落語ワークショップの意義について「調布噺の会」の北田代表(高座名:三栄亭大笑)は、
「わずか2ヶ月足らず、5回ほどの稽古でしたが、受講生の皆さんは、落語の楽しさ、難しさのごく一部を感じられた事と思います。落語に限らず、人前できちんと話が出来るという事がどんなに大切なことかを考えるきっかけになったらと思います」と語っておられます。
三語楼師匠は続いて開かれた「第二部 家族で楽しめるプロの寄席」でトリをつとめられ、
『妾馬(めかうま)』というめでたい出世話を披露してくださいました。
ご来場くださった皆様、有難うございました。
来年度の落語ワークショップ、おらほ亭せんがわ落語会にもどうぞご期待ください。
(取材・文/ライター 才目)
-------
せんがわ劇場は「次世代を担う子どもたちを育成する事業」に取り組んでいます。
「伝統芸能ワークショップ」もその取り組みのひとつで、
日本独特の話芸である「落語」に焦点を当て、講座を開催・運営してまいりました。
協力してくださるのは、市内で10年を超える活動歴をもつ落語愛好会「調布噺の会」の皆さんです。
本年度「落語ワークショップ」への参加者は、市内の小学生から大人まで計6名。
プロの落語家を講師に招いて稽古した成果を、年明け成人の日(1月12日)
「おらほ亭せんがわ落語会」の「第一部 市民落語会」として発表する運びとなりました。
「年の初めは落語で笑って過ごしたい」と多くのお客様がお越し下さいました。
受講生の皆さんが初々しく一生懸命高座をつとめる姿に、お客様は大いに笑い、盛大な拍手と声援を送ります。その温かい笑いが受講生にますます力を与えます。
心もほっこり、新春の初笑い。笑門来福。めでたく実りの多い市民落語会となりました。
今年度、講師にお招きしたプロの噺家さんは、四代目 柳家三語楼(やなぎやさんごろう)師匠。
2014年3月に真打ち昇進し、「三語楼」の名跡を継いだ若手注目株です。
三語楼師匠の司会進行のもと、本年度のワークショップの概要が紹介され、落語会となります。
「本日はようこそ市民落語会においでくださいました。
今回、稽古期間は約2ヶ月と短かったのですが、受講生の皆さんはよく頑張って稽古してくれました。
演目は各自の希望で選んだものです。
お客様の笑い声がなにより大きな力になります。どうぞ大いに笑ってください」。
「落語ワークショップ」参加者は<おらほ亭一門会>と呼ばれ、「おらほ亭」の屋号を名乗ります。
以下、出番順にお題と出演者を紹介していきましょう。
●『転失気(てんしき)』おらほ亭おばこ
トップバッター・おばこさんは、主婦でありながらフリーアナウンサーのお仕事もなさっているとのことで、口跡も滑らか、綺麗なお声の持ち主です。
演し物は、医者が言ったオナラを意味する「転失気」の意味がわからず、寺の和尚が知ったかぶりをするというお噺。
着物の着こなしも美しく、落語のセミプロといっても通じるほどの落ち着きと腕前でした。
●『平林(ひらばやし)』おらほ亭風りん(小学5年生)
丁稚の定吉が平林さん宅に手紙を届けるようお使いを頼まれる。
行き先を忘れないよう「ヒラバヤシ、ヒラバヤシ」と唱えながら歩くが、やがて忘れてしまい、
道行く人たちが口々に違う読み方を教えるというお噺。
風りん君が、大きな声で「タイラバヤシか、ヒラリンか、イチハチジュウのモークモク…」と呼び歩く姿がなんとも微笑ましく、しかも完璧に近く演じきるので、高座姿も堂々と見えてきます。
●『真田小僧(さなだこぞう)』おらほ亭りんりん(小学6年生)
りんりん君は昨年もおらほ亭に登場してお客をわかせた実力派です。
お題の『真田小僧』は、子どもがおとっつぁんに小遣いをせがみ、悪知恵を働かせて5銭、10銭とせびり取っていく噺。前座噺ではなく、東西の名人も取り組む「悪童噺」です。
子どもが子どもを演じる面白さ。しかも、古今亭志ん朝ばりの切れのいい口調で生意気な感じを出し、お色気シーンでは大人をハラハラさせる芸のうまさを見せます。
見事にお客を引き込み、噺半ばではあるものの、独自のオチで決めました。
日頃から落語に親しみ、研究熱心なことが分かる出来映え。昨年からの成長ぶりにも目をみはります。
将来楽しみな逸材といえるでしょう。
…仲入り(休憩)をはさんで…
●『まわり猫』おらほ亭小とら(小学4年生)
お題の『まわり猫』は飼い猫に強い名前をつけてやろうとして、まわりまわって結局「猫」になるという噺。
落語というより、童話かメルヘンでも聞いているような、ファンタジーの世界が広がっていきます。
小とら君は途中つっかえながらも、お客様の応援をうけ、最後までしっかりつとめました。
小学4年の落語初心者でも「ここまでできる」。当ワークショップの「質」と達成度を示す一席といえるでしょう。
●『猫の皿』平屋まつえい(大学生)
大学で落研に所属し、すでに屋号を持ち活動中です。
お題は、古美術を扱う商人が立ち寄った茶屋で高価な骨董品の皿を猫のエサ皿にしているのを見て、
その猫を買うといって亭主をだまし、皿を買い叩こうとする噺。
本人のやる気も十分な上、プロの指導を受け、見事に演じ切りました。
●『動物園』おらほ亭らいや(小学4年生)
トリは小学4年の女の子です。落語初挑戦のらいやさんはお笑いやモノマネが大好き。
『動物園』は新作落語で、あの桂枝雀も得意としたお題です。
高報酬にひかれ、動物園でライオンの真似をするアルバイトにありついた怠け者の男。
ぬいぐるみをかぶり檻の中をのしのし歩く仕草や、
いきなり「猛獣ショー」に駆り出されてあたふたする様子など、
語りだけでなく、身振り・手振り、体の動きも入れながら可愛く楽しく演じてくれました。
最後に、出番が終わって緊張も解けた受講生が高座に勢揃い。三語楼師匠が舞台の感想や出来映えをインタビューします。
それぞれ感想を述べ自己採点していくのですが、それにもまた個性が出て、客席に笑いが絶えません。
つねに笑顔で励まし指導してくださった三語楼師匠や「調布噺の会」の皆さんに感謝しつつ、
大きな拍手に包まれながら、舞台と客席が一体となった温かい落語会の幕が引かれました。
====================================================================================================
落語ワークショップの意義について「調布噺の会」の北田代表(高座名:三栄亭大笑)は、
「わずか2ヶ月足らず、5回ほどの稽古でしたが、受講生の皆さんは、落語の楽しさ、難しさのごく一部を感じられた事と思います。落語に限らず、人前できちんと話が出来るという事がどんなに大切なことかを考えるきっかけになったらと思います」と語っておられます。
三語楼師匠は続いて開かれた「第二部 家族で楽しめるプロの寄席」でトリをつとめられ、
『妾馬(めかうま)』というめでたい出世話を披露してくださいました。
ご来場くださった皆様、有難うございました。
来年度の落語ワークショップ、おらほ亭せんがわ落語会にもどうぞご期待ください。
(取材・文/ライター 才目)
Posted by せんがわ劇場 at 16:59│Comments(0)
│落語
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |